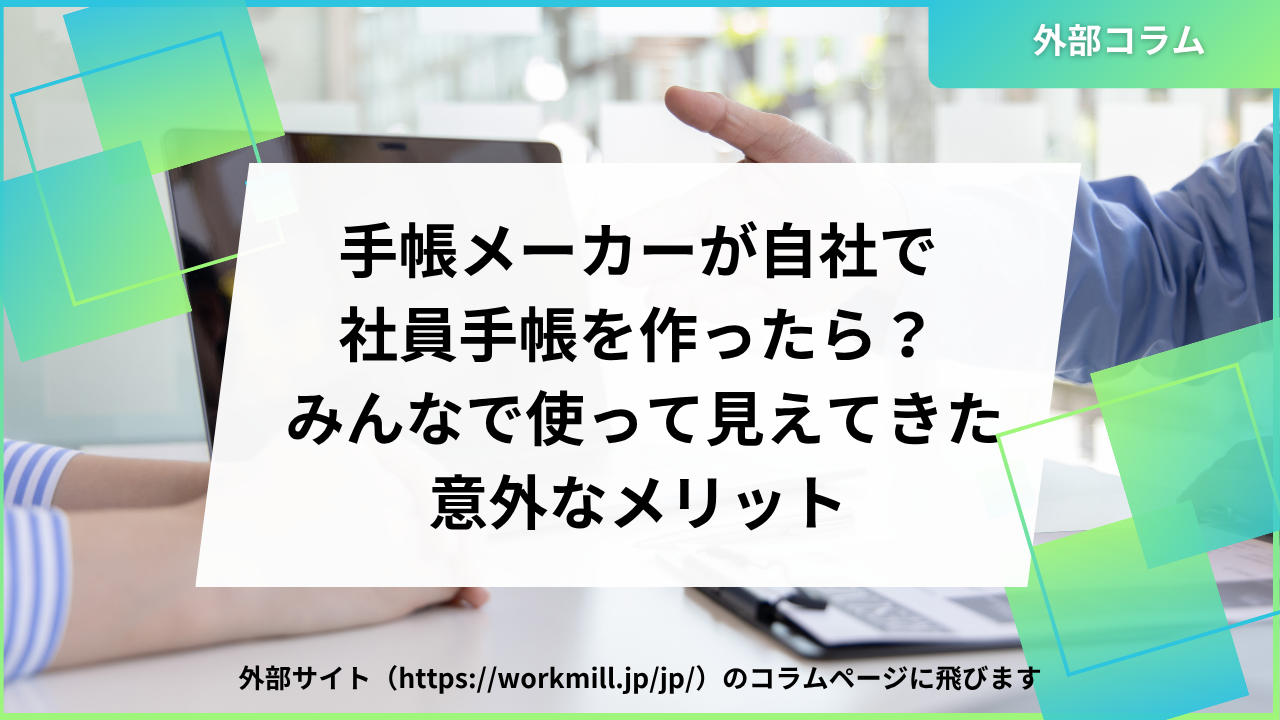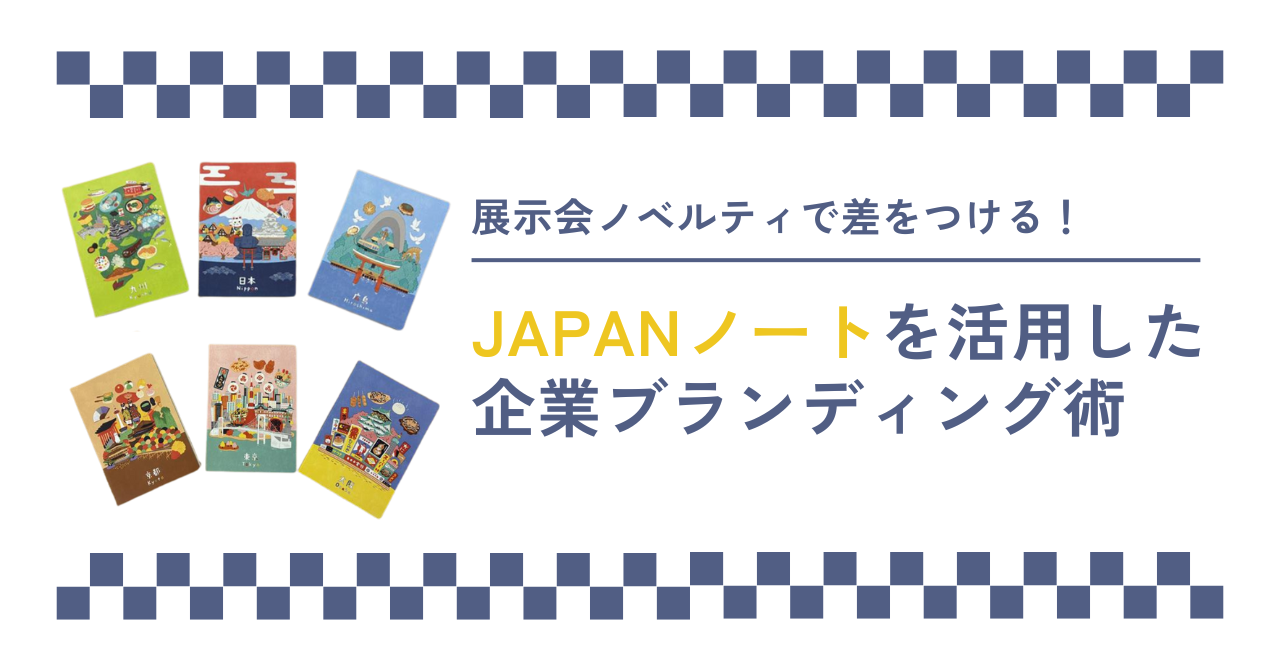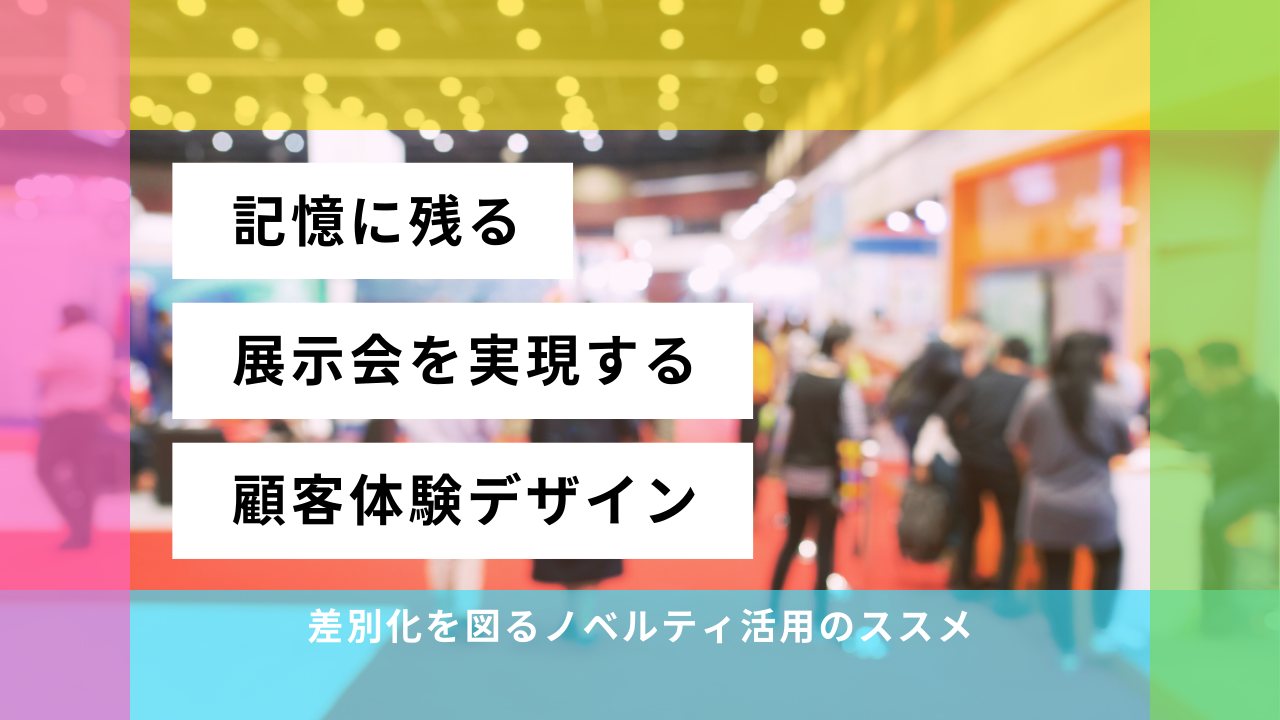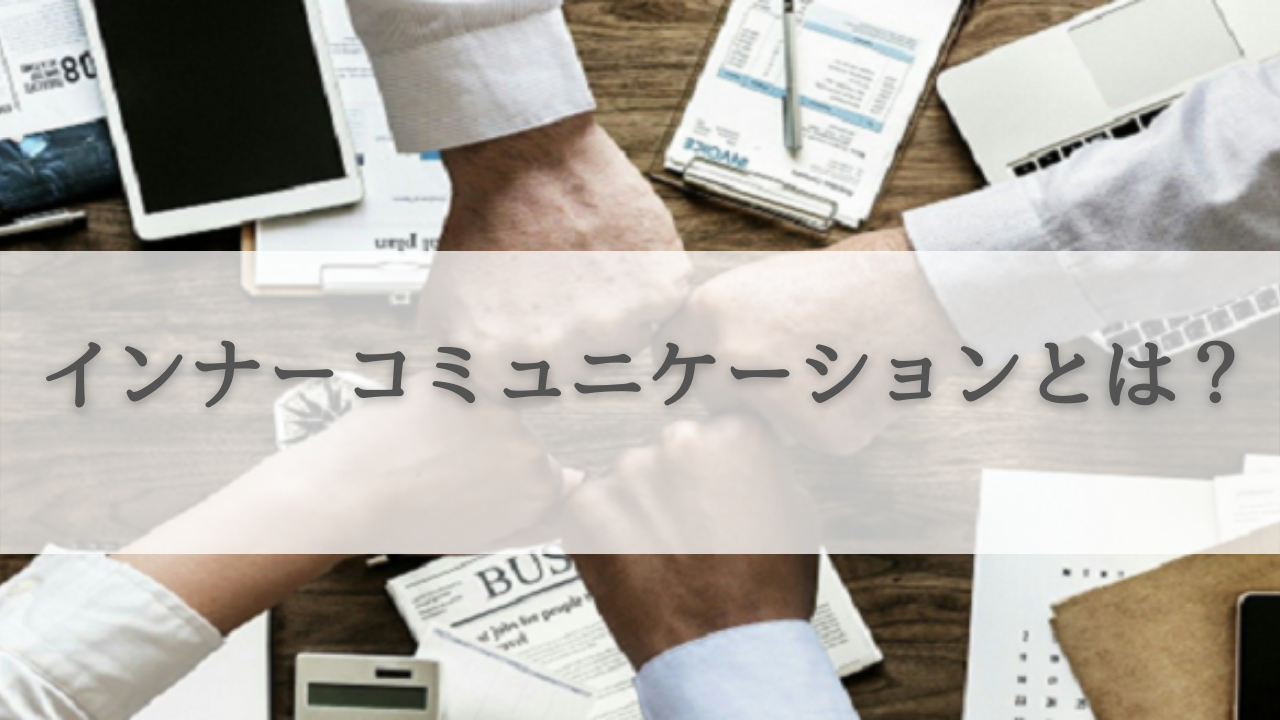
コロナ禍でのテレワークの増加により、社員同士のコミュニケーション不足が問題視されるようになりました。そこで、打開策としてインナーコミュニケーションを取り入れた企業経営に注目が集まっています。
しかし、社員に活発なコミュニケーションを求めたいと考えていても、具体的に何をしたらよいのかわからないという経営者・管理者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、インナーコミュニケーションの概要やそのメリット、社内コミュニケーションを活性化させる方法について解説します。
目次
インナーコミュニケーションとは

インナーコミュニケーションとは、部署の垣根を超え連携をスムーズにすることや、経営理念や企業のビジョンなどを社員に浸透させることを目的とした、社内で行われるコミュニケーションのことです。社内広報やインターナルコミュニケーションと呼ばれることもあります。
社内のコミュニケーションといっても、単に社員同士が仲良くなるためだけに行うのではありません。あらゆる部署や立場の社員が交流することによって、組織としての団結力を高めるとともに、経営理念や企業のビジョンを共有することで、同じ方向に向かって目的を達成する意識づけを行います。
インナーコミュニケーションを重視するメリット

インナーコミュニケーションを重視することには、次の3つのメリットがあります。
●すれ違いによる手間やコストの減少
●社員のモチベーションアップ
●離職率の低下
それぞれについて詳しく解説します。
すれ違いによる手間やコストの減少
インナーコミュニケーションが不足すると、互いの業務の進め方や考え方を知らないことで、すれ違いが生まれやすくなります。
例えば「資料を今日中に提出してほしい」という指示があった場合、「今日の定時までに提出が必要」という解釈をする人もいれば、「明日の朝確認できる状態になっていればいい」と考える人もいます。同じ会社の中であっても、普段からコミュニケーションをとっていなければ、あらゆるところにこうしたすれ違いが生まれる可能性が潜んでいます。
こうしたすれ違いを防ぐために、毎回細部まで確認するとなると、相応の手間や時間が必要です。インナーコミュニケーションを活性化させて普段から社員同士がコミュニケーションを取れていれば、すり合わせのための手間を減らせるため、生産性が高まる可能性があります。
社員のモチベーションアップ
社員に自社のビジョンや経営理念、価値観などを浸透させることを「インナーブランディング」と呼びます。
インナーブランディングを目的としたインナーコミュニケーションを行うことで、自分の仕事に価値を感じられるようになり、組織の一員としての帰属感が高まります。
このように、自分の仕事に価値を感じられるようになったり、帰属感が高まったりすることは、社員のモチベーションアップに繋がります。社員のモチベーションを高められれば、会社全体としての業績アップも期待できるでしょう。
インナーブランディングについては、次の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
インナーブランディングとは?目的や手法・メリット・デメリットを解説
離職率の低下
インナーコミュニケーションを活性化することで、離職率を下げられる可能性があります。
職場の人間関係の悩みは、退職の要因となります。厚生労働省の「令和2年雇用動向調査 」によると、転職入者が前職をやめた理由のうち「職場の人間関係が好ましくなかった」と答えた人の割合は、男性が8.8%、女性が13.3%で、男性の離職理由の4位、女性の離職理由の2位でした。
男性の離職理由の上位は次のとおりです。
|
離職理由 |
割合 |
|
その他の理由(出向を含む) |
31.3% |
|
定年・契約期間の満了 |
16.0% |
|
給料等収入が少なかった |
9.4% |
|
職場の人間関係が好ましくなかった |
8.8% |
|
労働時間・休日等の労働条件が悪かった |
8.3% |
また、女性の離職理由の上位は次のとおりです。
|
離職理由 |
割合 |
|
その他の理由(出向を含む) |
26.9% |
|
職場の人間関係が好ましくなかった |
13.3% |
|
定年・契約期間の満了 |
12.7% |
|
労働時間・休日等の労働条件が悪かった |
11.6% |
|
給料等収入が少なかった |
8.8% |
「定年・契約期間の満了」が積極的に離職したい理由ではないことを考えると、職場の人間関係は、自ら希望して退職する理由の中で高い割合を占めていると言えます。
インナーコミュニケーションの活性化によって人間関係を構築できていれば、離職率を下げられる可能性があります。
インナーコミュニケーションの方法
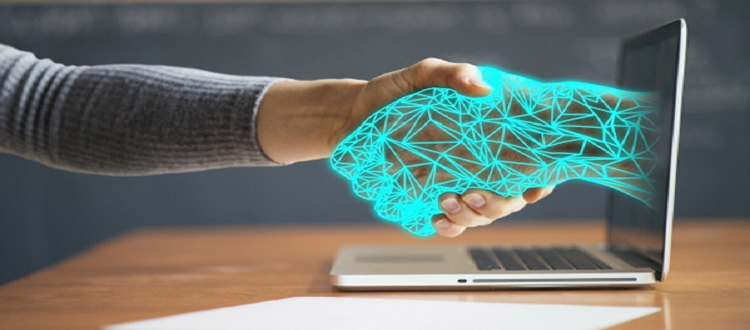
インナーコミュニケーションの方法として考えられるのは次の5つです。
●イベントの実施
●社内報の発行
●社内SNSの活用
●社員手帳による理念の周知
●オフィスレイアウトの変更
それぞれについて、詳しく解説します。
イベントの実施
社内でイベントを実施することで、インナーコミュニケーションを活性化できます。大規模なイベントでなくても、社員同士気軽に雑談できる場を設けることで、コミュニケーションの活性化が期待できます。
インナーコミュニケーションに役立つイベントの例として、次のようなものが挙げられます。
●社員の表彰
●ランチ会
●ゲーム大会
インナーコミュニケーションを意識してイベントを開催する場合には、社員同士の交流が生まれやすいよう意識して企画を立てましょう。例えばゲーム大会であれば、普段交流が少ない部署同士でチームを組むといった方法があります。
上記のイベントは、オンラインでも開催できます。個々人の都合に合わせて参加しやすいオンラインのイベントは、オフラインのイベントと比べて気軽に参加できるのが特徴です。
特に、テレワークの社員が多い企業で社内コミュニケーション不足を感じている場合には、オンラインイベントの開催に挑戦してみてはいかがでしょうか。
社内報の発行
インナーコミュニケーションのためには、社内報を発行するのも有効です。社内報を発行することで、他部署が何をしているのか、どんなことに取り組んでいるのかなどを知ることができます。
作成した社内報は、印刷して掲示板などに掲示してもよいですが、オンラインでの発行も有効な方法です。オンラインであれば、掲示板に貼り出す手間がかからないため、手軽に発行できることに加え、遠隔地の支所やテレワークの社員にも同時に共有できます。
社内SNSの活用
社内SNSとは、社員同士の相互理解や業務の効率化を目的として、社員のコミュニケーションを促す、いわゆる社内版「Facebook」のようなツールです。社内SNSを導入することで、業務に関する情報をスムーズにやりとりできることに加え、部署の垣根を超えた交流も行いやすくなります。
雑談用のスペースを作るなど、業務以外の場面で社員同士がコミュニケーションを取れる場を作るのもおすすめです。
社内SNSを利用することで、部署や物理的な距離を問わず、社内の誰とでもコミュニケーションを取れる環境が作れます。
社員手帳による理念の周知
インナーコミュニケーションとして理念やビジョンを共有する方法のひとつが、社員の目につきやすい場所に掲載しておくことです。
この際おすすめなのが、社員手帳に記載する方法です。ビジネスシーンで使いやすい手帳に掲載することで、理念が周知されやすくなります。
社内にポスターなどを掲示する方法もありますが、ポスターの場合、テレワークなどで出勤が少ない社員は理念やビジョンを目にする機会が減ってしまう点がデメリットです。手帳であれば、社員がそれぞれの場所で働いていても、仕事の合間に理念やビジョンが目に入る環境を作れます。
オーダーメイドで情報を掲載できる社員用手帳については、次のリンク先に情報を掲載していますのでぜひご覧ください。
社員用手帳
オフィスレイアウトの変更
オフィスレイアウトを変更することで、コミュニケーションが活性化する場合もあります。他部署とも気軽にコミュニケーションがとりやすいよう、導線や作業スペースを考えてレイアウトを作ってみてください。
コーヒーマシンを置いた休憩スペースなど、共有スペースを作るとよりコミュニケーションが活発になります。
その日の仕事の都合や気分に合わせて自由に席を選べる、フリーアドレス制を取り入れるのも有効な方法です。個人の席が決まっていると、離れた席の人と話をする機会はほとんど無いですが、フリーアドレス制を導入すると、社内のあらゆる人と会話が発生する可能性があります。
インナーコミュニケーションの活性化で多くのメリットが得られる

インナーコミュニケーションとは、組織力を高めることを目的とした、社員同士のコミュニケーションのことです。インナーコミュニケーションが活性化することで、離職率の低下や社員のモチベーションアップなどさまざまな効果が得られます。
インナーコミュニケーションの活性化には、社員用手帳による理念の周知やイベントの開催などが有効です。この記事を参考に、インナーコミュニケーションの活性化に取り組んでみてはいかがでしょうか。