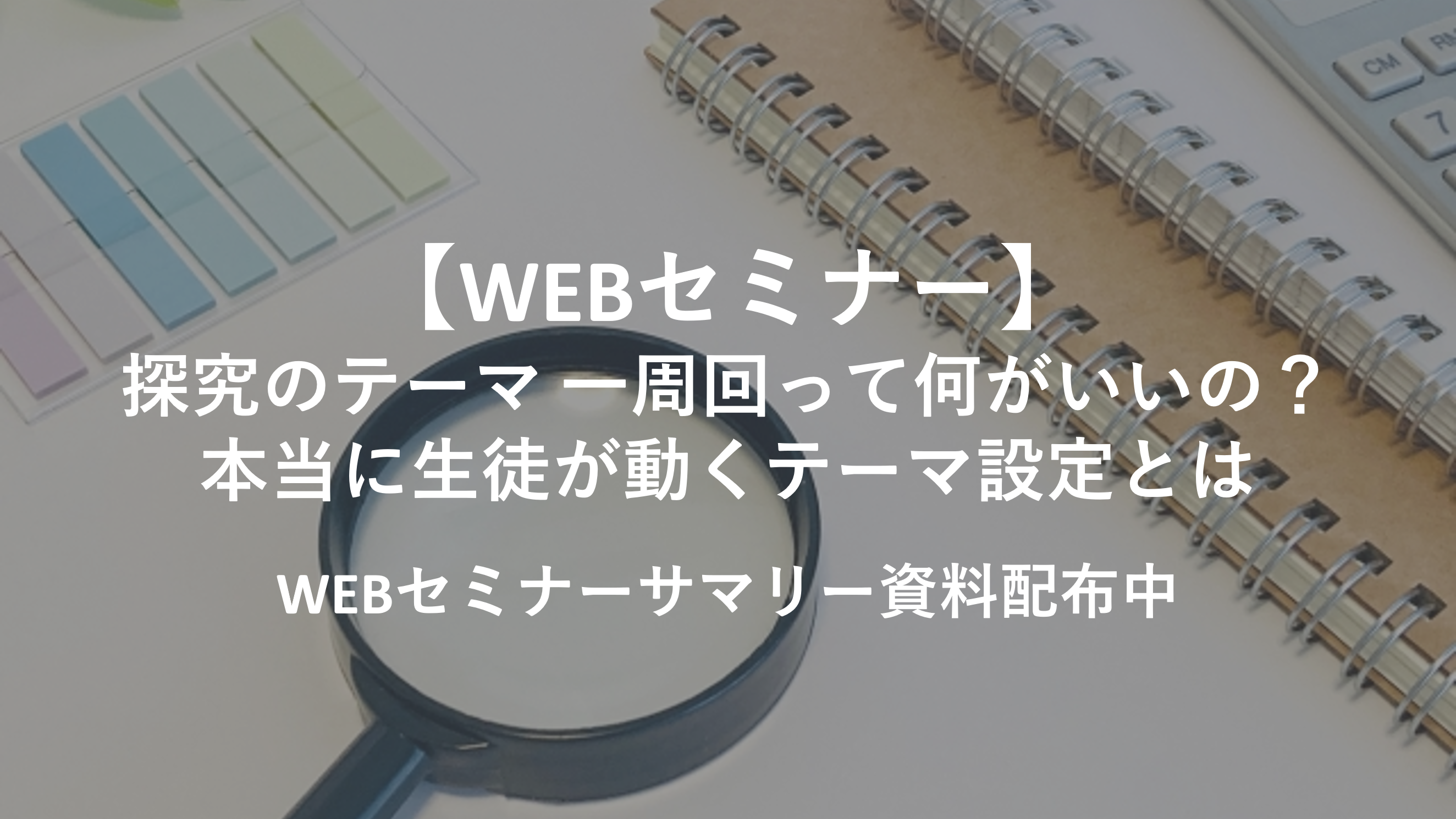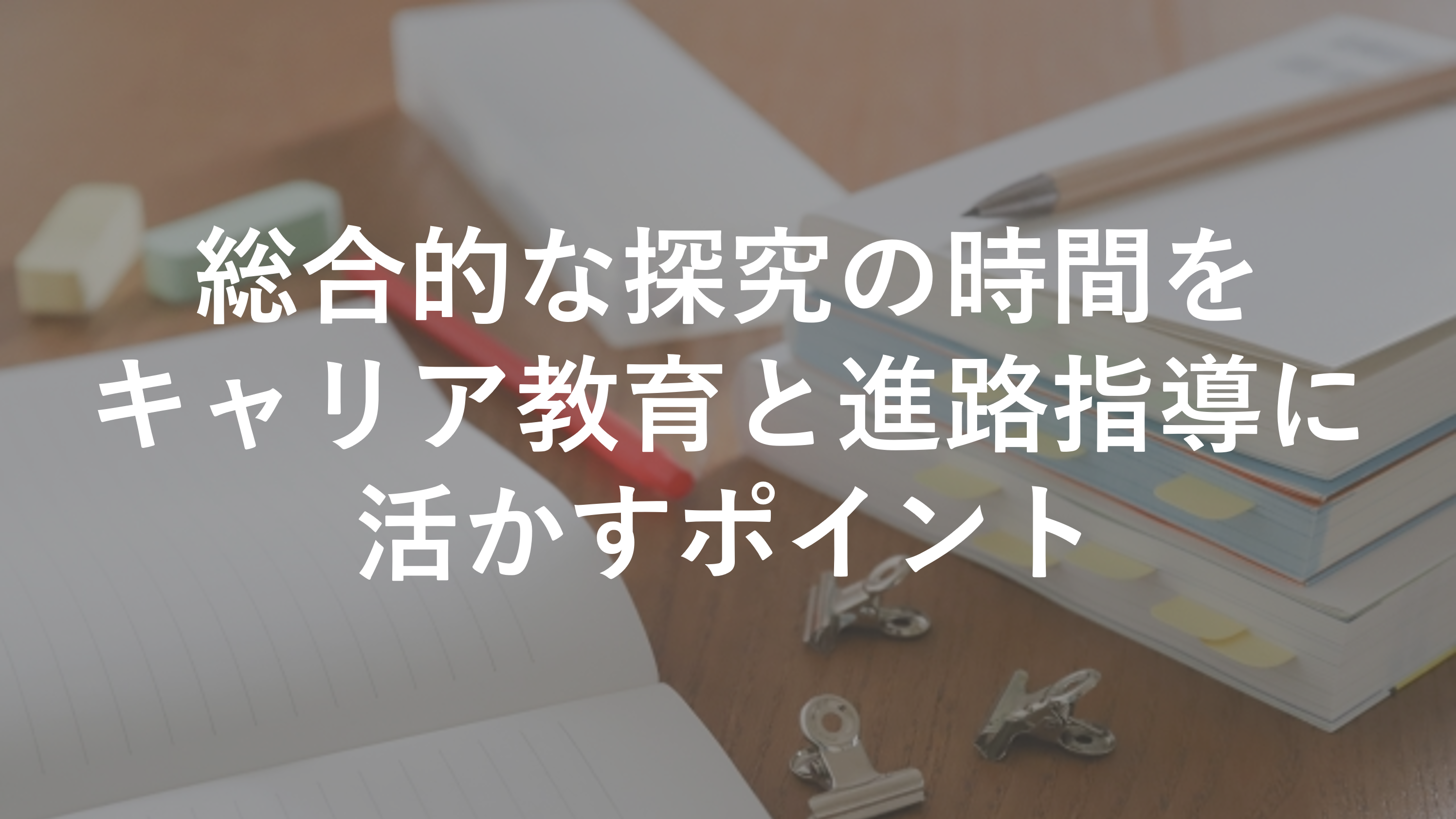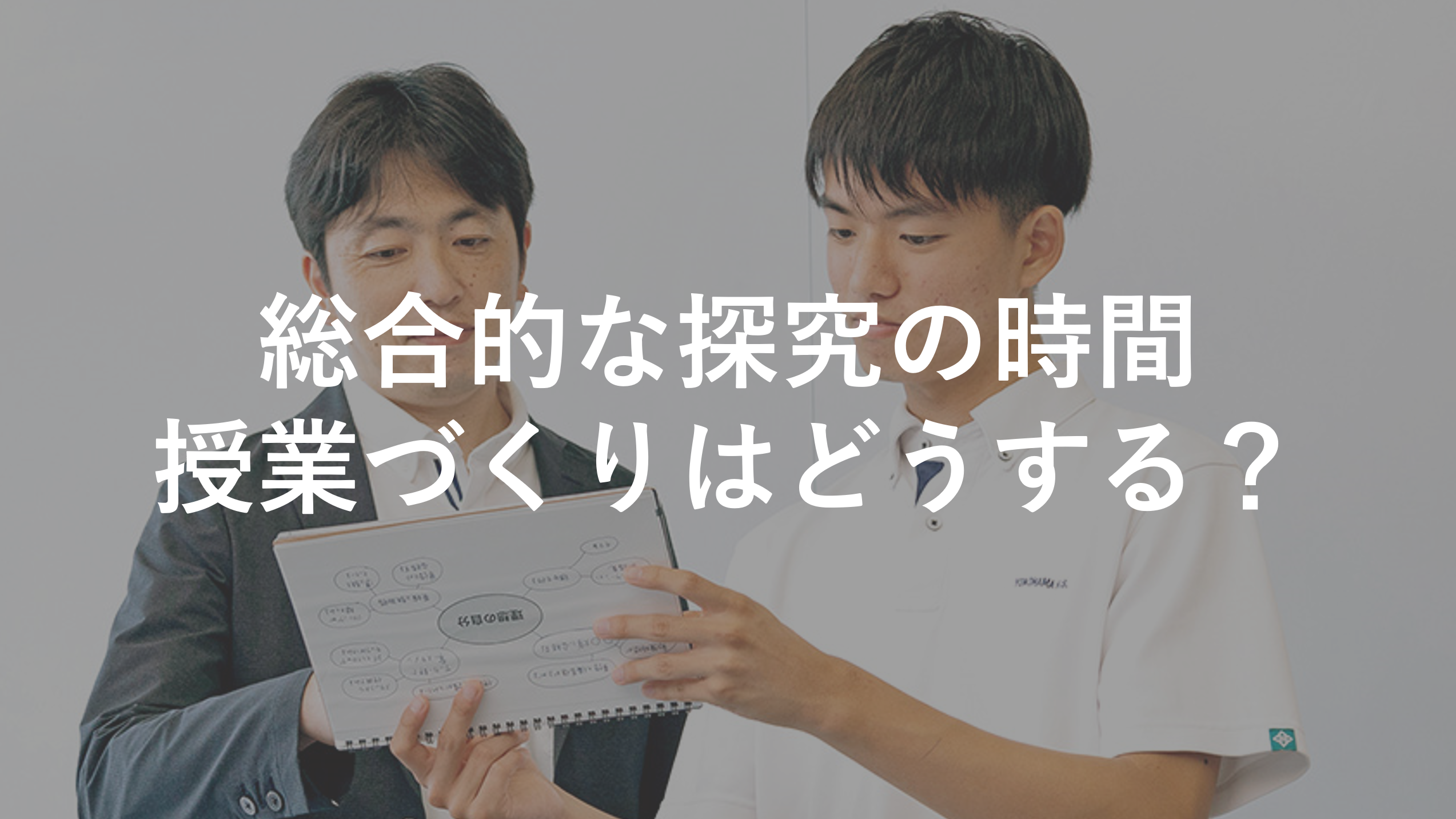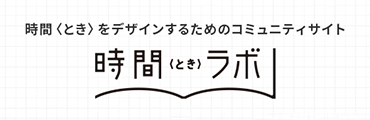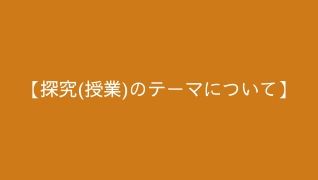
探究活動においてどのようなテーマ設定をすべきかとても悩ましいことではないでしょうか。
特に生徒が意欲的に取り組めるテーマを設定することが難しいのではないでしょうか。
このような状態になる原因の一つとして「生徒の自己肯定感の低さ」が考えられるのではないでしょうか。
自ら課題を設定し、自ら解決するために行動をするといっても自己肯定感の低い生徒にとってはあまり現実味がないです。
頭の中で求められることは分かっていても、実際の行動に落とし込んだときに解決できそうというイメージや興味がないと本気になれることは難しいのではないでしょうか。
ーおすすめ記事ー
生徒は課題設定が苦手
https://www.noltyplanners.co.jp/scola/column/1237653_2572.html
そこで練習(※)として簡単にできるテーマを考えてみました。
条件は生徒にとって身近であることとすぐに解決策を実行できそうなことです。
※私たちは探究活動を『生徒が自分で課題を発見し、解決するための資質・能力を育成する』活動と捉えているため
いきなり探究活動を行わずに探究活動を練習しても良いと考えています。
『教室のレイアウトを全員が集中して授業を受けられる形に変える』
教室は通常スクール形式です。しかし、この机の並びは本当に全員が集中して授業に臨めるレイアウトでしょうか。
生徒たちに考えさせ、レイアウト案を発表しどのレイアウトにするか決めさせても面白いのではないでしょうか。
これはすぐに実施することができますし、その効果もアンケートなどですぐに検証することができます。
上手くいかなければ他の案に変えることもできます。
また、普段の授業から全員が集中しているかということを生徒が気にすることもできます。
『テスト勉強をしっかり行って定期考査に望む』
定期考査に対して2週間前からテスト勉強を行う生徒は多いのではないでしょうか。
しかし、テスト勉強といってもやり方は千差万別です。
他人の考査の結果は気になりますが、勉強方法や計画については意外と目が向かないものです。
そこで考査2週間前に『クラスメイトにおススメの学習計画』を各班で考えて紹介することはいかがでしょうか。
探究活動は実社会や実生活と繋がって行う授業ですが、大きすぎるテーマからスタートすると少し現実味が弱くなります。
まずは身近ですぐに解決できそうなことがテーマとして良いです。
また、生徒自身の喜怒哀楽をテーマにしても良いと思います。
悲しかったことや怒ったことから課題を見つけて解決策を考えてみる。
自分のことからスタートしているのでより興味を持って活動できるのではないでしょうか。
自己理解を促進する
https://www.noltyplanners.co.jp/scola/notebook-light/index.html
また、SDGなどのテーマを扱う場合にもその範囲を世界や日本などの大きな範囲から入らずにまずは教室や学校に関連付けたところからスタートし、徐々に大きくすることが良いのではないでしょうか。
例)環境問題をテーマにしてもまずは学校全体のゴミの量を知ることからスタートするなど
SDGs
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
また、文部科学省のホームページには「総合的な学習の時間」応援団ページというものがあるそうです。
各省庁を中心に様々なテーマがあり連絡先もあります。
「総合的な学習の時間」応援団ページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/syokatsu.htm