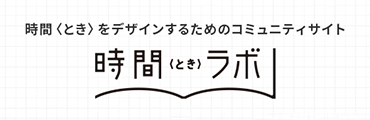先生の声
ノートの見やすさとアレンジできる柔軟性が導入の決め手
今まで本校の探究学習は進路について考えるというテーマで独自に行っていました。教材の準備については、教師が自分で用意するという意識を持つ先生が多く、外部の教材には物足りなさを感じることがありました。しかし、外部の教材を活用しつつも、自分たちの理論を組み合わせることで、良い授業が実現できるのではないかと感じていました。今年度から探究の授業を担当することになり、複数の会社の教材を検討する過程で、NOLTYスコラ探究プログラム基本編(以下、基本編)に出会うことができました。この教材はノートが厚すぎず、メモを取るためのスペースも十分に確保されており、視覚的にもすっきりしていて見やすいことが魅力です。さらに授業用のスライドも付属しており、これをアレンジすることが可能な点も魅力的であったため、基本編を活用することを決めました。
忙しい先生でもスムーズに授業を進行できる
特にこの基本編は授業用スライドのスピーカーノートに教員用のセリフが入っていた点が良かったです。極端な話、全てを読み上げるだけでも授業を進められます。授業開始前に20分程度見ておけば流れがつかめるため、忙しい先生にとっても助かるポイントでした。学年会議の際にも授業進捗や準備の話し合いを行うのですが、少し説明するだけで先生たちは内容を理解し、授業に落とし込んでくれたので、使いやすさを感じました。
付属の授業用スライドに工夫を加えることで、より良い授業に
また、より学習がスムーズに進むようにスライドに一工夫を加えていました。例えば、スライド1枚に対して話す内容が多いとき、スライドにアニメーションを追加し、クリックするとイラストが出たり、注目ポイントがわかりやすいようにしたりするなどのアレンジです。生徒も集中力を切らさずに授業に臨むことができたので、進行がスムーズになったと思います。
探究の基礎を学び、進路へ繋げる
1年生では、基本編を使い基礎的な探究学習の進め方や姿勢を学びました。2年生では、より社会や大人と触れ合う機会を持ってほしいという思いから、起業体験を通してアントレプレナーシップを養うNOLTYスコラ 探究プログラムMyBiz編を活用する予定です。3年生では進路も見据えながら自分で課題を見つけて探究します。1、2年生の間で教材を使って調べ方などの基礎的な方法論を身につけてもらい、3年次の探究に繋いでいってもらえたらいいなと思います。
自分で考えて表現できる力を身につける
探究の学習では失敗を恐れない力を身につけてほしいと思います。あらかじめ答えがあるものを丸写しする、言われたことしかやらないではなく、失敗しても良いから、自分で考えて、自分の意見を表現できるようになって欲しいです。 基本編には自分で考えて文章を書く時間やスペースが設けられているので、その訓練にはなると思います。言語化が苦手な生徒もいますが、スペースの半分ぐらいでも書けるようになれば良いかなと思います。
基本編を通して自分を見つめ直すきっかけになった
教員の中でも正直、最初はどうなることやらという不安はありました。ですが、基本編という土台となる教材があることによって、先生たちもうまく活用しながら授業を進めていたと思います。 生徒も授業の後半からは自分で考えて作業する時間が多くなり、集中して取り組む姿が見られました。自分自身を見つめ直す良いきっかけになったのではと思います。また自分の考えを言語化し、紙に残すことで、より深い学びができたと思います。全体として楽しみながら授業に取り組むことができました。
_3.jpg)