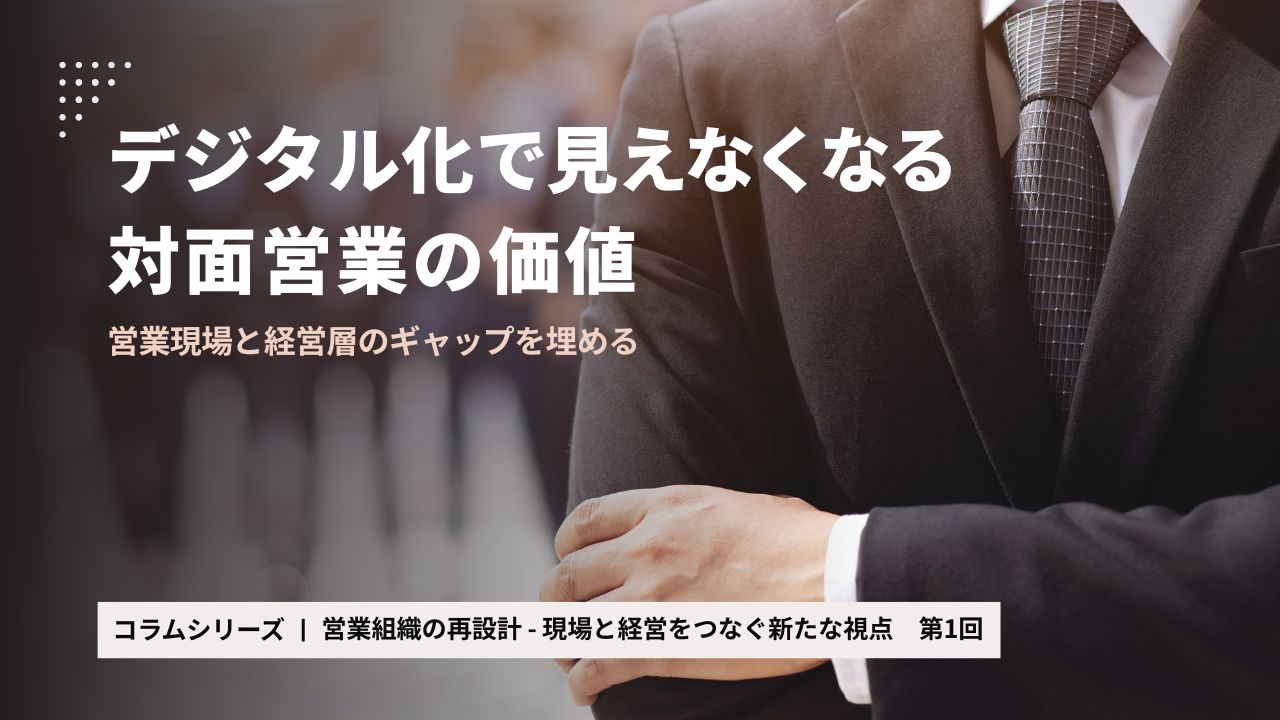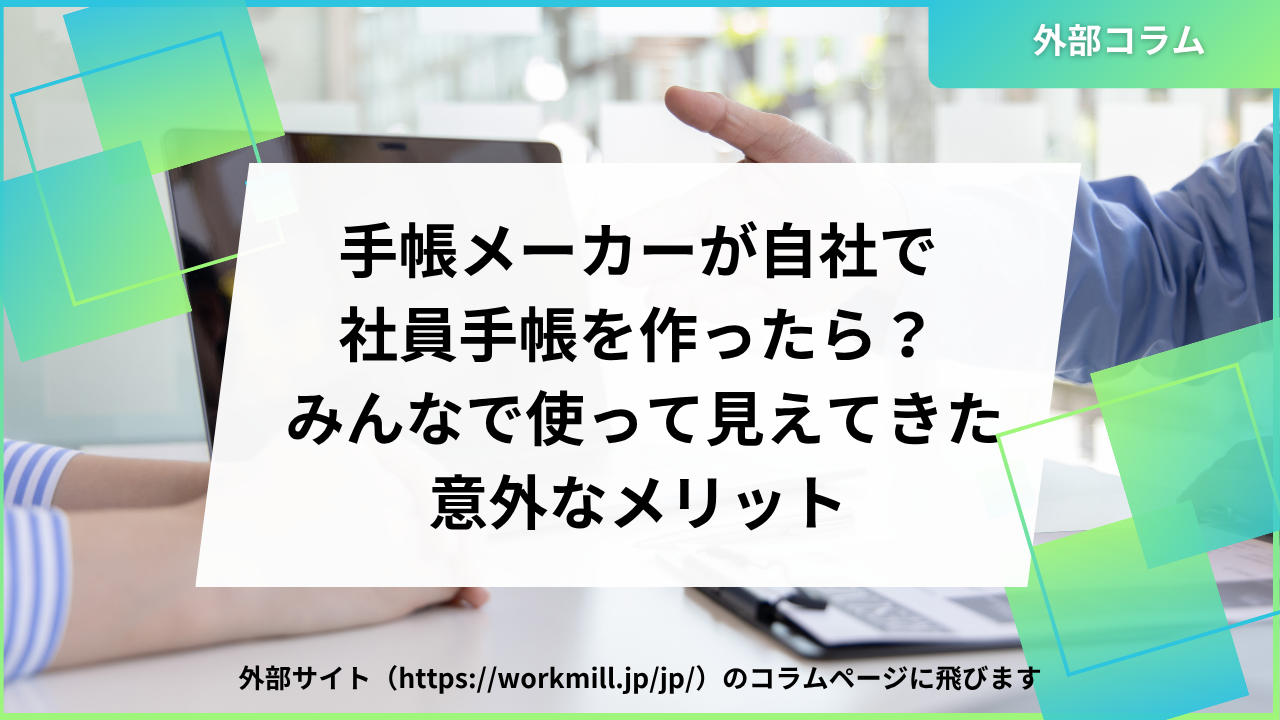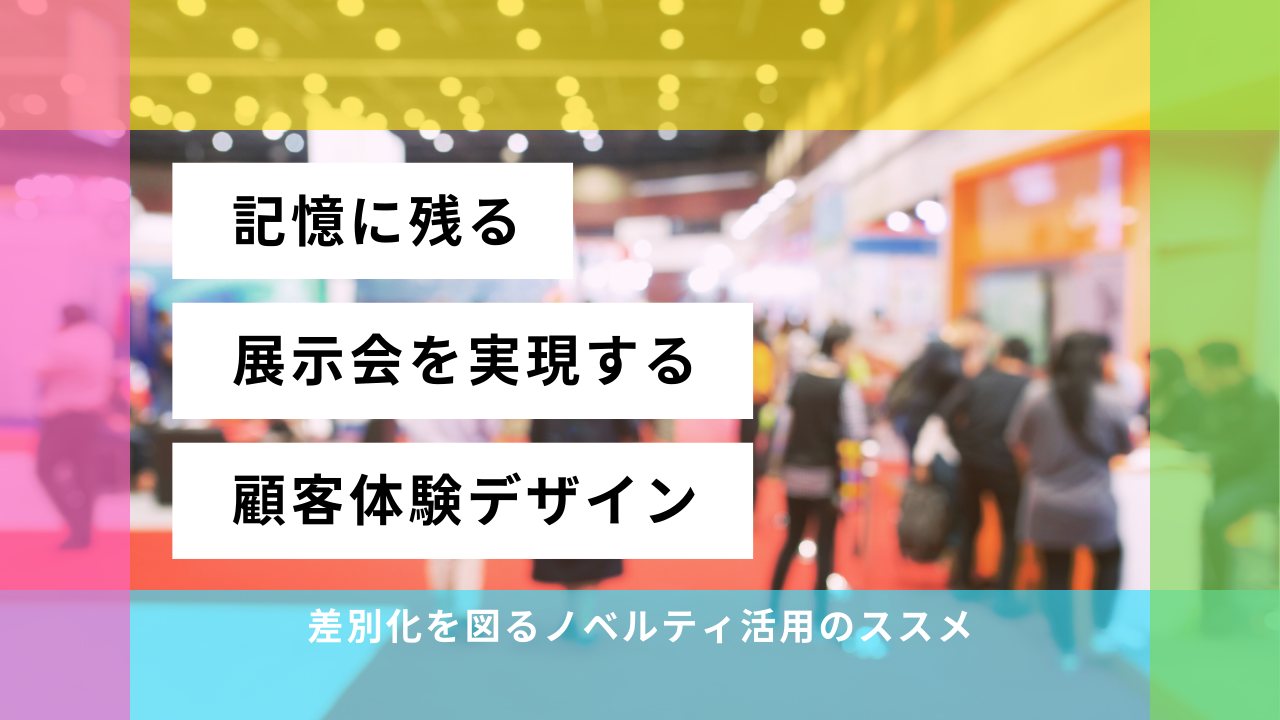「キャリアオーナーシップ」という言葉が近年話題になっています。しかし、意味や取り組むメリットがよくわからない、という方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、キャリアオーナーシップの意味や話題になっている理由などについて解説します。
企業が取り組んでいるキャリアオーナーシップの事例についても紹介します。
目次
キャリアオーナーシップとは

キャリアオーナーシップとは、自分のキャリアにおいて「どうしたいのか、どうなりたいのか、どうあるべきなのかを主体的に考えること」です。
また、理想のキャリアの実現に向けた主体的な行動という意味でも使われる場合があります。
人材派遣会社のパーソルグループでは、2020年からキャリアオーナーシップについて探求を開始して、概念について公表しました。
1.軸を起点にありたい自分の生き方を構想する
2.自己を理解し、仕事を通して自己実現・表現する
3.心の内側にある好奇心やモチベーションを起点に行動する
4.新しいものを受容し、自己変容を積み重ねる
5.自分自身・周囲と調和し、好循環を生み出す
上記5つを中心概念として、キャリアオーナーシップについて整理しています。(キャリアオーナーシップ 概念整理より)
ちなみに、キャリアオーナーシップはほとんど同じ意味の「キャリア自律」と表現される場合もあります。
比較的新しい造語として近年使われるようになりました。
キャリアオーナーシップが話題になっている背景

キャリアオーナーシップが話題になっている背景は、以下のとおりです。
●平均寿命が長くなって「人生100年時代」といわれるようになった
●従来の日本型の雇用制度(終身雇用と年功序列)を撤廃する企業が増えた
まず、医療技術の進歩によって平均寿命が長くなり、生きるために働く年数も延びた、という理由が挙げられます。人生100年時代といわれ、長い人生を生きるためには働いて収入を得る必要があります。
また、終身雇用や年功序列のような日本型の雇用制度を撤廃する企業が増えた点も理由です。就業や給与の保証がされなくなったため、自ら考えてキャリアを形成することが求められます。
企業としては、従業員に対して画一的なキャリアパスを用意するのではなく、さまざまな働き方を後押しできるような体制の整備が求められる時代になりました。
個人と企業の関係性が変わるなかで、キャリアオーナーシップという考え方が注目されています。
キャリアオーナーシップに企業が取り組むメリット

企業がキャリアオーナーシップに取り組むメリットは以下の3つです。
●生産性が向上する
●優秀な人材の確保につながる
●モチベーションやエンゲージメントが上昇する
キャリアオーナーシップは従業員個人の考え方として重要ですが、企業にも取り組むメリットがあります。それぞれのメリットについて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
生産性が向上する
まず、生産性が向上するメリットがあります。企業がキャリアオーナーシップを推進した結果、自ら考えて行動する「自律型人材」が増えて、最終的には生産性アップにつながるでしょう。
また、生産性アップの効果をさらに高めるには、従業員が知識やスキルを習得し、専門性を高められるような配慮が必要です。個性に合わせた能力を最大限に発揮できる環境を整えましょう。
優秀な人材の確保につながる
キャリアオーナーシップを推進する企業は、優秀な人材の確保がしやすいです。キャリア形成に意欲的な優秀な人材は、社員のキャリア開発支援を積極的に行う企業を魅力的と感じます。
また、キャリアオーナーシップに取り組む姿勢は、採用活動のアピールに活用できます。キャリアアップに積極的な求職者など、優秀な人材の確保がより容易になるでしょう。
モチベーションやエンゲージメントが上昇する
キャリアオーナーシップでは、上司と社員間で積極的に対話を行い、お互いの理解を深めます。1on1ミーティングやキャリア研修などによりコミュニケーションが増え、企業に対するエンゲージメント(信頼感)の上昇や離職率を下げる効果が期待できるでしょう。
また、キャリアオーナーシップを推進すると、個人が明確な将来のビジョンを持ち、意欲的に仕事に取り組みやすくなります。前向きに取り組む姿勢や結果に対する評価は、モチベーションアップにもつながるでしょう。
キャリアオーナーシップの取り組み事例

キャリアオーナーシップの取り組み事例について紹介します。
事例①社内インターン制度
事例②キャリア研修
事例③社内公募制度
企業でキャリアオーナーシップのサポートに取り組む際、ぜひ参考にしてください。
事例①社内インターン制度|富士通株式会社
富士通株式会社は、社内インターン制度を取り入れています。長期と短期、希望に合わせてチャレンジできる環境です。
ポスティングは長期で別のポジションに挑戦したい社員が利用できる制度です。富士通グループ内の空きポジションは常時公開されており、いつでもチャレンジできます。海外の部署も募集中です。
短期では、富士通グループ内の別の組織で3~6ヶ月を目処に移動できる「Jobチャレ!!」という制度があります。ほかにも1on1など、グループ全体でキャリアオーナーシップを推進している企業です。
事例②キャリア研修|株式会社JTB
株式会社JTBは、定期的なキャリアアップ研修が特徴です。入社4年目までの若手向けに「ヤングプロフェッショナルプログラム」という、研修プログラムを用意しています。
中堅からベテランについては、キャリアデザイン研修があります。28歳・36歳・46歳・56歳の社員が対象です。また、29歳と56歳の社員全員が人事部との面談を行う「キャリアデザイン面談」情報提供や対話の機会を意図的に作っています。
事例③社内公募制度|ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社では、社内公募制度があります。
管理職を含む社内のオープンポジションを公開しているため、興味があるポジションにチャレンジ可能です。2022年からは富士通グループのような「社内インターンシップ」制度もでき、6ヶ月間別の仕事ができるようになりました。
企業がキャリアオーナーシップに取り組む場合の注意点

キャリアオーナーシップに取り組むメリットがある反面、以下のような注意点も存在します。
●キャリアオーナーシップと企業目標の両立が難しい
●キャリアオーナーシップ関連のコストが増える
次に、企業がキャリアオーナーシップに取り組む際に注意すべき点を詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
キャリアオーナーシップと企業目標の両立が難しい
企業が掲げる目標と、キャリアオーナーシップの両立は難しいです。例えば、従業員個人が将来のビジョンについて考えた結果、そのビジョンが所属する会社内で実現できないと判断されてしまった場合は、離職するリスクが高まるでしょう。
また、組織の目標を優先し過ぎると個人のキャリア形成がうまくいかない場合があります。ルーティンが多い部門でポジション変更せずに長年過ごすと、結果的に将来的に目指せるキャリアの幅が狭くなります。
キャリアオーナーシップに取り組む際は、個人キャリアと企業目標のバランスが取れるようにパーパス経営やジョブ型雇用、公募型の異動制度などを一緒に取り入れるのがおすすめです。また、制度を取り入れるだけではなく、定期的にパーパスやそれらの制度について丁寧にコミュニケーションしていくことが大切です。
キャリアオーナーシップ関連のコストが増える
キャリアオーナーシップに取り組む際、さまざまな費用が掛かります。例えば、教材費や研修費がわかりやすいコストです。
また、担当する人材の配置や社内公募制度などの整備も必要になる可能性が高いです。
キャリアオーナーシップに取り組む際は事前に予算や、どのように環境を整備するかを決めるのがよいでしょう。
キャリアオーナーシップについて考えよう

人生100年時代で、変動が激しい社会になり、キャリアオーナーシップという考え方が大切になっています。
個人は自分で将来の働き方について考え、企業は多様性を受け入れてサポートすることが求められています。
今一度、キャリアオーナーシップについて考えてみてはいかがでしょうか。人事を担当している方も、自社での取り組みについて、ぜひ考えてみましょう。