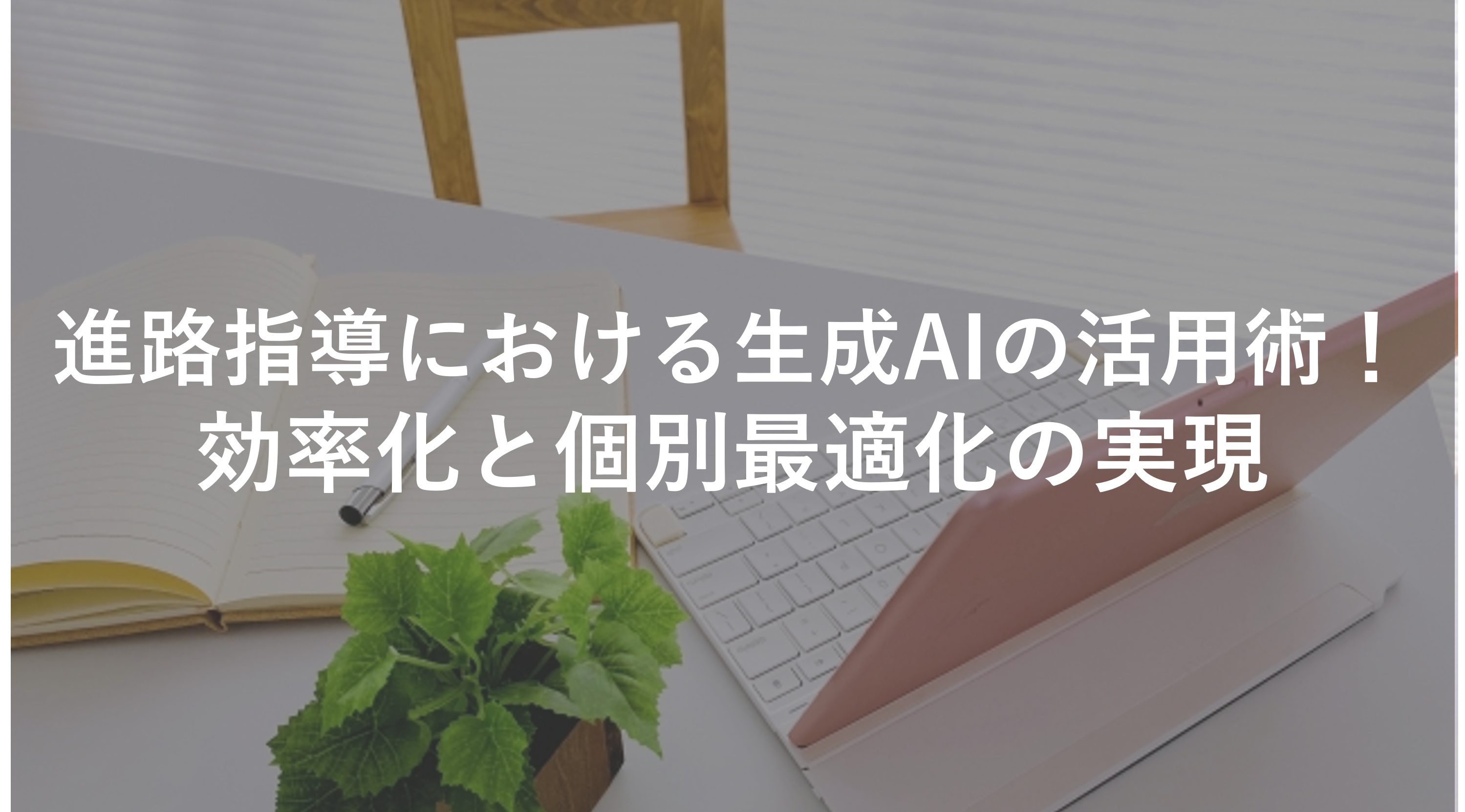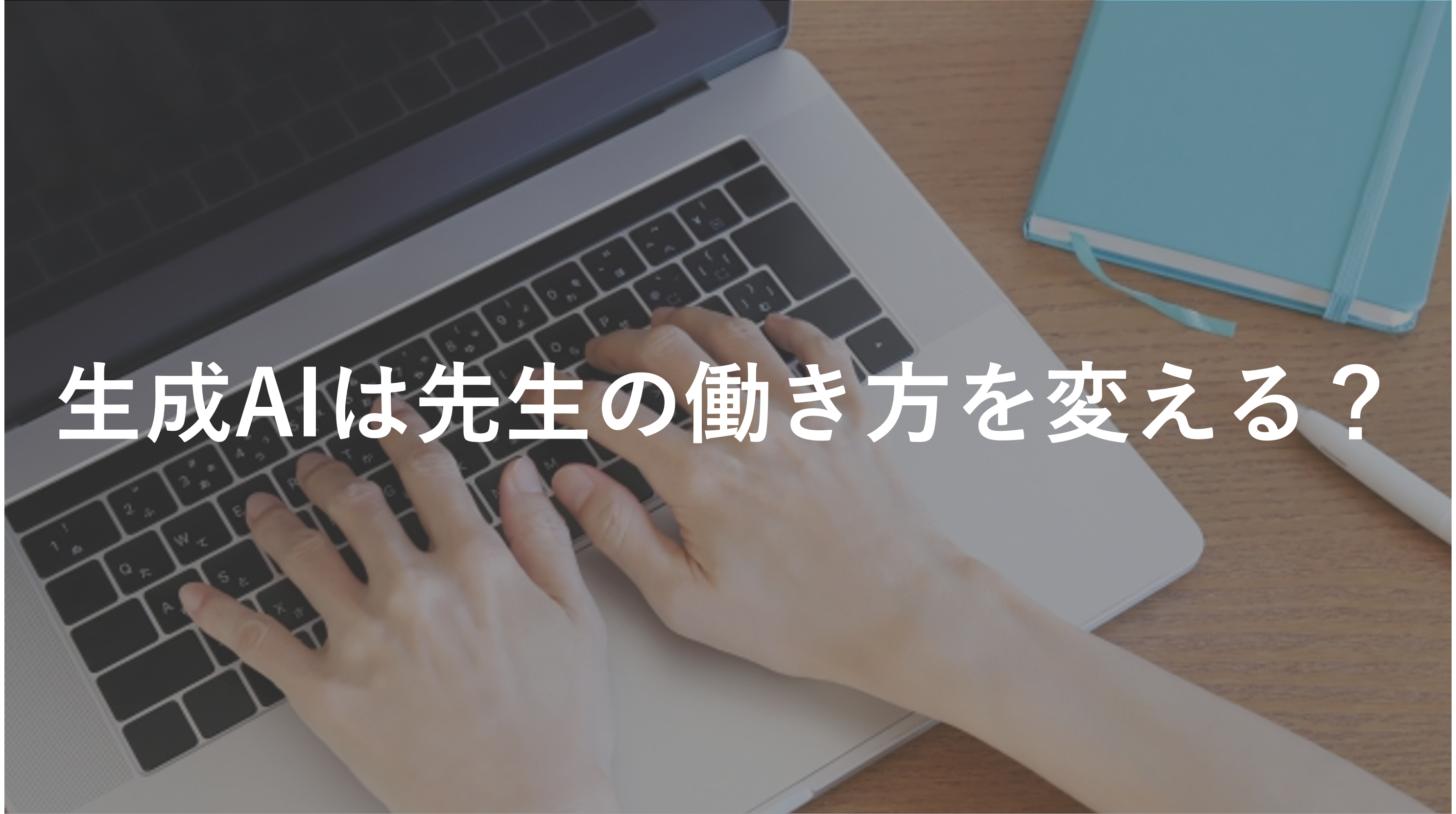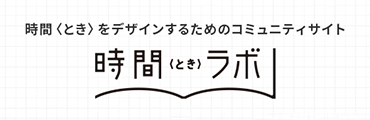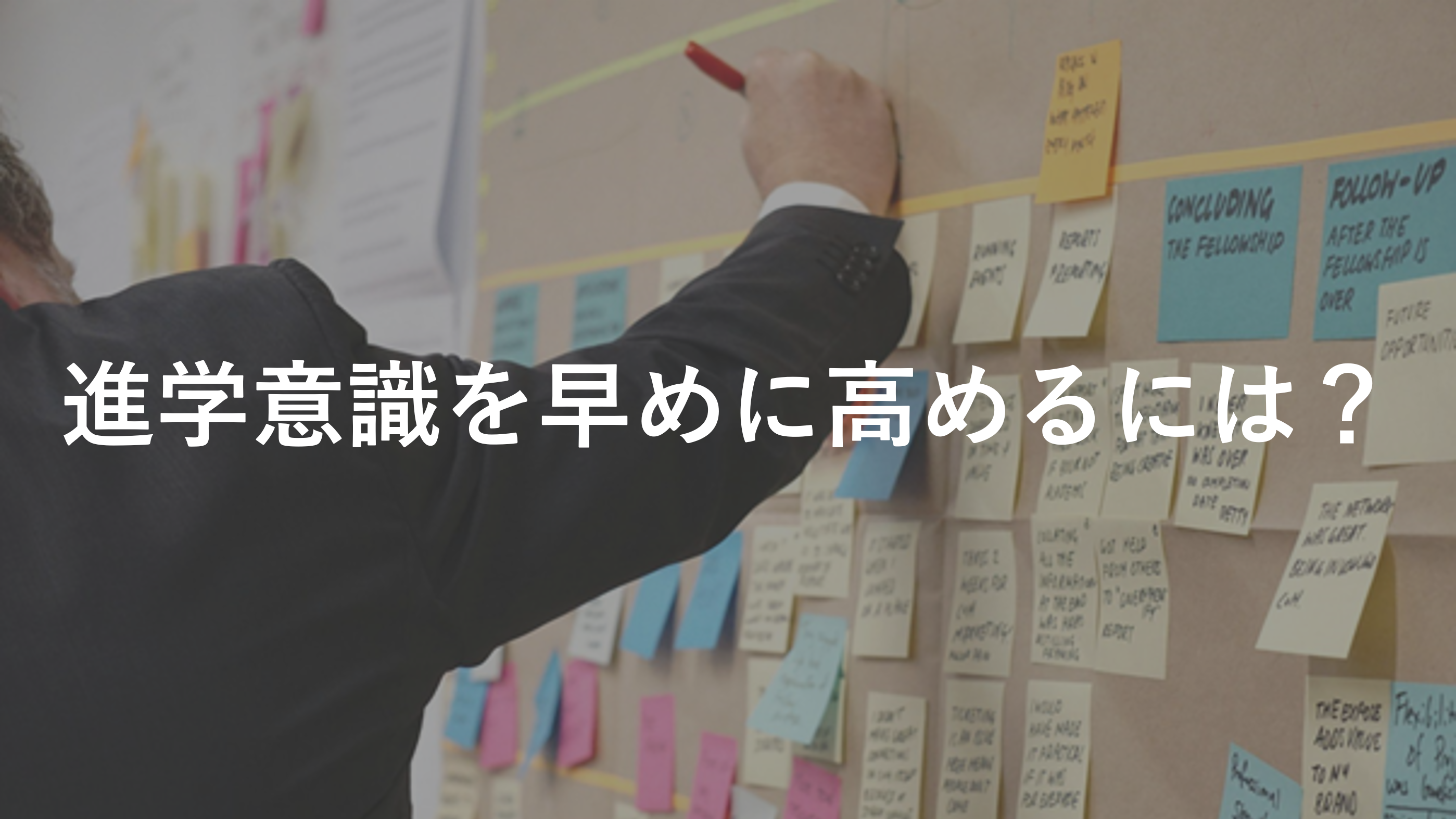
学生の進学意識を早めに高めるのは非常に重要です。職業や将来の方向性を考える決ことで、目的意志を持ちやすくなり、進学やその後の選択に影響を与えます。
そこで、この記事では大学生へのアンケート結果をもとに、学生の本音や進学で直面しやすい課題や不安について詳しく解説します。また、進学意識を高めて得られるメリットや重要なポイントについても説明しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
「やりたいことをやりなさい」といわれた高校生の本音
リクルートが発表した「第11回 高校生と保護者の進路に関する意識調査」の報告書によると高校生の83%、保護者の89%が進路に関する会話をしているというデータが示されています。
保護者から高校生に掛ける言葉として最も多いのは「⾃分の好きなことをしなさい」「やりたいことをやりなさい」という内容です。
「やりたいことをやりなさい」という言葉を使う割合は、年々上昇している傾向にあります。言葉自体は、多くの高校生が受け入れていますが、本音としては「不安」と感じるケースが多いようです。
これはデータ上でも明らかで、進路を考える際の気持ちとして「不安」と回答した学生が67%、一方の「楽しい」と回答した学生は28%に留まっています。
進路選択で多くの学生が感じる3つの悩み
文部科学省が2010年に公表した「進路を考える時の高校生の気持ち」のデータを読み解くと、多くの学生が感じる進路選択に関する悩みが見えてきました。
「進路を選択するときの悩み(職業を意識した時期別)」という調査では、大学生を対象に、「小学・中学」「高校」「大学入学後」「現在」といった時期ごとに、進路に対する意識がどのように変わったのかを分析しています。
大学に入るまでは「志望する大学・学部に入るのに学力レベルが十分ではない」という悩みが多くの割合を占めています。しかし、それ以降は具体的な進路選択についての悩みが増える傾向にあるようです。
さまざまな悩みのなかで多いのが、以下の3つです。
●自分の適性(向き不向き)がわからない
●自分の就きたい職業がわからない
●自分の進みたい専門分野がわからない
それぞれの項目について、紹介します。
●自分の適性(向き不向き)がわからない
職業選択において「自分が何に向いているのかわからない」「何が得意・苦手なのかわからない」といった悩みが多く挙げられています。
働いていない年齢の小学・中学時代でも43.8%が「向き不向きがわからない」と回答しており、年齢を重ねるごとにこの不安は増加していきます。
アルバイトを経験するような年齢になっても不安を払しょくできない方が多いのが現状です。そのため「実際に働いてみないと適正かはどうかわからない」と考えている大学生も多いのではないかと推測されます。
●自分の就きたい職業がわからない
「自分の就きたい職業がわからない」という回答も多くありました。大学入学後の段階でも、65%以上が「将来どのような職業につきたいか明確にはない」と回答しています。
こちらのデータも「小学・中学」「高校」「大学入学後」「現在」と、進むにつれ、職業に関しての迷いや不安が増加しているのがわかります。
小学・中学時代のほうが、就きたい職業を明確にイメージしている方が多く、大学に入って、現実的な選択肢が見えてくると、小学校の頃に憧れていた職業が難しいと感じるケースも少なくありません。
その結果、気持ちに折り合いをつけながら考え直しても、自分がどんな職業に就きたいかはっきりわからず、不安を抱えている学生が多いのが現状です。
●自分の進みたい専門分野がわからない
「自分の進みたい専門分野がわからない」と回答した学生は、大学入学後から回答時点までで、55%以上を占めているというデータがあります。
大学受験の際には学部を選んで入学するものの、具体的な専門分野までは決めきれていない方が大半でした。
学部までは選べても、専攻については深く考える時間がなかった可能性があります。大学の種類や学部など選択肢が多く、進路選択がかなり複雑になっているため、仕方ない現状もあるのかもしれません。
将来を意識した高校生活が進路選択のカギになる
大学生になっても、進路選択で不安を感じている方は多いです。不安を減らすには、高校生のうちから将来を意識した学校生活を送るのが重要です。
将来就きたい職業が明確であれば、大学やその先の進路を意識して学校生活を計画的に過ごせます。
例えば、自分が興味を持ったことを体験したり、その体験を書き記したりして、得意・不得意や好き・嫌いを自覚して、高校生のうちに自分自身について知ることが大切です。自己分析ができていれば、職業を選択しやすく、進学先を選びやすくなるでしょう。
さらに、総合型選抜や学校型推薦など入試形態の多様化で、逆算して学校生活を送ると希望する進学先に通りやすくなります。推薦入試での小論文に活用できる経験や、面接での志望理由が明確になるメリットも得られます。
大学生の職業に関する調査から読み解く進学意識のポイント
改めて、文部科学省が2010年に公表している「進路を考える時の高校生の気持ち」をもとに、進学意識について読み解くと、以下2つのポイントが見えてきました。
●将来を見据えて大学へ進学した学生が多い
●将来についてはっきりとした目標を持っている学生が多い
進学先をどのように決めたのか、また進路選択時にどんな気持ちを持っていたのか、について詳しく解説します。
●将来を見据えて大学へ進学した学生が多い
大学への進学理由 (職業を意識した時期別)の調査結果を見ると、「将来の仕事の役に立つ勉強がしたい」という回答が「小学・中学」「高校」「大学入学後」「現在」どの時期でも最も多い結果となっています。
将来を見据えて大学へ進学する学生が、どの時期でも75%以上を占めているというデータがありました。このことから、早い段階でどのような職業につきたいか、どんな働き方をしたいかなどのプランを立てておくのが重要だとわかります。
一方で、少数派ではありますが「すぐに社会に出るのが不安」「自由な時間を得たい」「周囲の人が進学する」といった消極的な理由で、大学への進学を希望した方もいるようです。
いずれの場合でも、社会に出て働くタイミングは多くの方に訪れるため、将来について早めに考えるのが大切である、といえるでしょう。
●将来についてはっきりとした目標を持っている学生が多い
「大学生の職業に関する意識 (職業を意識した時期別)」では、TOP2の回答が「希望する職種がある」と「将来についてはっきりとした目標を持っている」という結果でした。
このデータから、大学に進学している方の多くは具体的な目標を持って入学しているのがわかります。また、職業選択だけでなく、将来にどう活かすかまで考えて、日々学びを得ている学生が多いことも示されています。
高卒で離職した7割が「仕事が向いていない」という理由
文部科学省の同調査では、高校卒業後に進学せず就職した方のうち、71.4%が「仕事が向いていない」という理由で離職しているというデータが出ています。
71.4%の内訳で最多の回答は「仕事があわない、またはつまらない」で、26%を占めていました。高校生の時期、あるいはもっと早い段階から、職業選択や進学について考えるのが重要だとわかります。
進学意識を早めに高めるのが重要
大学生・高校生・保護者のアンケート結果から、将来の職業について早くから考える重要性がわかりました。また、現在ではさまざまな入試方式が取り入れられており、進学意識を早めに高めることで、優位に進められるでしょう。
NOLTYプランナーズでは、志望理由書作成をサポートする「NOLTYスコラ 副担任mirAI 」の提供を開始します。副担任mirAIは生成AIと対話を重ねることで、その生徒のキャリア観ややりたいことなどの思考を引き出し、言語化をサポートするツールです。実際に提出する志望理由書の作成だけではなく、学校生活で頑張ったことや興味のあることなどを深堀してくる生成AIとの対話によって、自分自身を見つめなおし、進路やキャリア選択の役に立つことも期待できます。
気になる方は、ぜひお問い合わせください。