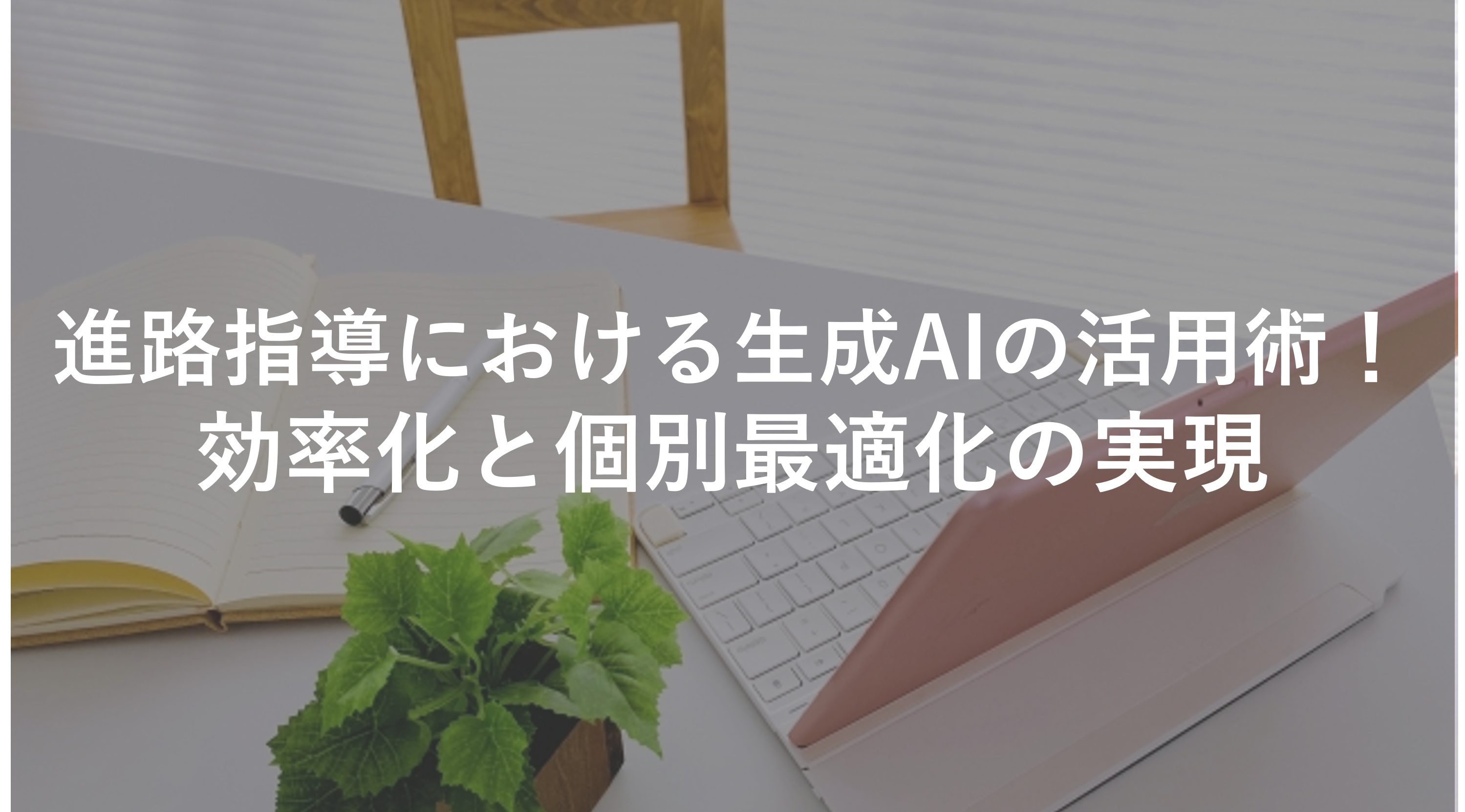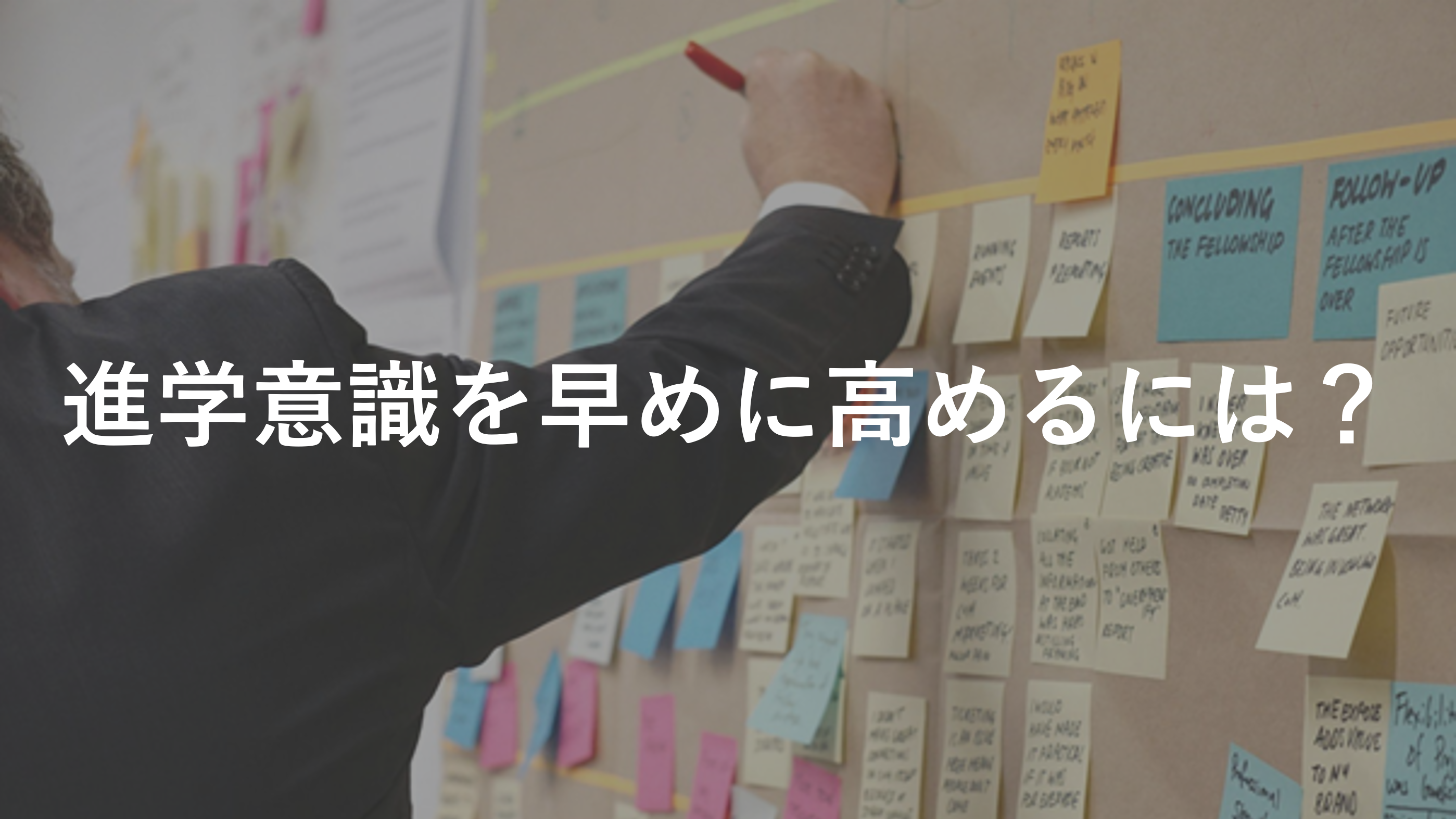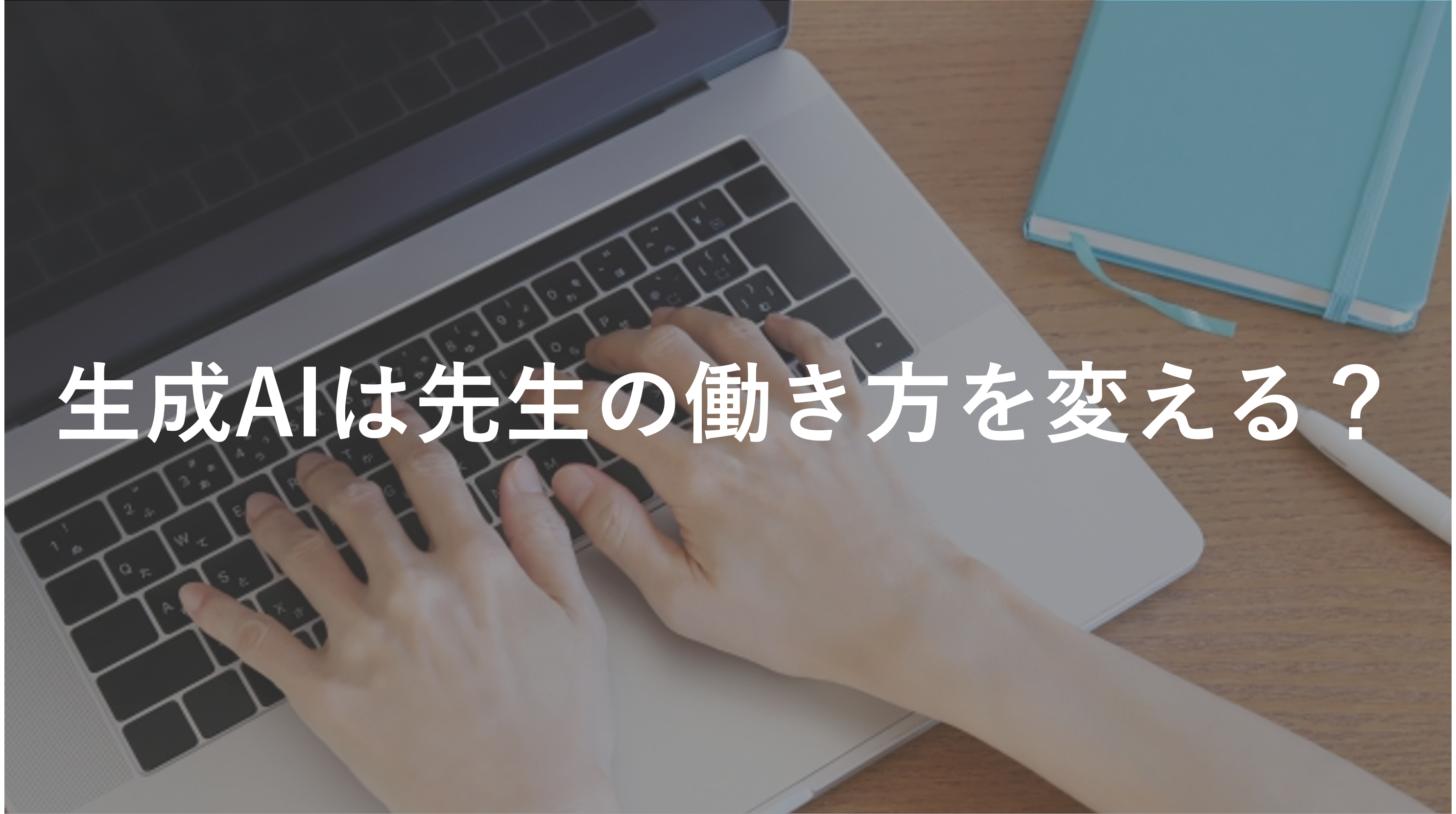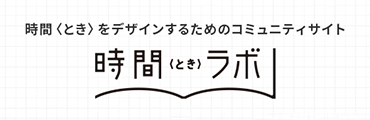生成AIは、文章や画像を簡単に生み出してくれるとても便利なツールです。そのため、学校のような教育現場で生徒の能力を引き出せるのではないかと期待する声もあります。
一方で、生成AIを使うと考える力や学習する機会が損なわれるという意見もあります。ルールを決めずに推進して、生徒の学習能力が伸びないと本末転倒でしょう。
この記事では、生成AIを活用して生徒の能力を伸ばすコツについて紹介しています。また、活用事例や注意点も解説します。これから学校で生成AIの活用を検討している方に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてください。
目次
生成AIを教育で活用する際に期待できること
OpenAIのchatGPTやMicrosoft Copilotなどに代表される生成AIは、使い方次第でさまざまな領域で活用できます。
日本語で命令文(プロンプト)を書くだけで、文章や画像など、多種多様なものを作成できると有名になりました。
教育の分野では、質問力・言語化力・問題解決力などを効率良く鍛えられると注目を集めています。
生徒は先生と会話するより、生成AIを利用したほうが、偏見や先入観なく思考を広げられるかもしれません。先生の思考バイアスがかからないため、自由な発想ができると期待されています。
生徒が生成AIを活用するメリット
生徒が生成AIを活用するメリットはさまざまですが、以下では3つ紹介します。
●生徒のレベルに合わせた指導ができる
●時間を問わずいつでも学習をサポートできる
●テスト問題や添削を効率化できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
●生徒のレベルに合わせた指導ができる
生成AIを活用すると、生徒一人ひとりの学力に合わせて指導しやすくなります。授業の場合は、レベルをどこかに合わせる必要があるため、一定数の生徒は自分のレベルに合っていません。
生成AIを活用すると、授業のペースと学力のレベルがあっていない生徒の学習をフォローできます。授業よりレベルが上でも下でも問題ありません。
本人の生まれ持った資質・能力によって問題を理解するスピードが異なるので、個別教育で生成AIが活用できるシーンは多くあります。
●時間を問わずいつでも学習をサポートできる
24時間好きなときに学習のサポートを受けられるのもメリットです。生成AIは、人間ではないので、朝から夜までいつでも質問できます。
例えば、部活動や習い事などで忙しい生徒でも、各々の生活リズムに合わせて活用できます。
また、問題を解いて、すぐに答え合わせができるのも優れている点です。今までは、先生に添削してもらうまで時間を要する機会は多かったですが、生成AIを活用するとすぐにフィードバックを得られます。アウトプットとインプットを短い時間で繰り返し実施できるので、記憶に定着しやすく、学習効率も上がるでしょう。
●テスト問題や添削を効率化できる
生成AIは、データからパターンを学習するため、生徒が間違えやすい問題をまとめて生成して「苦手分野の問題集」を自作できます。
また、先生もこれまでの経験からつまづきやすい問題を自作していましたが、さまざまなデータを用いて効率良くテストを作れるようになりました。
テストの添削についても生成AIが活躍します。先生が自分の手で添削を行うと時間がかかりますが、生成AIなら短時間で対応可能です。
日本語の不自然な表現や誤字脱字を機械で見つけられるため、作文の校正や記述問題でも力を発揮します。
生成AIを活用する際の注意点
生徒が生成AIを活用するメリットの反対で、注意点についても紹介します。
●使い方を工夫しないと考える力を伸ばしにくくなる
●生成AIの回答が誤っている可能性がある
●個人情報や著作権を侵害するリスクがある
生成AIで学習する際につまづきやすいポイントであるため、それぞれの内容を確認しましょう。
●使い方を工夫しないと考える力を伸ばしにくくなる
生成AIを活用する際は、ルールを明確にしましょう。生徒が問題を解く前に生成AIで回答を求めるようになってしまうと、考える力が育ちません。まずは、回答の確認や添削で生成AIを利用して、少しずつ活用範囲を広げましょう。
一方、答え合わせで生成AIの回答が複数ある場合は、生徒の思考力を引き上げるチャンスです。AIが見つけた回答以外の視点がないか考える機会が与えられます。さらに、考えさせることによって、生徒はより理解を深めたり思考力を引き上げたりするでしょう。
●生成AIの回答が誤っている可能性がある
生成AIの回答は誤っている可能性があるため、すべて正しいと思わずに参考程度にとどめましょう。回答や添削結果が正しいか怪しいときは、自分でも生成AIの情報が正確か考えたり調べたりすると、より理解が深まります。思考過程についても、チャットで確認して問題ないかチェックするのがおすすめです。
また、生成AIの回答が間違っていた場合は、正しい答えを出すためにどのような指示を出したらよかったのか、プロンプトを学ぶきっかけにもなるでしょう。
●個人情報や著作権を侵害するリスクがある
生成AIを利用する際、個人情報を入力すると情報漏えいにつながる可能性があります。生成AIのサービスや機能である程度は保護されますが、完璧ではありません。
また、著作権に関わる文章や画像を読み込ませた場合、AIに学習される可能性があります。一般的なアイディア出しや、ラフ案の作成には向いていますが、著作権が絡む問題に発展する可能性があるため、すべてを生成AIに頼らないようにしましょう。
生成AIパイロット校での活用事例
生成AIパイロット校として、令和5年度にAIを活用した学校の事例を以下で紹介します。
|
活用項目 |
内容 |
| デスクトップアプリ作成 | プログラミング教育で生成AIを活用した学習支援。 |
| 美術教育での画像生成 | AIを使い、苦手意識を克服し創造性を伸ばす支援を実施。 |
| 校務効率化 | 学校行事、テスト問題、配布文書作成へのAI活用を推進。 |
プログラムに詳しくなくても、デスクトップアプリを作成できたり、美術で生成AIが作った画像を参考に発想を広げて自分の構図にアレンジしたりするなどの取り組みが見られました。
また、小学校では活用以前に、情報モラルの教育として、AIの誤りを教材として活用し、正しい知識を身に付ける試みもあります。
さらには、校務の効率化で、学校行事・テスト問題・配布文章の作成でAIの活用を推進する例もありました。
生成AIで生徒の学力は伸ばせる
生成AIを活用するメリットはとても大きいです。時間や学力を問わず、生徒の能力を引き出せると期待されています。人間ではないので、理解できるまで質問できたり、作文や志望動機などのアイディア出しにも使えたりします。一方、考える力を伸ばしにくくなったり、回答が間違っている可能性があったりと注意点もあるため、適切な指導が必要です。
NOLTYプランナーズでは、志望理由書作成をサポートするNOLTYスコラ 副担任mirAIをリリースしました。副担任mirAIは生成AIと対話を重ねることで、その生徒のキャリア観ややりたいことなどの思考を引き出します。生成AIが志望理由書を代わりに作成するのではなく、対話を通して言語化をサポートするツールです。
これまで先生が行っていた志望理由書作成の指導をmirAI先生が部分的に代行することで業務負担を軽減します。
気になる方は、ぜひお問い合わせください。