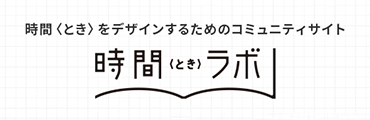貴校の教育理念・教育方針について教えてください
(伊藤校長) 本校の教育における究極の目的は、「大人になること」です。単に年齢を重ねるだけでなく、“ちゃんとした大人”――私たちはこれを「聖人」と呼んでいます――になってほしいと考えています。
初代校長が示した「聖人」という言葉には、「人や環境に支配されず、自分自身と自分以外のものをきちんと区別できる人」という意味が込められています。自分以外のものに心を奪われず、自分のできること、できないことを正しく理解し、主体的に行動できるようになる。それが「聖人」の姿です。
例えばテストの点数や大人たちが追い求める経済的成功など、これらはいずれも自分以外のものであり、自分の外側から貼り付く評価にすぎません。もしそれらを自分の価値そのものだと思い込んでしまうと、常に結果に左右され、真の自由から遠ざかってしまいます。
そこで本校では、自分の心から他者の言葉や価値観を削り落とすトレーニングを重ねます。テストの点数が上がれば喜び、下がれば悔しくなる。けれども、それだけで自分の価値が変わるわけではないと理解し、自信をもって成果と向き合う、この繰り返しによって、自分だけの強み=Only Oneを見つけ、社会の中で唯一無二の存在として成長できるのです。
このように、自分と自分以外のものを区別し、自分だけのOnly One を見つけて磨くこと、それが本校の教育理念です。
中高時代は特に多感な時期であり、周りの影響を大きく受けます。そのような中で自分に貼り付いた自分以外のものを削り落とすためには、どんな姿勢が必要だとお考えですか?
(伊藤校長) まず大切なのは、「これは本当の自分だ」と思い込む前に立ち止まり、自分自身を振り返る姿勢です。たとえば怒りを感じた瞬間、それは自分の本質からではなく、“外部の声”や“貼り付いた価値観”から来るものかもしれません。「なぜ私は今、こんな気持ちになっているのか」「この感情はどこから来たのか」と自問し、何度も振り返る姿勢が大切です。
こうした自己に問いかける姿勢は、一朝一夕には身につきません。本校では入学から卒業までの6年間をかけて、生徒一人ひとりが自分の内面を深く見つめる機会を設けています。
教職員にも、チャットツールや朝礼を通じて日々の気づきを共有し、学校の目指す姿を常に確認し合う体制を整えています。具体的な生徒指導は各担任に託すことで、組織全体で理念の浸透に努めています。
理念浸透のための仕組みづくりについて具体的に教えてください。
(伊藤校長) まず、教職員一人ひとりが自分自身の行動指針として「クレド(※)」を設定することから始めたいと考えています。これに加えて、管理職が担う各部署にもそれぞれのクレドを定め、さらに学校全体のクレドとつなげます。建学の精神を核として個人・部署・学校のクレドを明文化し、さらに「本当にクレドが守れているか」をチェックできる仕組みを整えようとしています。
ただし、クレドを言語化するのは簡単なことではありません。クレドは上から押し付けられるものではなく、自分自身と向き合い、自分の信念から出発するものであるべきです。ここでも先ほどの自分以外に貼り付いたものを剥がすという話と共通しますが、私たち大人も、本当の自分と向き合いながら言語化をしていくということを常に続けていかなければならないと思います。
(※)クレド…「信条」「志」「約束」を意味するラテン語。組織において、構成員が共有し行動すべき価値観や具体的な行動指針を明確に示したもの
ありがとうございます。それでは玉木教頭にお聞きします。自分とは何かを考えるための問いを見つけるために、具体的に授業やカリキュラムの中でどのようなことを行っていますか?
(玉木教頭) 学校の授業において、一方的な講義だけでは生徒自身の問いにはつながりません。そこで本校では、授業の中に「自分と出会うヒント」を意図的に組み込み、リアルな現実と結びつけながら学べるよう、「ICE (アイス)モデル」を導入しています。
ICEモデル
・I(Idea:基礎的な知識の定着)
・C(Connection:知識と知識をつないで活用)
・E(Extension:価値づくり・課題の解決)
この3つを授業内で行き来させることで、「知る」「結びつける」「活用する」のサイクルが回り、生徒が自らの手と頭を動かして学びを深められる設計になっています。どれか一つが抜けると学びが浅くなるため、意図的に行き来しながら進めます。導入前と比べ、学問を現実世界のものとして捉え、自分の頭で確認する授業を展開することによって、生徒の考える幅が一気に広がったと思います。ICEモデルを柔軟な枠組みとして活用することで、自分で問いを見つけ、その問いに向き合う力を養っています。
ありがとうございます。山本先生にお聞きします。探究学習における取り組みはいかがでしょうか?
高校GIC(Global Innovation Class)統括長
情報・STEAM・Project担当
(山本先生) 総合探究の取り組みは、教科教育での「ICEモデル」による探究型学習と一体化しつつ、宿泊行事を中心に据えるかたちで、3~4年前から本格的に整備してきました。具体的には、中学2年では夏期学校での山登り体験、中学3年では農村での生活体験学習、高校1年で熱海や真鶴地域を舞台に地域創生をテーマとするソーシャルデザインキャンプ(以下、SDCとする)を実施した上で、高校2年で沖縄へ赴いて戦争と平和を学ぶという段階的なプログラムを構築しています。
例えば高校1年のSDCでは、バブル期に地域振興の一環として立ち上げられ、一度は衰退したものの、また盛り上げようとしているリゾート地を中心にフィールドワークを行います。地方再生は日本各地における課題であり、その課題解決に対して、リアルな現場で学ぶ機会としています。また、街づくりを例に、デザイン的な視点から空間を構想したり、観光客の増加が地域にもたらす経済効果をデータで試算したりといった、社会科や情報科などの授業と密接に結びつけた学びの展開を行っています。宿泊行事が単発のイベントではなく、日常の学びの一部として自然に位置づけられるようにしています。
生徒たちが部活動や放課後の課外プログラムで手いっぱいになるなか、授業と外部活動を有機的に連携させることで、学習の「余白」を生み出し、授業内外を往復しながら深い探究が進むように工夫しています。これらの取り組みによって、生徒自身が自ら問いを立て、実体験を通じて学びを拡張し、総合的に思考を深める環境が整いつつあります。
(伊藤校長) 本校にとって探究とは、単なるひとつの学習コンテンツではなく、すべての学びを貫く「根本のコンセプト=学問のエンジン」です。何を学び、何を問い、そこからどんな答えや行動が生まれるのか──まずは「探究の意図」を明確にしたうえで、各教科の知識や体験的プログラムを結びつけます。
具体的には、ICEモデルというサイクルを回すことで、学びを固定化せず「動き続ける思考」にします。答えはその場限りの到達点でしかなく、大切なのは問いを立て続けるプロセスです。この姿勢こそが、生徒一人ひとりの主体性を育み、変化の激しい社会の中でも自ら考え抜く力、ひいては「幸せな人生をつくる力」につながると考えています。
貴校で6年間過ごした生徒の様子は、先生方の目から見てどのように見えますか?
(山本先生) 私は本校の卒業生ではないため、自分の母校と比べると、教育に対するスタンスも取り組みもまったく異なると感じます。特に印象的なのは、生徒一人ひとりが自分の軸や「やりたいこと」を非常に明確に持っている点です。もちろん、全員が最初から固まった目標があるわけではありませんが、「まずはこれをやりたい」という関心を掲げ、その中から自分にとって居心地が良く、成長できそうだと思えるものを模索しているように見えます。加えて、一つの主軸をもとに、それを支える二つ三つのテーマを同時に抱えています。高校生の段階でこれほど主体的に選び、行動する姿勢は非常に頼もしいと感じています。
(玉木教頭) 本校の進路指導では「どの大学に行くか」「偏差値で選ぶ」ではなく、まず「なぜそうしたいのか」という本人の動機を深掘りするところから始めます。一人ひとりが本当にやりたいことを考え抜いた結果、自然に最適な進路を選択できているように思います。在学中から人とのつながりや自分自身の問いを大切にしてきた伝統が、進路選択でも表れています。
(伊藤校長) 高校3年生に「聖人、見つかった?」と聞いてみます。すると「分からない」と答える生徒も多いです。でも私はそれで良いと思っています。まだ18歳ですから、人間が完成するわけではありません。彼らは自分なりに問いを立て、模索を続ける姿を見せてくれており、そのプロセスこそが私たちの仕事の成果だと感じています。たとえ卒業時点で進路を明確に定められなくても、その後も問い続ける力が身についているからこそ、30代・40代になったときに自らの道を切り拓くことができると私たちは信じています。
これまでのお話の中で、「振り返る」「自分自身を見つめ、問う」ということをとても大切にされていると感じました。そういった姿勢を身につける一環として、貴校では「できたこと手帳」というオリジナルの手帳を使っているようですが、こちらの取組みについても教えてください。
(玉木先生) 本校が「できたこと手帳」を導入した背景には、生徒の自己肯定感が低いという課題意識がありました。「できない自分」に囚われるのではなく「今日自分は何を成し遂げたか」を内省する機会をつくるため、手帳の右ページに小さな成功を書き留める欄を設けています。普段見逃しがちな達成感や内発的なエネルギーに気づくことで、自己肯定感が自然に高まります。左ページには授業やテスト、行事などのスケジュールを記録できる欄を配置し、自ら計画を立てて実行し、振り返る習慣を育んでいます。
手書きの記録は生徒の筆跡から意欲や感情の温度を感じ取れるため、担任が一人ひとりに寄り添ったフィードバックを行いやすいという利点があります。確かに時間と手間はかかりますが、この人間的な温もりという部分でも大切にしています。
それでは最後に、学校の学びとして大切にしたいことや、貴校での学びを通して生徒にどのような力を身につけてほしいか先生方のお考えをお聞かせください
(山本先生) 私が最も大切にしたいのは、生徒の感情や感覚を揺さぶることです。ただ知識をインプットさせるのではなく、新しい世界を見せて、「次は自分でやってみよう」と実感できる機会をつくりたいと考えています。たとえばデジタル教材や動画は概要をつかむのは確かに効率的ですが、それだけでは「わかった気になる」だけで終わってしまいがちです。まずはアナログにこだわって手を動かし、実際に失敗しながら学ぶことで得られる“生きた感覚”を重視したいです。そうした生の経験を生徒には中高時代にたくさんしてほしいと思っています。
(玉木先生) 私にとって「Only One」とは、自分の活動を支えるエネルギー源そのものです。社会に出る前に、自らの原動力が何かを見つけてほしいと思っています。もちろん、いろいろなことを経験するうちに揺らいだり、別のものに気持ちが移ったりすることもあるでしょう。しかし中高時代の体験は人生における原体験であり、この時期だからこそ「エネルギーの源泉」を最もリアルに感じられるはずです。一度でもその核に触れられれば、社会に出てからも大切に育み続けることができると信じています。
(伊藤校長) 管理職として取り組むべきことは、教員一人ひとりに「余白」を与えることです。ここでいう余白とは、探究のための問いを立て、新しい視点や疑問を生み出すための物理的な時間と心理的なゆとりのことです。トップダウンで業務を押しつけるだけでは、教員が自ら試行錯誤し、学びをデザインする余地は生まれません。安心して挑戦できる環境を整え、自律的に授業を設計・実践し、振り返りまで行える仕組みをつくることこそが、私たちの重要な使命です。
そして生徒には、「疑うこと」と「信じること」の両方を身につけてほしいです。疑いだけでは否定的に偏ってしまい、信じるだけでは盲目的になりかねません。だからこそ、常に「何を疑い」「何を信じるのか」を自問し続ける姿勢が求められるのです。そして、疑う行為そのものも、次の一歩を踏み出すための信じる力あってこそ意味を持ちます。両者のバランスを保ちながら学びを深めてほしいです。