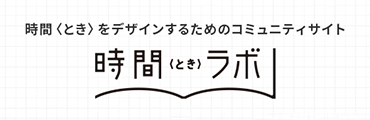貴校の教育理念・教育方針について教えてください
(青木校長) 本校は校訓として「行学二道」を掲げています。「行」は体験、「学」は学問を指します。これからの時代、知識の習得だけでなく、その知識を実社会のさまざまな場面で活かす体験も同じく重要です。仲間と何かに一生懸命取り組んだ経験や、友人と過ごした時間といった、目に見えない「知」として蓄積されるものが、社会に出たときに必ず役立ちます。こうした「行」と「学」の両面を、在学中の6年間(または3年間)を通じてしっかりと身につけてほしいと願っています。
貴校は探究プログラムやグローバル教育に力を入れているとお聞きしました。具体的にどのような理念のもとそれらの教育を展開していますか。
(青木校長) 探究については、ゼロから立ち上げ推進してきました。まず、教員一同が「探究」の本質や教員としての役割を深く理解し、共有しつつ歩みを重ねてきたことが、今日の成果につながっていると感じます。探究は学問というよりも、学問を深めていくための考え方そのものです。それ自体が一種の「体験」でもあると思いますし、先ほど述べた「行(体験)」の要素ともリンクしていると考えています。
また、グローバル教育について、本校は建学の精神として「平和な社会の繁栄に役立つ若者の育成」を掲げています。これは、創立当初から大切にしてきた教育理念であり、現在もそれを体現できる学びの場をつくることに力を注いでいます。本校の教育プログラムを通して、仲間と協働しながら問題を解決し、新たな価値を生み出す経験をしてもらいます。こうして平和社会に貢献できる若者に育ってほしいのです。
探究学習推進部長の上野先生にお聞きします。実際にどのようなカリキュラムで探究学習を行っていますか。
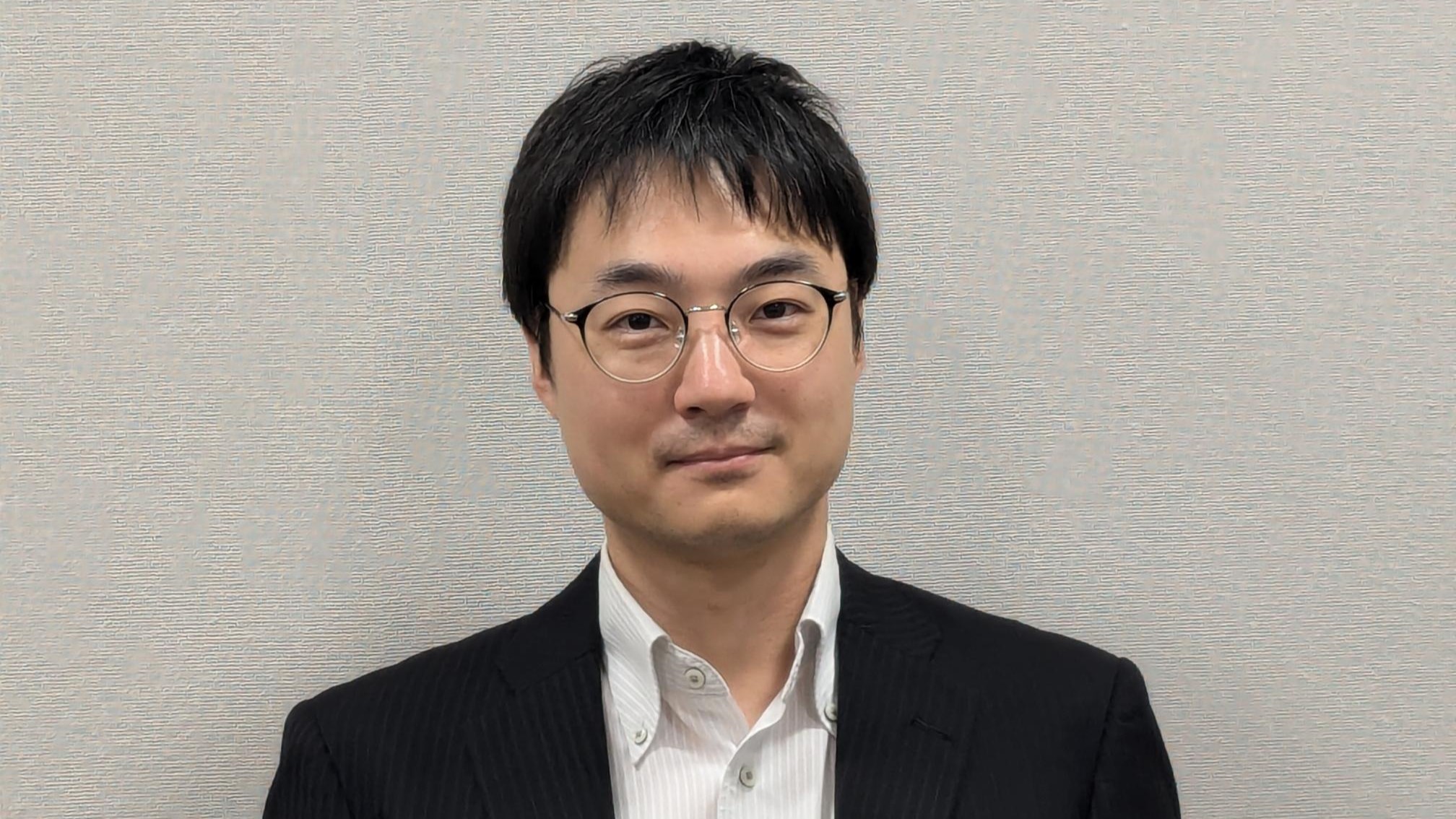
探究学習推進部長
理科(生物)教諭 サイエンス部顧問
(上野先生) 2018年度に探究学習推進委員会(現 探究学習推進部)を立ち上げ、委員の教員と協力して探究学習のカリキュラムデザインを行いました。初年度は中学1年生を対象にスタートし、翌2019年度からは(高校3年生を除く)高校2年生までの全学年に拡大し、全校的に「総合的な学習の時間」(当時)に探究活動を取り入れるようになりました。
科学的な現象に興味を持つ小学生は多く、「問い」も生み出しやすいため、中学1年生では、夏の自由研究や自然教室などと連動した自然科学系の探究活動を実施しています。中学2年生では社会課題解決や、文化・歴史など人文社会学系の探究に取り組み、理系・文系を段階的に経験できるよう工夫しています。中学3年生では自分の興味ある分野で自由にテーマを設定し、探究しています。成果発表も自由度を重視し、A4一枚で形式にとらわれず、自分らしい表現でまとめています。
中学生段階では、様々なことに楽しみながら取り組む中で、自然に探究的な態度を身につけることを目標としています。
高校では、内部進学者と高校からの入学生が一緒になるため、グループで協働的に進めながら、改めて探究のメソッドや実践的なスキルの習得を目指していきます。高校1年生の前半では実際にメディア業界で活躍するプロの方々を講師として招き、ドキュメンタリー制作に取り組みます。社会課題をリサーチし、インタビューや調査を重ね、その内容をグループでビデオ作品にまとめるプログラムです。制作の過程で、著作権や情報リテラシー、インタビューの仕方、文献調査の方法なども学びながら、動画表現のスキルも磨いていきます。
高校1年生の後半からは個人課題研究に取り組み、テーマやリサーチクエスチョン、仮説の設定と、その検証方法の考案などを半年かけてじっくり練ります。探究ではテーマの設定が最も苦労する部分でもあるため、AIとの対話なども取り入れながら、時間をかけて「問い」の焦点化を行います。高校1年でやるべきことを定め、高校2年生の1年間をかけてしっかりと研究を進め、最終的に修了論文としてまとめます。
こうした5年間にわたる段階的なカリキュラムを2018年度の導入以来、試行錯誤しながら形にしてきました。現在は本校独自の探究活動として、一定の成果が表れていると感じています。
探究学習に対する生徒の反応はいかがでしょうか?
(上野先生) 探究活動を立ち上げた当初は、「なぜ探究をしなければいけないのか」といった疑問や、「やらされている」と感じる生徒も少なくありませんでした。しかし、現在では中学1年生からカリキュラムに沿って段階的に取り組むことで、探究活動や探究的思考が生徒の中に自然と根付いてきていると感じます。今では「探究はなぜ必要か」といった抵抗感もほとんど見られなくなりました。
本校の探究学習の特徴は、各自の「好きなこと」をテーマにできる点です。中学3年生以降は、たとえばSDGsや自然科学といった特定の分野を設けず、自由なテーマで探究を進められるようにしています。そのため、生徒たちは自分の興味・関心に従って主体的に取り組むことができ、「楽しい」「前向きに挑戦できる」と感じています。教員も生徒の意欲を尊重し、徹底的に寄り添い、サポートしていく姿勢を大切にしています。
先生方にとっても新しいチャレンジが多かったと思います。探究学習への理解促進やレベルアップのためにされていることはありますか?
(上野先生) 始めの頃は、探究活動をどう進めればいいのか手探りの状態でした。教員が集まってレクチャー形式の研修なども行いましたが、なかなか浸透しませんでした。やはり時間をかけて、教員一人ひとりが生徒と向き合い、指導者というよりは伴走者として寄り添いながら見守ることで、徐々に経験を積んでいきました。
そうした中で、探究活動で秀でた生徒がコンテストで入賞したり、総合型選抜入試につなげたり、進学後も自分のプロジェクトを継続したりするような事例も少しずつ増えてきました。そのような実際のモデルケースが出てきたことで、「この生徒はこんなふうに進めてきた」という具体的な進め方や手本が共有されるようになり、教員同士も進め方を工夫できるようになっています。生徒とともに、教員も一緒に探究活動を作り上げているという実感があります。
その他には、有志による「探究的な学び」をテーマにした勉強会を開催しています。既に探究型の学びを経験した教員も増えてきたため、ノウハウの共有の場として活用しています。おおよそ1ヶ月半に一度のペースで開催しており、今年度から本格的にスタートし、今年は計5回を予定しています。
例えば、4月にはレゴブロックを使ったリフレクション、5月には「具体と抽象トレーニング」、6月は「エッセンシャルクエスチョン(本質的な問い)の作り方」といったテーマで行いました。授業をより探究的にするために必要なスキルや実践例を共有するだけでなく、お菓子やコーヒーを飲みながら、自由な雰囲気の中で意見交換を行っています。まさにカフェのようなリラックスした雰囲気です。毎回10~15名ほどが参加しており、特に若手教員が多く集まりますが、ベテランの教員も関心を持ち参加してくれています。世代を超えて、さまざまな立場の教員が互いに学び合える場になっています。こうした勉強会に参加する教員が、今後は授業自体をより探究的なものへと変えていってくれることを期待しています。
校長先生からは探究学習における取り組み全体を見てどう思いますか?
(青木校長) 時代の変化に伴い、教員もまた変化を求められます。そして、生徒たちが学びに向かう姿から、教員も多くの刺激と良き影響を受けております。校内には、「私たち自身も成長し、変わり続けよう」という気運が醸成されていると感じております。
また、生徒が「楽しそうだからやってみよう」と、自分の興味や関心に夢中になって取り組めることは、本校の大きな魅力だと感じます。クラスには実に多様な生徒がいて、魚や虫の研究でコンテストに入賞する生徒、アメフトで日本一になったスター選手、研究成果を世界に発表しに行く生徒など、さまざまな個性や才能が集まっています。それぞれが自分のために研究や部活に熱中できる環境が整っており、個性が埋もれず、のびのびと活動できます。「好きだから」「やりたいから」という純粋な思いが原動力となり、本人の意志で取り組める雰囲気が感じられます。
さらに発展的な探究学習にしていくために、今後取り組みたいことはありますか?
(上野先生) やはり授業が大切だと感じます。探究活動というと「総合的な探究の時間」だけの特別なプロジェクトのように思われがちですが、それだけではなかなか生徒は育ちません。探究活動は実践の場ですが、日常の教科授業こそが「問いの設定」や「仮説検証」、「教科を横断した考え方」など、探究的な思考を養うトレーニングの場となるべきです。各教科の授業そのものをさらに工夫・改善していくことが、次の重要なステップだと感じています。
それでは、グローバル教育推進部長の北野先生にお聞きします。グローバルコースでの具体的な取り組みについて教えてください。

グローバル教育推進部長
グローバルコースプログラムディレクター
英語科 教諭
(北野先生) 2021年から「グローバルコース」が立ち上がりました。実践的な英語力を育成するだけでなく、「世界平和実現のために貢献できる真のグローバルリーダーになること」を目的としたコースです。また本コースは、全校に先駆けて新たな取り組みを実践し、その成果や手法を他のコースへ展開していく、という意識で運営しています。
教科授業においても、高校生の場合、学期ごとに1~2回「パフォーマンス課題」に取り組んでいます。これは問いをベースにしたプロジェクト型課題で、例えば生物と国語を連動させた教科横断課題が出されます。国語で生命倫理に関する評論文を読み、生物ではDNAについて学び、「デザイナーベイビーは倫理的に許容される」といったテーマについて調査や議論、プレゼンテーション、レポート作成などを一定期間かけて行います。
本来はこういった課題は他のコースでも実施したいと考えていますが、課題設計は非常に大変であり、すべての教員が一斉に取り組むのは難しい現状です。まずグローバルコースで試行し、課題や方法を整理・ブラッシュアップして、他のコースに展開しています。
またグローバルコースのパフォーマンス課題については、週に一回担当教員が集まる検討会を設けて、知見を共有し、様々な教科の教員がアイデアを出し合い、議論して課題を作っています。検討会から始めて、徐々に学校全体でレベルアップしていくのが理想です。本校の教員は専門知識や教養が豊富で、スペシャリストも多く在籍しています。そうした先生方が議論に加わると、本当に面白く、クリエイティビティにあふれる企画が生まれます。知見を引き出し、みんなで楽しく創造的な取り組みができるような体制を、今後も広げていきたいと思っています。
グローバルコースにおける探究活動ではどのようなことに取り組んでいますか?
(北野先生) グローバルコースは探究的な学びに特化したコースであり、前述のパフォーマンス課題の実施や総合探究の時間のボリュームも増やしています。
高校では探究活動の一環として「起業家精神」を育むアントレプレナーシップ教育に取り組んでいます。教育業界でアントレプレナーシップ分野の先駆者であるTAKTOPIA株式会社にご協力いただきながら、授業を実施しています。異文化理解については、株式会社Culmonyとも連携し、多様な外国人講師による講演やワークショップの機会も設けています。
特に社会課題の解決と起業家教育を結びつけ、インタビューやリサーチを通して身近な社会問題における課題を定義し、最終的には1年次はアイデア、2年次には実際にプロダクトを作り、価値提供まで行うことを必須課題としています。アイデアのみで終わる探究学習が多い中、実際にプロダクトを形にし、価値提供まで進める点が大きな特徴です。 最終的には日本での発表を経て、英語に翻訳・ブラッシュアップし、ボストンで現地の起業家や投資家に英語でプレゼンテーションします。野心的な目標としては、現地で投資を獲得して帰国することも目指しています。
このように、グローバルコースはグローバルな連携や先進的な取り組みを意欲的に実践しており、実際に在学中や卒業後に起業を果たした生徒も出ています。
学校の強みとして、多様な探究プログラムを提供することで、保護者からの反応の変化はありましたか?
(青木校長) 学校選びにおいては偏差値が重視されがちですが、最近はそうした流れとは少し違う風潮が生まれてきていると感じています。学校の広報活動を通じて、本校が探究活動に力を入れていることや、グローバルコースでの多様な体験の魅力を伝えると、「子どもにぜひこうした経験をさせたい」という保護者の声を多くいただきます。探究的な学びや、協働して問題解決に取り組み、新たな価値を模索する―こうしたこれからの社会に必要な学びや考え方に共感してくださる保護者の方が増えていると実感しています。
特に、日々お仕事をされている保護者の皆様は、職場で「どのような人が生き生きと活躍しているか」を実感され、学力だけではなく、協調性や探究心、問題発見力や課題解決力などが大切だと気づかれているのではないでしょうか。保護者が自分の子どもに望むことは、やはり「幸せになってほしい」ということだと思います。これからの社会がいかなる変化を遂げようとも、子どもたちが活躍し、豊かで幸せに生きていける人間に育ってほしい。そのために、どのような環境にあっても力を発揮できる人間になれるよう、私たちも子どもたちの成長を支えていきたいと思います。
最後に皆さまにお聞きします。貴校での学びを通して、生徒にはどのような力を身につけて卒業して欲しいですか?
(上野先生) 自分で楽しいことを掴んで、幸せに生きてほしいです。人生を楽しむためには問う力が必要だと思います。何事も、「なんでだろう?」と考えていくと面白くなっていきます。そのように楽しく生きていくための手段として探究を学んでいってほしいと願います。
(北野先生) 自分を知って、社会を知って、社会との接点を知って、他者との協働の仕方を知って、卒業して欲しいと思います。
(青木校長) 仲間と協働して、新しい価値を創造して発信できる、変わる社会に対応する力を身につける一方で、変化しない自分の価値もしっかり磨いてほしいと思います。