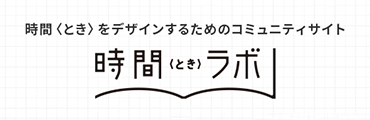貴校の教育理念・教育方針について教えてください
(中根校長)1980年に開校した本校は今年で45周年を迎えます。開校当初から「創造性の開発と個性の発揮」という理念を掲げています。
かつてこの地域は、管理教育で知られていました。そのような時代の中で、本校は他校とは異なる教育方針を打ち出しました。この新しい方針を推進した先生たちは、フロンティア精神に富み、当時の臨時教育審議会などが打ち出していた未来の教育のあり方を模索していました。
開校当時から現在の探究学習に通ずる総合学習を取り入れ、また2004年から文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(以下、SSH)にも指定され、途中、10年間のブランクがあったものの、2018年から第Ⅱ期、2024年度からは第Ⅲ期の指定を受けています。
こうした取り組みが、今日の本校の教育方針の土台となっています。生徒たちの能力を最大限に引き出す教育環境を提供するという目的において、今もさまざまなことにチャレンジしています。
理系進学者が多い学校かと思います。理数教育に関して何か特徴的な取り組みは行っていますか
(中根校長)例えば芝浦工業大学と連携して、生徒たちが実際の大学の研究環境で学ぶ機会を提供しています。高校3年生の段階で、芝浦工業大学への進学意志が強い生徒を大学の研究室に配属し、教授や大学院生から指導を受けるプログラムを行っています。これは、生徒にとって非常に価値のある経験であり、大学生に交じって受ける先取り講義は、大学入学後の単位として認定されます。
さらに他機関、学校間の連携も積極的に進めています。山階鳥類研究所や福井県立大学と連携し、鳥類や恐竜などに興味を持つ生徒が深く学べる機会を提供しています。
理数教育に力を入れた人材育成が大きな特色となる一方で、決して理数教育だけに偏っているわけではなく、文系の教育にも重きを置いています。現在、生徒の約4分の3は理系、約4分の1は文系です。理系の割合が他校に比べても多いですが、文系教育も高い水準で行われ、全国的な賞を受賞することも多々あります。他校のSSHの指導をしている先生や探究学習を担当する先生方からも、「これほどまでに文系教育も充実させている学校は珍しい」という評価をいただいています。
文理融合の教育を実践されているということですね。具体的な事例を教えてください
(中根校長)昨年ドイツの大学に進学した生徒がいました。彼は数学が得意だったのですが、中学時代から小説が好きで、文学にも興味を持っていました。特に太宰治の作品に興味があり、その中で「女の決闘」は、森鴎外の同名の小説をパロディーにしたものですが、この小説の下敷きになったとされるドイツ人作家、オレインベルクの原書も含めた3作品を課題研究で比較するため、ドイツ語を独学で学んで読破したのです。この過程でドイツ哲学にも興味を持ち、最終的には数理哲学の道に進むことを決めました。数理哲学はコンピューターサイエンスの基礎にもなっており、ドイツがその分野で特に優れていると知った彼は、ドイツの大学に出願し、見事合格しました。
こうした実例は、教育現場での分野を超えた学びの重要性を示しています。特にデータサイエンスや統計学は、文系・理系を問わず必要とされるスキルです。文系の生徒でもビッグデータを扱う機会が増えています。文理融合的な学びは今後、さらに重要になるでしょう。早稲田大学などはそうしたことを見越して、学部に関係なくデータサイエンスを履修できるプログラムを設けるなどしています。
このように、理系、文系に分けるのではなく、それぞれの生徒の興味や関心を伸ばしていく教育が大切です。興味を持った分野が後に関連する新しい分野への理解を深め、広い視野を持つことが可能になります。
学校の歴史として探究的な学びが受け継がれてきたとのことですが、現在はどのような探究学習を行っていますか
(中根校長)探究的な学びにおいては、本を読んでレポートをまとめればいいというような形式的な学びで終わらせないようにしています。子供たちに寄り添いながら、何をやりたいのかをディスカッションし、サポートする体制が整っています。
SSH第Ⅲ期の大きな目標として、全員が課題研究(※)に取り組むことを掲げています。今までは高校1年生の4割程が行っていたのですが、学年全員が課題研究に参加し、教員全員が関わる体制を作っています。生徒たちが自分のやりたいことに取り組むことで、学びが楽しいと感じられるようになってくれたらと思います。また、近年の総合型選抜入試でもこうした探究的な学びの成果が評価されるようになってきています。課題研究を通して大学での学びにも繋げてほしいです。
また中学段階から知的好奇心を育む教育を行っています。中学では土曜日に探究の時間として「ワールドデイ」という時間を設けました。以前は授業内容を各学年に任せていたために、ばらつきが出ていましたが、「探究科」を設置することで、より体系的なプログラムを考える体制を整えました。大学で行われている面白い研究を紹介したり、さまざまなテーマを取り入れたりすることで生徒たちの興味を引き出すような内容を提供しています。中学の段階から知的好奇心を育み、高校ではさらに発展した探究学習に取り組むための土台を作っています。
毎年2月には探究発表会を開催し、生徒たちはポスター発表を行います。保護者にも来てもらい、卒業生がアシスタントとして参加することもあります。この発表会を続けているうちに、最近では教育関係者からも注目されるようになりました。大学の教授や近隣の小学校の先生方が見に来てくださるようになりました。学校間連携としてもさらに広がりを持たせていきたいと考えています。
(※)課題研究とは数学、情報、物理、化学、生物、人文・社会科学から1つ分野を絞り、実験・観察・調査の進め、研究成果の発表を行う取り組み
生成AIの活用についてはどのようにお考えですか
(中根校長)生成AI活用に関しても取り組めることは取り組んでいこうという姿勢で推進しています。最初からこの技術を拒否するのではなく、重要なのは生成AIの特性をきちんと理解し、どうやって上手に付き合っていくかという意識を持つことです。
もちろん、AIの活用には倫理的な問題や課題が存在します。しかし、それらの課題を恐れて使わないのではなく、使用しながら課題が出てきたらその都度改善していけば良いのです。なぜなら、技術の進化と共に教育も進化するべきだからです。
それでは、学校内での生成AI活用を推進している徳倉先生にお聞きします。具体的にどのようなステップで進めていますか
.jpg)
(徳倉先生)2023年7月に文科省から生成AIの活用に関するガイドラインを設けられ、本校では2024年度から先生と保護者を対象に事前説明を行いました。その後、教育振興部を中心に教員研修を5回実施し、教員に対して生成AIの使い方講座やリテラシー教育を進めていきました。実際の授業での生成AI活用はまだ模索途中なものの、校務における文書や指導案の作成、テスト問題作成などで生成AIを活用する教員は増えています。
具体的な活用事例を教えてください
(徳倉先生)試験問題の作成では、過去の問題を生成AIに読み込ませ、それを基に新しい問題を作成することで時間を短縮しています。授業では主に知識をまとめたり、文章を要約したりする作業に活用されています。また、総合探究や課題研究の時間で生徒たちがまとめた論文の要旨や発表用の資料作成、プレゼンテーションの練習においてもAIが役立っています。発表会での質問予測やそれに対する反駁の準備にも生成AIが活用されています。
生成AIの活用を推進していく中で、先生方の反応はいかがでしたか
(徳倉先生)生成AIに対して肯定的な先生もいれば、AIに依存しすぎる生徒が増えることを心配する先生も多くいました。しかし、研修を通じて見えてきたのは、キーになるのは使う側の人間の裁量ということです。適切な指示ができない、プロンプトをうまく打てないという点が生成AIを使いこなせるかに大きな影響を与えていると感じます。これからはAIが仕事を奪うのではなく、AIを使いこなせる人に仕事が集中していくのではないでしょうか。
具体的に研修では、初回~2回目で「生成AIとは何か」、「生成AIの使い方」、「リテラシー教育」について説明し、3回目で生成AIを使って実際に業務削減を試みるということを行いました。4回目では対外的に生成AIの実践発表を行い、最後の研修では最新の生成AIの紹介を行いました。実際に使ってみると、先生の反応は徐々に変わり、隣の先生が使っていれば使い始めるというように、初めに比べてだいぶ肯定的な意見が多くなったと思います。
生徒たちの反応はいかがでしょうか
(徳倉先生)生徒の順応はとても速いです。今年、中学2~3年生の全生徒にアンケートを取ったところ、約50%の生徒が学校外で既に生成AIを使ったことがありました。一部生徒たちは授業のプリントを読み込ませて自習用の試験問題を作成するなど、様々な形で活用しています。学校が指示しなくても、自発的に使っている生徒が多いため逆に心配でもあります。学校教育でしっかりリテラシー教育を行う必要があると感じています。
生成AIの良さとは何だと思いますか
(徳倉先生)生成AIの良さは対話の履歴が残ることです。人間同士の会話は録音したりメモをとるしかありませんが、生成AIとの対話は履歴が残るため、過去の対話を見直し、どのように考えたかを振り返ったり、もっとこうすれば良い答えがもらえたのではと考えたりすることで、メタ認知能力を向上することができます。
最後にお二人にお聞きします。生成AIの活用が日常のものとなり、シンギュラリティも近いと言われている現代において、教育とはどのようなものであるべきと考えますか
(徳倉先生)時代の変化に対応しようとする力、学び続ける姿勢など非認知能力を身につけることが重要だと思います。知識も大切ですが、目に見えない資質・能力を学校教育の中で培ってほしいと考えます。
またAIに依存しすぎるのは危険ですが、最終的な判断を行うのは人間です。補助的な役割としてAIをうまく利用する意識を持ってほしいと思います。生成AIはアイデア出しや自分が思いつかないものを創り出す力も優れていると思います。それを利用して、今後はアントレプレナーシップ教育等においても生成AIを使うことでオリジナリティあふれる教育ができるかなと考えます。
(中根校長)知識詰め込み型の教育よりも、創造力を働かせる教育をするためにどうすればよいかを考えなければなりません。そのためには教育実践する先生方が意識を変える必要があります。
かつての馬具メーカーが時代の流れに合わせて自動車部品メーカーに変わり、高級ファッションブランドへと変貌を遂げたように、考え方をどんどん変えていかなければ淘汰される時代でもあります。時代の流れを理解し、幅広い観点から今を考えることが必要です。イノベーションによって消えていく職業や商売もありますが、それでも存続するものもあります。人生100年時代とも言われる中で、生涯にわたり主体的に学び続けられる人材を育てるために、若手の先生のアイデアを積極的に取り入れながら、生徒たちの健康面にも留意しながら知的好奇心を育んでいきたいと思っています。