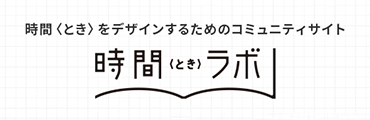貴校の教育理念について教えてください
本校は太平洋戦争の戦火を受けた沖縄県で、地元に貢献する人材育成を行う趣旨のもと設立されました。建学の精神は校名が示す通り、「南(沖縄県)を興す」という理念に基づいています。この建学の精神に則り人間教育を土台にした学習面の充実と部活動の活性化を教育方針として掲げています。具体的には、知・徳・体が融合する文武両道を目指し、活力に満ちたたくましく、情操豊かな人格を陶冶し、社会に貢献できる人材の育成を目指しています。
校長就任の挨拶(※1)の中で「新しいステージの文武両道」とおっしゃっておりました。新しいステージとは具体的にどういうことでしょうか。
興南学園と言えば、甲子園春夏連覇を成し遂げた野球部を率いた、我喜屋理事長の標榜する人間観や教育観が象徴的です。私たちはそれを「我喜屋イムズ」と呼んでおり、全人教育の理念を意味しています。興南学園には、この全人教育に基づいた部活動が精力的に展開されています。野球部だけでなく、全国制覇を成し遂げたハンドボール部や全国短歌甲子園で優勝を果たした短歌・俳句部など文化系においても活気あふれる部活動が多数存在しています。私が「新しいステージ」と表現するのは、これまで築き上げてきた素晴らしい部活動の実績に加え、特に学習面でもさらなる飛躍を遂げて行きたい、という強い想いがあるからです。まさに私たちは現在、新しいステージに立っていると感じているところです。
(※1) 興南学園 中学校・高等学校 新校長就任挨拶
https://konan-h.ed.jp/sp/topics/1680740615/#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%94,%E3%82%92%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
興南学園の生徒の印象や学校の雰囲気はいかがでしょうか。
我喜屋理事長の教育理念というのは人間教育です。それは単に学習面や部活動の実績を向上させることだけを目指しているのではなく、挨拶や身なり、清掃の徹底はもとより心の教育など人間的な成長も重視しています。
中学生は入学当初は、挨拶してもおどおどしているような、比較的おとなしい子どもたちが多いです。しかし、この校風に触れるうちに、次第にはきはきとした態度に変わっていきます。このような雰囲気は高校から入学してきた生徒たちにも伝わり、自然と融合されています。大変人懐っこい生徒が多い学校だとも感じています。
そのような校風をつくるためには先生方の雰囲気作りも重要だと思います。
そうですね。日頃から先生と生徒とのコミュニケーションがしっかりと取れている学園だと感じます。まるで家族的な雰囲気のような、良い意味で距離が近く、先生方も気さくな方が多いですね。
先生の働き方についてはいかがでしょうか
部活動は本当に熱心です。特に強豪部活の監督でもある先生方は、土日や放課後もずっと練習や試合等に付き合っているため、大変多忙だと感じます。昨今の働き方改革の観点からすると、外部委託や経験豊富な外部指導者を新たに招く方が良いという考えもあります。しかし、部活指導に信念を持った先生方が一生懸命に頑張っているのが本学園の特徴です。
ただ、先生方には振替休日や年休などをしっかりと取ってもらうようにしており、柔軟に休みが取りやすい環境を整えています。業務やスケジュールの適正な管理、休憩や有休のとり方など、プライベートを大切にすることも重要視しています。働きやすい環境にするために、これらは学校全体として、特に先生方と管理職が連携して、取り組む大きな課題だと考えています。
進路状況はいかがでしょうか
県外への進学がやはり多いですね。特に難関の国立大学や、MARCH、関関同立等私大への進学率が伸びています。特に総合型選抜で入試を受ける生徒が少なくなく、今年も慶應義塾大学にAO入試(総合型選抜)で合格した生徒が3名いました。本校の探究学習の取り組みが実を結んだ結果だと感じています。
探究学習ではどのようなことを行っていますか
本校は総合的な探究の時間に大変力を入れています。おそらく先生方の取り組みの熱心さは、県内の中学校・高校でもトップクラスだと思います。
中学校の総合的な学習の時間は「興南まなVIVA」と呼んでいます。郷土文化、経済など五つのカテゴリーに沿って、学年内でチームを編成し、生徒たちは相互に学び合い、探究しています。チームでの議論の進め方やプレゼンテーションの方法なども体系的に学んでいきます。例えばあるグループは夏休みを利用して沖縄の離島の医療環境を調査し、実際に診療所を訪ねたり、あるいは海洋生物に興味のあるグループは琉球大学の先生を招いて一緒に海岸に赴いたりもしています。 最終段階に来ると成果発表が行われます。まずは学年内で発表し、その後全学年での発表へと進みます。生徒たちはこのプロセスで互いに切磋琢磨しながら成長していくのです。
高校生になると、今度は個人的に身近な探究活動に取り組みます。KTP(興南探究プロジェクトの略)という名前を付けて興味関心のある分野を探究し、みんなの前で発表します。 また今年からの面白い取り組みとして、那覇市長や市議会議員に直接地域の課題を訴えて、課題を解決するためにはどうすれば良いのかまで提案しようとしています。
このような探究活動は短期的なものではなく、将来的な方向性、つまり大学を卒業して社会に出るための準備としても行っているのです。社会での活動や、自分の人生における探究へとつなげていくためのものです。「何のための探究か?」という問いに対しては、将来自分の人生の中で起こり得る様々な課題に対して、解を見出す資質能力を培うための活動だと答えています。 特に、難関大学でAO入試によって合格した生徒が多くいることは、本校の探究活動が高く評価されている証だと思います。
探究の学習の在り方について模索されている学校も多い中、貴校の先生方の探究に対する姿勢をどのよう見られていますか。
先生方は、学年団で毎週1時間、探究の時間のために集まり、議論や協議を行い、知恵を出し合いながら活動を進めています。この時間では、新たな課題や改善点を見つけ、次のステップに進むための具体的な計画を立てます。これらの議論を持ち帰り、授業やクラス内のグループに反映させています。
探究活動を効果的に機能させるためには、先生方の積極的な参加が欠かせません。先生自らが試行錯誤しながら学び合うことで、生徒にも新たな学びの機会を提供していくのです。例えば、新たなテーマを設定した場合、先生自身も知らないテーマ分野であれば一緒に勉強し、生徒と共に成長します。実際に先生方が学び合う様子を見ると、本当に感動します。
今、重点的に取り組まれていることはありますか。
急速に進むグローバリズムの中で、国際的な視野を持つ生徒の育成は喫緊の課題だと感じております。むしろ学校教育の責務でもあります。その観点から今年の7月には、夏休みを利用して約20名の生徒を募集し、オーストラリアで短期語学研修を実施しました10日間の研修を終えた生徒たちの満足度は97%と非常に高く、実りある経験となったと思います。 私も同行し、オーストラリアの学校と姉妹校を締結することになりました。今後は修学旅行や短期留学の受け入れを行う予定です。また、一ヶ月間の留学プログラムなども締結しようと考えています。同様の取り組みは台湾とも進めているところです。これからも積極的に国際交流を推進していきます。
生徒たちにはダイナミックに動く国際社会を肌で感じてほしいですね。現在では、様々な媒体を通じて外国の世界を知る機会がありますが、そのことと実際に行って、見て、聞くこととは全く違います。「百聞は一見に如かず」です。それを子どもたちに感じて欲しいと思っています。子供たちが一歩を踏み出すきっかけを学校側でも作りたいと考えています。
その他おもしろい取り組みがあれば教えて下さい。
特筆したいのは金融経済教育の取り組みですね。地元の沖縄銀行の支店に協力していただき、出前講座も積極的に取り入れております。特に、総合進学コースの高校3年生80名全員に銀行口座を作ってもらい、授業の中で実際に株を購入しその売買を行っているのです。これは、株や投資信託などの金融商品について学ぶためのもので、地域の銀行をもっと活用しようとする先生方のアイデアから実現しました。最終的に沖縄銀行の頭取まで話を運び、80名全員に1,000円の銀行口座を開設したのです。18歳未満の生徒には保護者の同意を得た上で行っています。
実際に株への投資を行うことは、そうでない生徒たちと比べると、金融教育の理解度には大きな差が生まれます。例えば、株価の上昇や下落、損益を経験することで、将来の資金運用についての考え方も深まります。文部科学省も金融教育に力を入れていますが、教科書だけでなく実際の投資を通じて学ぶことが重要だと感じます。金融教育を通じて生きる力を養い、自活能力を身につけることは何よりも大切だと感じるからです。
諸見里校長は沖縄県教育委員会の教育長も務めていらっしゃいました。沖縄全体としての教育についてどのようにお考えでしょうか
沖縄県の子供たちはどちらかというと比較的におとなしい子どもたちが多いです。これは良い点でもありますが同時に欠点でもあるのですね。首都圏の子供たちと比べると、がむしゃらに勉強するという気持ちが薄いとも言えます。沖縄の方言には「なんくるないさ」(「何とかなるさ」)という意味を持つ言葉がありますが、これは子供たちだけでなく大人たちもその影響を受けているかもしれません。もっと子どもたちを鼓舞して勉強させる必要があると感じています。
私は県の教育委員会に長く勤務し、沖縄県の教育の課題について深く感じていることがあります。学校教育関して言えば、大きく分けると、学習面と生活指導面に分かれますが、本県ではこの二つに大きな課題を有しています。例えば、小中学生の全国学力テストでは沖縄県がずっと最下位でした。生徒指導面でも基本的な生活習慣が乱れているケースが多く見受けられます。深夜徘徊や飲酒、喫煙といった問題もマスコミ等で報道されることが多いです。これらの問題の根底には、沖縄の歴史的・地理的な要因に加えて貧困が関わっていると考えています。沖縄県では約3割の児童生徒が「子どもの貧困」状態にあり、この状況が学力や生活習慣に悪影響を及ぼしています。
私が県の教育委員会に勤務していた頃、全国学力テストでの最下位脱却を目指し、義務教育課内に学力向上推進室を設立しました。先生方の授業力を向上させる研修制度を強化すると共に学校訪問を積極的に展開し指導助言を行いました。その結果、沖縄県は全国で47位から24位へ。そして令和元年には全国6位にまで上昇することができました。ところがコロナ禍の影響で再び最下位に転落しているのが現状です。おそらく大きな課題であった家庭教育の習慣がまだできていなかったのだと思量するところです。この点に関して現在は教育委員会と連携して「家(や)~なれ~運動」(※2)を実施し、家庭でのしつけや教育を促進する取り組みを行っています。「や~なれ~」とは沖縄の方言で「しつけ」を意味し、家庭での教育を強化することを目指しています。
(※2)https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/seshonen/1009535/1009541.html
これからの子供達にはどのような力を身につけてほしいですか。
21世紀は変革の時代であり、先が読めない状況にあります。生成AIの登場やウクライナ戦争、気候変動等々は、私たちの価値観を揺るがす大きな課題だと感じます。世の中に一つだけの解なんて存在しない。今まさに社会は新しい解決策を求めています。そのために、新しい解を見つけ出す力を持つ人材を育成することが必要だと感じるのです。このような時代の中で、子どもたちには探究する資質能力を養うことこそが教育者の使命です。こうした探究力は、日本ではまだ十分に育まれていない分野です。将来の人間の価値は偏差値で測れるものではなく、生きる力や問題解決能力にあると考えています。これからも生徒たちが人生の開拓者となれるよう、信念を持って教育活動に邁進していく所存です。