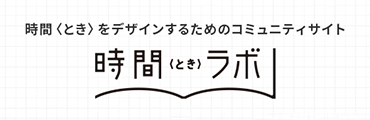生成AIの積極的な活用など、学校のIT化においては県内でも先進的な取り組みを行っておられますが、その背景を教えてください。
私自身もともとビジネスの世界の出身で、外資系の企業で複数社に渡り、改革やイノベーションの推進に携わってきました。その経験を活かして、茨城県が募集していた校長公募に手を挙げ、本校の校長になりました。民間企業で培った知識やノウハウを教育の現場に持ち込み、これまでにない新しい視点で社会課題を解決するイノベーターを育てることを目指しています。
イノベーションという言葉はビジネスの世界では常識ですが、学校の世界ではまだ浸透していません。私はこの文化を学校に導入し、自分で発信し、創造して、行動できる、「出る杭」になるような人材を育てたいと考えています。経済成長が終わり、工場のライン型の人材がパソコンや人工知能に置き換わる時代に、工業的な教育から脱却する必要があります。私のビジネス経験からも日本人のイノベーション人材が大幅に不足している実感があり、学校教育を通じて具現化させたいと思っています。
学校のIT化については、例えばGIGAスクール構想がコロナ禍の数年前に始まりましたが、社会全体で見るとこれは1990年代に始まったトレンドです。この時点で学校は社会の動きから30年ほど遅れているのです。同じ轍を踏まないよう、生成AIの活用については、世の中と同じタイミングで最新の技術を導入できるよう努めています。ファーストペンギンとして道を開拓し、生徒には世の中を生き抜くためのスキルをしっかりと身につけさせたいと思います。
デジタルに不慣れな現場の先生方への理解や行動の促進のためにされたことはありますか?
物事を変える際、一般論として、すべての人を一斉に変えようとすることは現実的ではありません。例えば、授業でパソコンを使いなさいとか、新しい技術を導入しなさいと言っても、教員全員が一度に動くわけではありません。
物事には、最初に手を挙げる好奇心にあふれた人がいる一方で、昔のやり方を頑なに守り続ける人も一定数存在します。変化というのは順番に起こるもので、段階的に進んでいくのです。
まずは好奇心旺盛で新しいもの好きな5~10%の先陣を切る先生たちが、新しい技術を試してみることが大切です。そうして実践することで、彼らの背中を他の教員が見て、少しずつ変化が広がっていきます。温度差は徐々に埋まり、最後にはそれが文化となり、意識せずとも自然にできるようになります。
このように、全員が一斉に「よし、やろう!」と動き出すことを期待するのではなく、まずは先行する少数派に対して変化の種をまくことが、変革を起こすための鍵です。段階的に広がるこのプロセスこそが、持続可能で効果的な教育の改革につながると信じています。
生成AIの授業・校務活用が浸透していくプロセスにおいて、全体のフォローアップとして行っていることはありますか?
全体のフォローアップとして、外部業者によるプロンプトエンジニアリングの研修などを行っています。ですが、生成AIはマニュアル通りに使う工具のようなものではないので、まずはやってみて、実際に使いながら授業や校務に活かしていくことが重要です。
留意しなければならないのは、ただ掛け声をかけて成功体験が自然に伝搬するのを気長に待っている余裕はもうないということです。以前もパソコンの一人一台利用が教育現場に浸透するまでに非常に長い時間がかかりました。同じことをまた繰り返していては、世の中の変化に追いつけません。ですので本校では昨年度より、生成AIに焦点を当てた授業研究日を定め、各教科に実践公開を課すなど、一歩踏み込んだ推進に取り組んでいます。
今の時代、シンギュラリティ—AIが人よりも賢くなる時—が近づいています。これからは、AIを単なるツールとして使うのではなく、自分たちのパートナーとして活用することが重要です。授業の一部をAIに任せることで、効果と効率が格段に向上する場面も増えてきています。 教育者としてはAIは敵であり味方でもある存在です。その存在が目の前に現れているのに、それに触らないという選択肢はありません。積極的に取り入れ、教育の質を向上させるための一歩を踏み出す必要があると強く感じています。
生徒の反応はいかがでしょうか?
子供たちは非常に柔軟で、すぐに触って覚えます。彼らは何でも試してみて、それが何なのかを自分なりに理解し、使いこなしています。 現在の学習指導要領にある三観点:「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習 に取り組む態度」、この中で特に重要なのは、最後の「主体的に学習 に取り組む態度」だと思っています。
個別最適な教育が求められていますが、先生が目の前のクラス40人全員に対して同時に個別の授業をすることは現実的には難しいです。気後れして先生に質問しづらい生徒も有数います。しかし、AIの助けを借りることで、子供たちが学びのエージェントとしてAIに質問し、個別に最適化された学びを得ることができます。
例えば、「ちょっと先生みたいに上から目線で教えてもらうのは苦手だから、最後にハートをつけてね」なんてリクエストもできます。子供たちは自分に合った学び相手をカスタマイズすることで、一人ひとりが学びに主体的に向き合い、学びを深めることができます。
実際の授業ではどのように使用しているのでしょうか?
例えば英語の授業では、「10年後、20年後の地元の未来を考えて絵にしてみよう」という問いに対して、画像生成AIを用いて英語でプロンプトを書かせます。日本語の発想は英語とは異なるため、日本語を英語に翻訳しようとするとネイティブらしいコミュニケーションにはならず、単なる置き換え表現になってしまいます。生徒に英語でプロンプトを書かせることで、生成AIが出力した画像を見て、自分の伝えたかったことがイメージと合っているか視覚的に確認できます。もしイメージと違う場合は、プロンプトに入力した英文をさらに書き換え、修正し、意図したものに近づけていきます。英語の学習が単なる翻訳作業ではなく、コミュニケーション中心の生き生きとしたものになるのです。
生成AIは、英語学習においてまさに画期的なツールであり、これまでにない新しい形の学びを実現しています。
民間出身の校長として、どのような点が教育現場の課題だと思いますか?
現在の学習指導要領には「総合的な探究の時間」、「公共」といった社会課題の解決をテーマにするような新しい科目が追加されていますが、実際に世の中で何が起きているのか、報道以上の生の現実を理解している教員は少ないです。
多くの教員は大学を卒業後、教員免許を取得してすぐに学校に入り、数十年もの間、教育の世界だけで過ごしています。そのため、現在のAIの進化や不透明な世の中に向けた教育を設計しようと思っても、実効性を伴わない表面的なものになりがちです。
社会と学校の間に距離感がある状態で、開かれた教育を実現するのは容易ではありません。学校は企業の方に出前授業を依頼したり、地域に開かれた学習を進めようとしますが、コミュニケーションがうまくとれなかったり、効果的なパートナーを取捨して互恵関係を築くことができなかったりすることがあります。
これを解決するためには、教員自身が社会との接点を増やし、実際の社会の動きやニーズを理解することが不可欠です。生成AIの導入においても、お墨付きのついた教員向けの情報を待つだけではなく、先行する一般社会の情報に積極的に耳を傾け、異業種の実践者コミュニティに加わり、いち早く活用を進めるべきです。学校と社会との温度差を埋めるためにも、教員が積極的にAI技術を取り入れ、教育現場での新しい学びの形を実現することが求められています。
AIの活用を検討する他の学校に対してアドバイスするとしたらどのような声をかけますか?
教員の皆さんには、「AIはあなたを取って食うものじゃない」ということを伝え、怖がらずに触ってみることを勧めます。これは明らかに、自動車が登場した時代に「人は機械に触れるな」と恐れられたのと同じことが現在も起きていると考えています。
現代においてAIや新しい技術に対して反発や恐れがあるのは当然ですが、それが当たり前になる時代はすぐそこに来ています。その時期を乗り越えるために、少しずつAIを日常に取り入れて行くことが重要です。私は日頃から教員には、シンギュラリティが近づきつつあることや、AIが人よりも賢くなる可能性について話しています。特に、詩や作文のようなクリエイティブな作業で、AIが教員すら唸るような質の高い結果を出していることを実感している人も多いのではないでしょうか。
このような技術進化を背景に、恐怖心や危機感もきっかけにして触れてみることが重要です。例えば、生徒がAIを使って作成したものかどうか、自分でも見分けがつかないと感じた時、その危機感こそが行動を促す動機となります。技術に対する理解と触れ合いを促進し、最終的にはAIを自然に使いこなせるようにすることが重要です。
生成AIによる教育方法が将来的にどのような形で進化していくと考えていますか?
AI技術の進歩により、従来苦手だった数学や詩・古文などの分野でも十分な活用ができるようになってきています。また、推論の機能強化により、回答の精度も格段に上昇しています。AIがより能動的なエージェントとなり、アバターやロボットの形を取って教えることが可能になる未来がすぐそこに来ているのです。これにより生身の教員とAIは、生徒一人ひとりが学びのスタイルに合わせて取捨選択する関係へと変化し、学校における学びのあり方に多大な影響を与えることが予想されます。
例えば、ソフトバンクの孫正義氏も「AGI(人工汎用知能)が10年以内に人間の知能を超える」と予測しており、それは決して遠い未来の話ではありません。現実にSNSで知り合った会ったことのない恋人がいるように、初恋の相手が生成AIという時代も確実に訪れるでしょう。変化の時代における教育者として重要なことは、一歩先の未来をしっかりと想像し、その未来に向けた準備を始めることです。未来は不確定だと棚上げにするのではなく、確定した未来に対してどのタイミングで準備を始めるかが問われているのです。