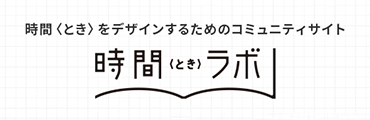貴校の理念、教育方針について教えてください
本校は昨年創立100周年を迎えた浄土真宗の学校です。仏教精神に根差した情操教育を建学の柱に据えています。創設者である高楠順次郎先生は、日本を代表する仏教学者であり、生徒たちに五戒、つまり5つの約束を教育の基盤として語り続けました。これらの五戒は、生徒たちに日常生活の中で実践するべき指針として根付いています。
<高楠順次郎先生の五戒>
今日は少なくとも一度、ありがたいなという感じを持ちましょう。
今日は少なくとも一度、苦しいなと思うことをやり遂げてみましょう。
今日は少なくとも一度、人に譲りましょう。
今日は昨日より新しい何かの知識か技能かを自分のものにいたしましょう。
今日は少なくとも一度、にこやかに語りましょう。
本校では、この五戒をいつも心の片隅に置いて生きていける人でありたい、そうした向上の心を持った人格の陶冶を目指しています。また仏教的情操教育の一環として、大乗仏教における六波羅蜜を現代風にアレンジし、6つの徳目を努力目標として掲げています。毎朝の「朝拝」や週1の宗教の授業などを通して、生徒たちは多様な角度から仏教的価値観を学びます。
近年では「探究学習」に力を入れていると伺いました。具体的な取り組みを教えてください。
2019年度に中学校、2020年度に高校が女子校から共学へと転換しました。これは新しい時代の教育ニーズに応えるための大きな一歩でした。これに伴い、仏教的情操教育という精神を大切にしつつも、現代の教育課題に応じた探究型の授業に力を入れるようになりました。
高校1年~2年においては、MAP(Musashino Arts Project)というプログラムを実施しています。このプログラムは社会で活躍するために必要な問題発見・問題解決力の育成を目的としています。高校には「ハイグレード」、「PBLインターナショナル」、「本科」という3つのコースがあり、各コースにおいて、それぞれの目標に応じた特色あるMAP、つまり探究系教育を週に2単位分用意し、専門の講師が教えています。
まず、ハイグレードコースは、日常の生活や事象の中の問題点を探り、問題の根底に存在する仕組みや道理を解明したり、問題の解決法を考え、生徒の「アカデミックマインド」を強化するプログラムを実施しています。医学部や国公立大学、難関私大を目指す生徒向けで、日常生活の中から問いを見出し、思考力を鍛えることを重点に置いています。
PBLインターナショナルコースは、主に1年間の留学を中心にしたプログラムで、海外大学や国内の国際系私大を目指す生徒向けの探究プログラムとして「アントレプレナーシップ」を養うための取り組みを行っています。商品開発や新規格の提案などグローバルな視点と実践力を育成しています。
武蔵野大学への進学を中心に幅広い進路の実現を目指す本科コースには、「LAMプログラム」というオリジナル講座を行っており、多様なジャンルの専門家をお招きしています。シナリオの執筆や社交ダンスなど多種多彩なプログラムを用意しており、生徒が自分自身の興味関心にあわせて選択し、活動しています。
校長先生から見て、探究学習における成果をどのような場面で感じられますか?
非常にアウトプットが上手な生徒が多いのにびっくりしています。人前でわかりやすく、エンターテイメント性も持ちながら、プレゼンテーションをするスキルが高いと感じます。保護者向けの学校説明会でも生徒主体でプログラムを考え司会も行います。自分たちで工夫して、堂々としたパフォーマンスを見せてくれています。このような力は、質の高い、探究型の授業による日々の積み重ねによって育まれたものであると言えます。
また、探究活動の集大成として、3月に「Mu-1グランプリ」というプレゼン大会が開催されます。中学1年から高校3年生まで、予選で選ばれた生徒たちが決勝大会でプレゼンを行い、非常に盛り上がります。探究におけるこれまでの学びの成果を感じられる大会です。
中学校ではどのような取り組みを行っていますか
高校での探究活動をスムーズに行うために、中学校ではその準備として「言語活動」という授業を行っています。週に2回行われるこの授業では、オリジナルのテキストを使い、ブレインストーミング、Tチャート、Yチャートといったアイデア出しから、分類、まとめる手法、討論、発表の仕方を学びます。中学3年間を通じてこれらの方法論を身につけることで、高校進学後の実践的な探究活動に取り組むための基礎が築かれます。
3年をかけて基礎的なスキルを身につけるのですね。言語活動を重視する背景にはどのようなお考えがありますか?
過去には校内暴力や家庭内暴力が社会問題として顕在化していましたが、現在では不登校の増加が社会的な問題となっています。このような生徒たちは、自分をうまく表現できないことで苦しんでいるのだと思います。自分を、あるいは自分の苦しさを上手に語ることができないため、その鬱憤が発散できず心に溜まり、やがてそれが暴力になったり、登校を渋ったりということになるのだと思います。そういった意味でも、言語活動や表現活動はとても大事です。もちろん思考力・対話力を身に付ける意味でも重要なことはいうまでもありません。
「言語活動」は、諸学の基礎となるものであり、それが本校では一つ一つ議論の進め方や、まとめ方の手法を学ぶことから始め、自然と表現力や話し合いができる力が身に付くように工夫されています。
また、本校の言語学習では、「反応は大げさなくらい大きくする」、「相手の意見は絶対に否定しない」というルールを重視しています。相手の意見を否定せず、受け入れる姿勢を養い、自分の考えを見直すきっかけを作ります。生徒が意見を述べる際に、批判されると話す意欲を失ってしまうことがあります。意見を自由に発言できる環境を整えることで、生徒は自信をつけていきます。これが将来、良き大人になるための準備となるのです。
環境を整えるために教師の立場として大切なことは何だとお考えですか
教師の役割は、生徒の現状を把握し、適切なアプローチを考えることです。例えば、「最近の子供は本を読まない」と言うだけでは教師としては失格で、その状況を打破するための具体的な方法を考え、実践することが教師の仕事です。
私が担任をしていた頃、例えば、百人一首を毎日1首ずつ黒板に書き、その感想を語ってみたり、自分が読んだ本のあらすじを劇的な効果を多少工夫して生徒に伝えたりしていました。生徒たちが少しでも興味を持ち、本を読もうと思うきっかけになればとの思いからです。実際には40人のクラスの中で、心動かされた生徒がいたかどうかはわかりませんが、それでも価値があると信じていました。教員は行動することです。生徒の成長過程にきちんとマッチした具体的な取り組みを考え、実行するのが教員の役割だと思っています
また、近年「個性」とか「自分らしさ」、あるいは「主体性」ということが叫ばれていますが、先述したわが校の探究活動なども、単に時流に乗じただけの軽挙妄動に終わってはなりません。見事な自己表現とは派手なパフォーマンスを意味するものではなく、地道な知的活動の積み重ねの所産であり、それは授業活動によって蓄えられるものという常識は忘れてはならないと思っています。個性や主体性をはき違えて理解している風潮が、自分にはそういう意味の個性も自分らしさもないと、自信を無くし悲観している生徒たちを生んでいる事実もあるのです。 本校は、本格的な探究型授業や発信力の育成と反復や継続に支えられた地道な学習活動とを、車の両輪のごとくバランスよく実践している学校です。そして、生徒の適性を見ながら具体的なアプローチを提供する学校です。
前任校では独自のノートを作成し生徒の時間管理力の育成を推進していたとお聞きしました。現在はいかがでしょうか?
私は、教育の目標はメタ認知能力をどこまで高めるかに尽きると信じています。メタ認知能力とは、自分を律する力といってもいいでしょう。メタ認知能力を高める最も有効な手法は「振り返り」です。 前任校ではTQノート(タイムクエストノート)を作り、楽しみながら時間を管理するという取り組みを行っていました。世界一周の地図を使い、勉強時間に応じてマークをつけていくことで、ゲーム感覚で時間管理を行うことができ、中学生にも好評でした。
また振り返りのページには一言でもいいので日々の振り返りを書き、教師がそれにコメントを返すようにしていました。これを続けることで、生徒たちにとって振り返りが習慣となり、最終的には強いメタ認知能力を身につけることができます。
本校でもすでにこのTQノートに類した取り組みを始めています。メタ認知能力を高めることは、大学進学やその先の人生での成功を支える基盤になります。ですが、誰もが意義を理解する一方で、仕組みがなければそれを達成することは難しいでしょう。だからこそ、教育現場での具体的な取り組みと継続させる仕組みが大切なのです。例えば、毎朝テストを行い、授業の範囲を確実に習得させるなど、小さな積み重ねが大きな成果につながります。こうした日々の取り組みが、生徒たちのメタ認知能力を高め、最終的には自立した社会人としての成長に寄与すると信じています。
教育の質向上において大事なことは何だと思いますか
教育の質を向上させるためには、目標設定、システム構築、環境整備の三位一体のアプローチが不可欠です。しかし、これを実現するための最終的な鍵は教師や親などの大人の関与です。教師が生徒一人ひとりに適切なフィードバックを提供し、親が家庭での学習をサポートすることが、生徒の成長に直結します。具体的なシステムや教材、学習環境を整えつつ、教師や親が真剣に関与することで、生徒は自己管理能力を高め、将来に向けた強固な基盤を築くことができます。
本校の教育理念と取り組みは、伝統と革新が融合したものであり、生徒たちにとって最適な教育環境を提供しています。仏教精神に基づく価値観を大切にしつつも、時代のニーズに応じた教育を実践することで、生徒たちが未来に向けて大きく羽ばたく力を育んでいきたいと考えています。