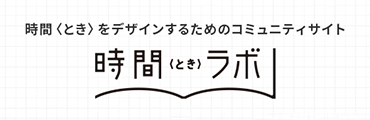まずは開智中学・高等学校の教育方針として大切にしているとこを教えてください
本校では生徒の主体性を重んじているため、生徒自身が考えて行動し、学校生活を送れるようにするためにはどうすれば良いかということを考えています。2021年の校長就任時から3年間は「外へ、未来へ」という学校目標を掲げ、学校の外に出て様々な経験をし、視野を広げて欲しいと伝えてきました。おかげで学校外での活動は多様化、活発化し、模擬国連や様々なコンテストに出場する生徒も多く、また地域とのつながりとして近隣の高齢者の手伝いや地元産業に関わる活動をしている生徒もいます。ですが次のステップを考えたとき、では外で「何を創造するのか」、「何を解決するのか」を重視したいと思い、今年から学校目標を「創造×解決」にアップデートしました。AIにさまざまなものが置き換わる現代社会においては、人間の創造力がどこまで発揮できるのかということが問われています。また地域や社会の問題をどう解決するのか、自分事として捉え、向き合う力も必要です。誰かが解決してくれるという他力本願ではなく、どうすれば自分たちで解決できるのか考えて欲しいと思っています。
「創造×解決」の目標に向かって取り組みたい具体的な案はありますか
創造力や問題解決力をどう身につけるかといっても明確な答えがあるわけではありません。創造の中には、学校生活を創る、学校行事を創る、あるいは自分の人生を創るなど、様々なレイヤーがあります。言葉を定義するのではなく、創造とは、解決とは何かを生徒と一緒に模索していきたいです。
貴校は開校以来、全国に先駆けて探究学習に取り組まれています。他校の探究とは違うと思う点はありますか
昔から探究学習をやっていることもあり、教員も生徒も探究の意義を理解しています。探究をやるのは当たり前で、どうやるかということに意識が向いています。
また探究を行う上で、疑問の発見→仮説→検証というサイクルを重要視しています。特に日常生活の中で見つけた疑問を大切にしよう、ということは常日頃から言っています。例えば、日直日誌には今日の疑問という欄があります。何でもよいので、生活や授業の中で疑問に思ったことがあったら書き込めるようになっています。「なぜ」にこだわることをずっとやってきたおかけで、小さな疑問を大事にする習慣が自然と身についていると思います。
疑問から探究の種となる本質的な問いにたどりつくためにはどうすれば良いと思いますか
何でもいいから疑問を出そうと言っても、なかなか思いつかないことも、表面的な疑問になってしまうこともあります。とにかく初めは難しく考えすぎず、とことん好きなことを深め、その中での気づきを大事にしていくことです。中学に入学した生徒の春休みの宿題では好きなものについての探究課題が出ます。好きなものを徹底的に掘り下げてみることを目的にしています。そして、なぜを10回繰り返してみるように声掛けしています。最初は表面的な思い付きでも、なぜを繰り返すことで、深い本質的な疑問にたどり着くことができると思います。
また、長期休みには家の外に出かけることを推奨しています。家族旅行でもよいし、近所の散歩でもいいです。とりあえず出かけてみて、注意深く周りを見渡していると、何かおもしろいことがあり、それが問いになることもあります。
なぜは重要な出発点ですが、これからは自分なりの仮説を創造する、検証して改善していくことがより重要になると思っています。仮説を立てるには創造力が必要なので、これからは仮説をどう作っていくかにこだわっていきたいです。
生徒は中高を通してどのように探究に取り組むのでしょうか
1~4年生までの生徒全員が個人の探究テーマに取り組みます。1年ごとにテーマ選定を見直す機会があり、同じテーマを継続して取り組んでも、途中で変更しても構いません。また人前で発表する機会も多くあります。他の人はどのように考えているのかということを知ることで、お互いの刺激になり、良い影響を与え合っています。 また高校1年生では、中学3年生までに取り組んできた探究テーマに関連する実地調査を行う首都圏フィールドワークがあります。大学や企業などに訪問し、専門家に話を聞きに行き、アドバイスをもらったり、自分で立てた仮説を検証したりしながらテーマへの学びを深めていきます。
探究指導をする上で重要視するポイントはありますか
探究学習が調べ学習で終わってしまうという課題を持っている学校も多いと思います。ネットで調べた情報だけで終わりにならないように、自分の足で得た独自情報がきちんと入っているかを重視しています。誰かが言っていたことを引用するのではなく、自分で考えたオリジナリティのある解決策なのか、その独自性を大切にして欲しいです。 また論文検索の仕方などリサーチ方法についても教えています。表面的になぞるのではなく、より深く知識を得るということを心がけています。開智の探究は大学のゼミでも役に立ったと言ってくれる卒業生も多くいます。
2021年度からコース選択制にした背景について教えてください
本校の理念として「社会に出たときに活躍できる人になって欲しい」という想いがあります。目先の大学進学が目的ではなく、何を学び、学んだことをどのように活かして社会に貢献できるのかを考えられる人を育てたいです。そのためには将来のことを考えて、自分の人生を自分で作っていくという意識を持つことが必要です。少し前まではとりあえず有名大学に入り、定年まで一社で働くというようなモデルがありましたが、今はそうではありません。何をやりたいか、何ができるのかを問われる時代です。自分自身の人生を考え、何が今必要なのかを考えて欲しいと思い、4つのコースを選択できるようにしました。大事なのはまず選ぶことです。自分の選択によってその後の状況が変わるということ、大人が全て準備してあげるのではなく、自分で選ぶという経験が大事だと思います。
進路についてはいかがでしょうか
現在は一般入試での大学進学が多く、塾や予備校に行かずに大学受験をする生徒が多いです。高校2年生の後半以降は放課後特別講座を行っています。受験指導と言えば一斉講義型のようなものをイメージすることが多いかもしれませんが、生徒同士で教え合う、学び合うという探究型のやり方を取り入れています。数学の問題でも解き方や英文の訳し方など、生徒がホワイトボードに書いて議論し合っています。皆で話し合って進めていく機会が多いので、協働して何かを作り上げていく力が身についていると思います。一般的な受験勉強のイメージとは違って、生徒からは楽しいという言葉を聞くこともあります。
開智の生徒にはどのような力を身に付けて卒業して欲しいと思いますか
自分の人生を自分で作り上げていってほしいと思っています。決まったレールやパターンに乗るのではなく、自分で進むべき道を見つけて欲しいです。そのためには創造力や問題解決力が必要です。本校における学びを通してその力を身に付け、社会に出てからの活躍に繋げて欲しいです。