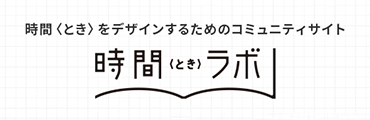まずは、おかやま山陽高等学校の教育方針、大切にしていることから教えてください
本校は昨年度創立100週年を迎えました。高等女学校として開校し、戦時中には工業高校へ、高度経済成長時には土木科や建築科を設置するなど、「時代に必要とされている人材を育成する」という目的のもと、進化してきました。そして今から40年ほど前、先代の学校長に代替わりしてからは、第二創業期として、調理科や自動車科などを新設し、「生徒の持ち味を生かし、地元で必要な人材を育成する」という方針を明確化しました。現在は機械科、自動車科、調理科、製菓科といった専門科に加えIT、公務員、音楽、スポーツといった専門コースがあります。普通科を中心に進学を目指す高校が多い中、本校は進学だけではなく、早くからキャリアプランを見据える教育を行っています。 一方で新学習指導要領に変わるタイミングで、特別進学コースを新設し、総合型選抜型の入試で進学を目指す生徒のために探究型プログラムを導入しました。
わたしの国際基督教大学(以下ICU)時代の同級生で、国際バカロレア教育(以下IB)の教員養成の専門家でもあるダッタ・シャミ先生と共に、IBの発想に基づく、思考力を鍛える学習を取り入れています。
とはいえ、学校として軸になっているのは、生徒一人ひとりの持ち味を生かすというものです。その生徒の一番良いところを伸ばして、それぞれが幸せな人生を送ることができるよう導く教育を展開しています。
専門科、専門コースに入学する生徒はどのような生徒が多いでしょうか。専門的な道に進むうえでどのようなキャリア教育をしていますか。
高校入学時点で、自分の将来を見据えて、これで勝負していきたいと心意気を持って入学してくる生徒が多いです。そのため、普通科高校のようなキャリア教育は行っていません。本校では、専門学校と同等の内容をリーズナブルに、早くから取り組むことができ、専門の国家資格等も取ることができます。卒業時点ではまだ18歳ですが、専門学校と同じレベルの技能を習得しており、さらにモチベーションも高いため、離職率が低く、就職先からも評価してもらえています。
また本校の学びの特長として、現場のプロの方から実際に学ぶことができるという点が挙げられます。製菓科・調理科の実習ではプロの方に講師として来てもらっています。また機械科・自動車科の教員は、実際に企業で働いたり若手指導をしたりした経験を活かして本校に転職してきた人たちです。現場を知る教員に直接教えてもらいながら、その背中を見て、さらに業界事情などの話を聞くことで、働くことへの理解と意欲を深めていきます。
学科、コースによって学ぶ内容、特色、学習の進め方も異なるかと思います。どのように個々の学科、コースを束ね、一つの学校として運営していますか。
わたしはいつも各コース、学科に「それぞれが独立した子会社のつもりで頑張って欲しい」と言っています。生徒が実際に活躍していく業界のことをよく知っているのは各現場の教員なので、なるべく権限移譲をして、例えば実習講師の選任、依頼する分野、教授内容なども基本的には各担当に任せています。最終的な判断を下す時は、生徒のためになるか、実践的な意味で役に立つかという軸で見ています。また生徒のレディネスや意欲、ポテンシャルは様々ですので、全員がきちんと修了することができるカリキュラムなのか、指導体制なのかという点は全てに共通して重要視しているところです。
探究型カリキュラムを導入するに至った背景について教えてください。
ちょうど現在の新学習指導要領へ転換するとき、ICUの同期であるダッタ先生と20年ぶりくらいに再会しました。ダッタ先生が大阪の私立高校でIBをはじめとする先進的な教育を長年主導された経験をもとに、教職大学院で教師教育に携わっていると聞き、ぜひ力を貸してほしいとお願いしました。 新学習指導要領を一読した時、日本の教育は、我々がICU時代に受けたリベラルアーツ教育にシフトすると感じました。さらにそれに伴い、大学入試も一般入試から総合型選抜へと主軸を移行していくという。これまでの教育改革と違い、今回は本当に大学教育・入試の在り方が変化すると直感しました。 今までは記憶力や知識を蓄積する力が強い生徒が、学力が高いとされてきましたが、大学入試において総合型選抜が主流となってくると、必ずしもそうではなくなっていきます。問題処理能力、対応力、発想力、アウトプット力など、実社会の仕事で求められる力に近いスキルが大学入試でも求められています。
実は、本校の卒業生は起業率が高いのですが、社会で成功しているかどうかと、在学中の学力パフォーマンスは必ずしも一致しないことを以前から感じていました。ならば「できる」とは一体何なのか。実社会で求められるリベラルアーツを伸ばすためのIB的な教育を、一部のエリート層だけではなく、たとえば現在本校にいる「普通の子」たちに適用したら、どんな化学反応が起きるのか。それがカリキュラムを改革した動機でした。
改革をはじめて今年で6年目です。まずは教員が変わらなければ何も変わらないので、ダッタ先生にお願いし、当時の若手教員を対象に、教員向けセミナーを毎月行ってもらいました。最終的には専門学科を含めて、すべての学科の普通科科目がリベラルアーツになって欲しいと思っていまが、まずは特別進学コースを中心に、探究型の授業をできる人を育成しています。去年は改革1期生が卒業したのですが、非常に力が伸びた生徒もいて、総合型選抜で慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(以下SFC)に合格しました。

探究型カリキュラムの導入にあたりサポートされているダッタ先生と、特別進学コースのコース主任である木戸先生にお聞きします。実際に現場ではどのような取組みをしているのか教えてください。
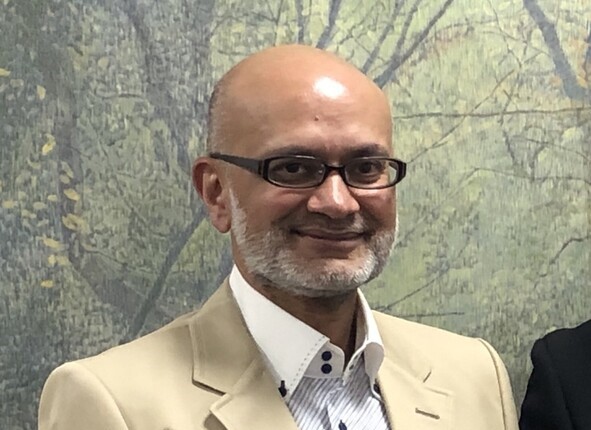
元 関西学院千里国際高等部 社会科教諭・進路・教務IB部長
日本国際バカロレア教育学会副会長
ダッタ先生:探究型の学びを展開するためには、まず教員自身が探究者にならなければいけません。そのため、初年度は進学コースの教員に向け、自分の授業の強み、課題、機会などの分析をするということを半年間行いました。中心メンバーから徐々に広げていき、2年目からは進学コースの実際のカリキュラムの中に探究型学習を取り入れていきました。知識学力と探究学力は相反するものではなく、相互作用するものです。知識が増えれば増えるほど、問いも増えていきます。知識学力と探究学力は同時に育つのが理想という認識のもと、授業の中で探究を入れていきました。また教科横断的な学びについても取り組んでいます。今後大学においても、学際的な学び、つまり教科横断的な学びが行われているのかが重要な指標の一つになるそうです。人間は生きていく上で、様々な学びや知識を総合的に繋ぎ合わせて考えていくことが必要ですが、学校システムの便宜上、どうしても縦割りになってしまっています。現在は実験的に数学と英語を組み合わせるなど、教科横断的な学びの充実に向けて取り組みを始めています。

進路指導部 進学担当課
特別進学コース コース主任
木戸先生:進学コースで2007年から指導しています。当時から推薦入試やAO入試に挑戦する生徒は多く、思考力や表現力を活かした面接や小論文における総合評価では十分に受験で勝負ができると感じていました。そのころは一部の生徒に個別指導を行っていましたが、その中でぽつりぽつりと生徒が国立大学に合格しているところや、大学入試の主流が総合型・学校推薦型選抜に移行する時代の流れを見て、一部の生徒だけではなく、クラス全体の指導やカリキュラムを探究型に変えていくことで、さらに生徒の持ち味を伸ばし、希望進路に実現につなげることができると考えました。
現在の総合的な探究の時間においては、地域の創生活動を題材としています。フィールドワークを主体的に行って、説得力のあるビジネスプランの構築を目指しています。また探究活動の中で先を見通す力も身につけて欲しいと思っています。思いついたアイデアを形にするためにゴールから逆算して計画、実行する行動力が大切だと考えています。PDCAサイクルを3~4回まわしてブラッシュアップしていくことで、実現に向けて説得力のあるプランに仕上げることができます。そういった探究サイクルの中で、総合型選抜で評価される力を養えるようカリキュラムを考えています。
SFCに合格した生徒はどのような活動を行っていましたか?
木戸先生: 1年生のころから地域の特産物の魅力を発信するというテーマで探究活動に取り組んでいました。その生徒は、地元の特産品であるマコモタケの廃棄部分を牛の餌にするというビジネスモデルを考案し、地元の農家や畜産業の方、企業にも出向いてどうすれば良いかを試行錯誤していました。そのプロセスが興味深く、自分で発信しアイデアを形にする勉強がしたいということで、慶応SFCを目指しました。3年生の時はもっと良い飼料の作り方はないか探究し、大学の先生に話を聞きに行くなどしながら、コンテストにも出場して全国で準優勝という成績も残しました。そのような主体的な取り組みが評価されたのではないかと思います。

今後はどのようなことに力を入れていきたいですか?
木戸先生: 高校生の発信力には大きな魅力があると考えています。英語力をはじめとする多様な表現力を養い、自分の意見をより多くの人に伝えられる生徒を育成していきたいです。その育成のために各教科での連携や探究学習の深化に取り組みたいです。
ダッタ先生:問いを見つけ、追及する力を身に付けて欲しいと思っています。例えば身の回りにあるものから、なぜこれはこの形になったのか、なぜ日本ではこの分野の産業が盛んなのかなど、問いの種を見つけ、その問いの答えを探究できるような教科授業にできたらいいなと思います。身の回りのものに対する疑問は、歴史の中に答えがあったりします。そういった問いを授業の中に取り入れ、生徒がオーナーシップを持って授業を進めることができたらなお良いと思います。また広告を題材にして国語の授業をやってみても良いかもしれません。教員は学びの伴走者として、学習者が自分で問いを見つけ探究するというプロセスから、教科学力も伸ばしていくことが理想です。世の中から疑問を見つけてきて、そこから考えていく、そういった授業に挑戦していきたいです。
原田校長:正直なところ、総合型選抜入試の趣旨や仕組みが、中学校や塾の先生、保護者にきちんと理解されていないと感じます。なぜ結果がでたのかということを理解してもらうために、まずは総合型入試について正しく理解してもらうためのプロモーションが必要です。また、時間に余裕がある中高一貫校の方がカリキュラム的に有利になってしまいます。高校3年間の限られた時間を使ってどのようにやっていくのか、試行錯誤の部分が多いですが、確証をもってやっていける道筋をはっきりさせたいです。
それでは最後に原田校長にお聞きします。貴校の生徒には高校3年間の学びを通してどのような力を身に付け、どのような人になって欲しいと思いますか?
私は、賢さは後天的に身に付けられると考えています。賢い人の「思考のスタイル」を身に付ければ、誰でも同じように考え、結果を出すことは不可能ではないと思います。社会的に成功している人は、失敗を恥ずかしいと思わないタフで前向きな人が多いです。生徒たちには、まずは自分を縛り付けている心のリミッターを解除し、もっと生意気に、もっと怖いもの知らずになって欲しいと思っています。探究型の学習にはそれを実現する力があると私は感じています。