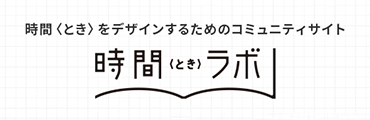能率手帳スコラの導入の経緯
能率手帳スコラを導入した経緯をお聞かせください。
そうですね、まず、低学年の家庭学習時間を増やすにはどうしたらいいかということが学校としての課題の1つでした。
これといって良いアイデアがなかったのですが、試験的に昨年の1年生が学習記録簿を導入しました。
毎週土曜日朝のSHRで学習記録簿を生徒に渡し、1週間単位で自分が勉強したところをマーカー(記録)させ、帰りのSHRで担任が回収しました。
その結果、それまでの生徒たちより学習時間が増えたというデータが取れました。それで、「記録する」ことが有効であるということが解りました。
能率手帳スコラを導入するきっかけはありましたか?
私は進路主任をしており、毎年難関大学に合格した卒業生と話をする機会があります。
そのうち2人の卒業生から、受験の時に学習記録をつけ続けて、第一志望に合格したという話を聞きました。ノートを1冊買い、計画を立てて、実践した記録をつけ、定期的にふりかえって、計画の調整を行ったのです。
1人は高3の4月から、もう1人は6月から始めて、夏以降に成績が伸びたそうです。学習記録は、自分の勉強の癖、科目ごとの時間配分、次に何をするべきかなどが一目でわかり、またこれだけ勉強したという達成感も味わえるので、受験勉強にとても役立ったそうです。 私はそれを進路通信で紹介しようと考え、コピーを取らせてもらいました。
ある日の進路部会の際に、朝日新聞に掲載された能率手帳スコラの記事を進路部の先生が持ってきて「これがいいんじゃないか?」という話がありました。
その後、能率手帳プランナーズさんへ連絡をして営業の方に訪問をいただき、実際の手帳を拝見したところ、とても良いということが解り、学校で導入の検討を行いました。
そして、導入、及び使用開始は4月からの新入生を対象にということになりました。