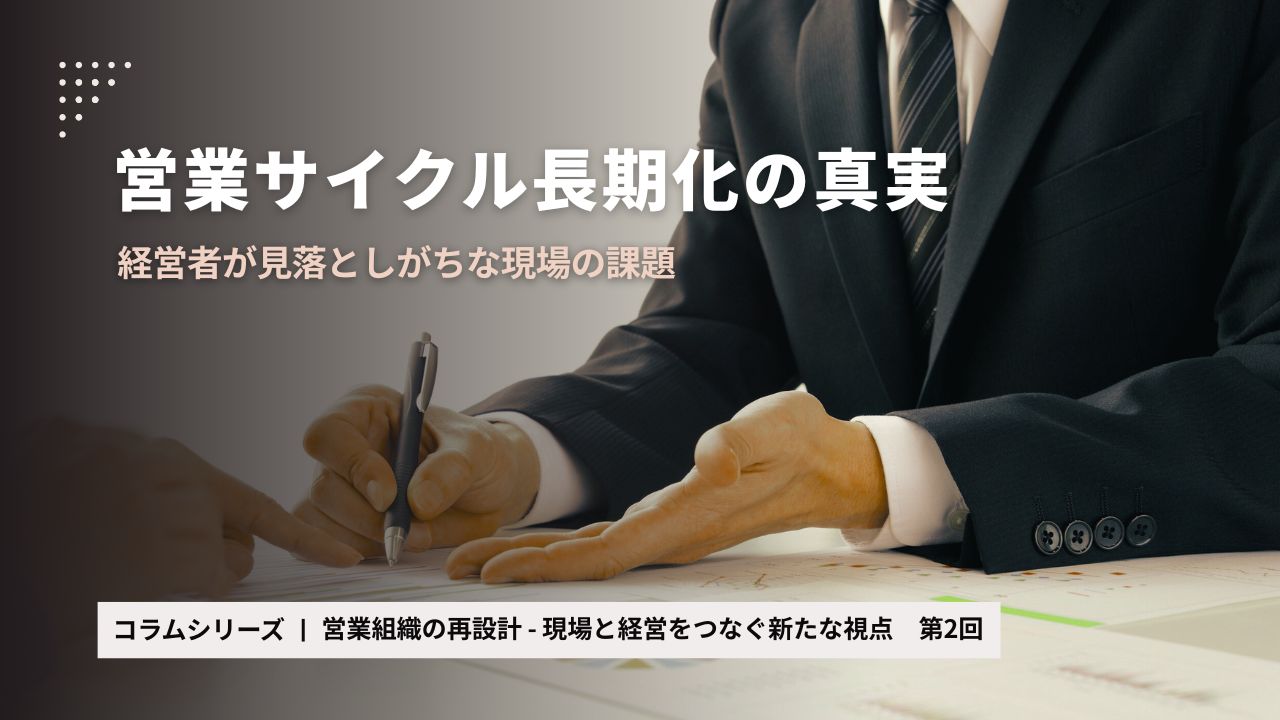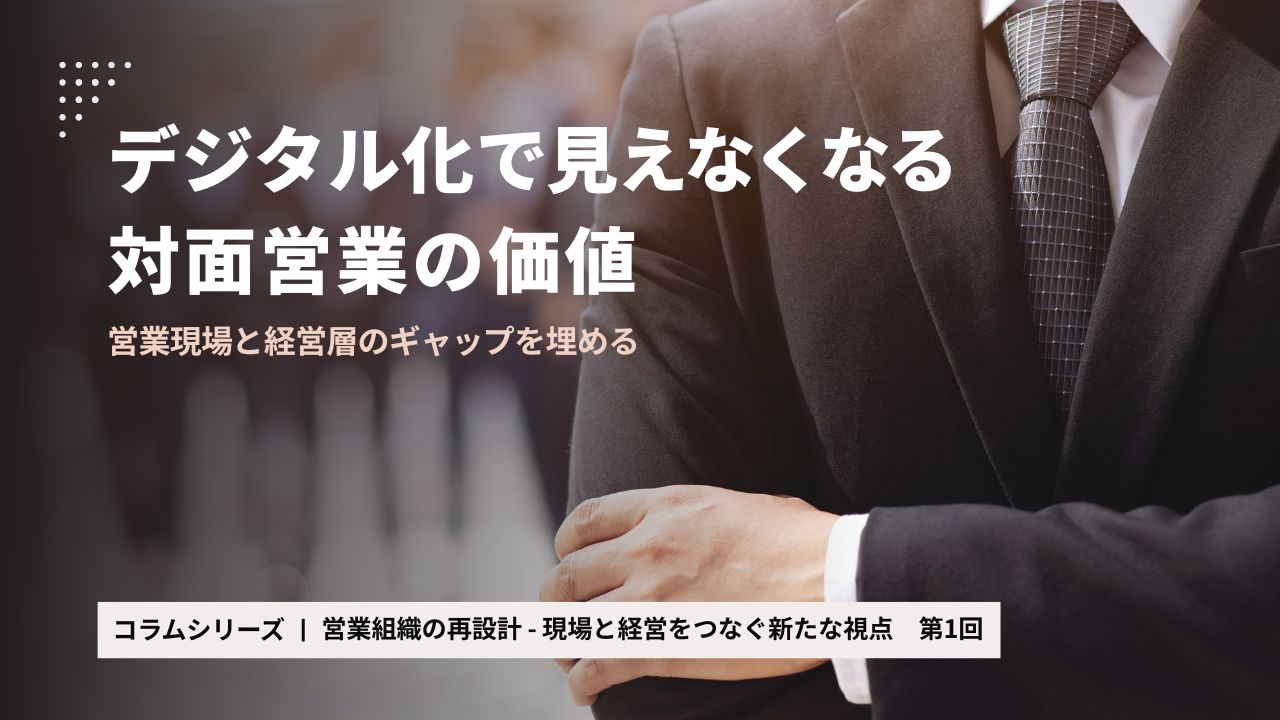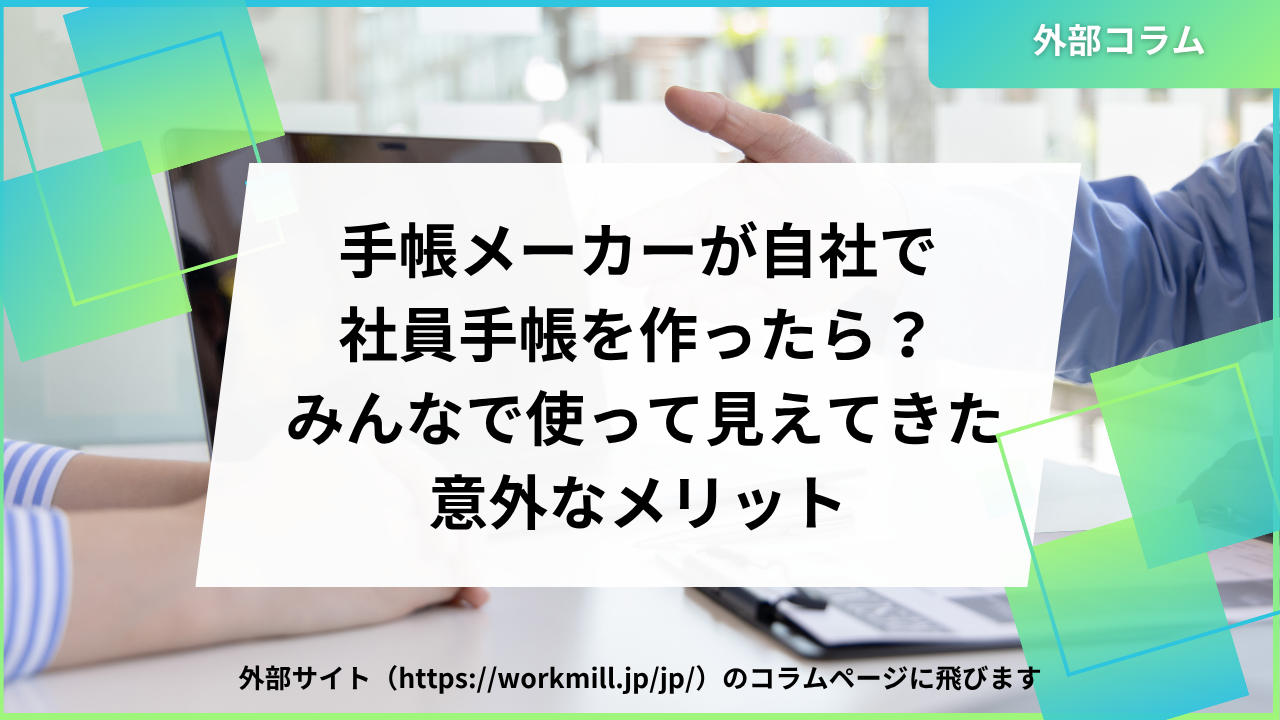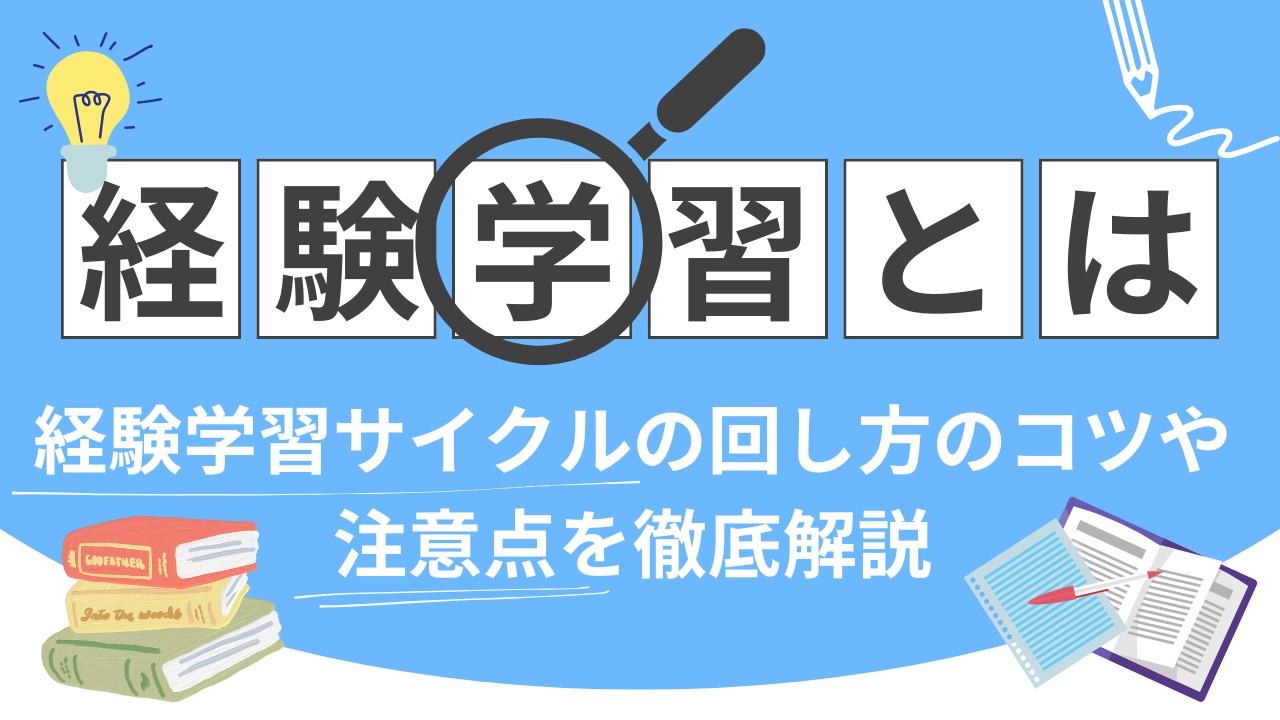
経験学習と聞いたことはあっても、実はどのような内容か具体的によくわかっていない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、経験学習サイクルについて実施するコツ・注意点について詳しく解説します。実践したいと考えている方に参考になる内容であるため、ぜひご確認ください。
目次
経験学習とは

経験学習とは、経験を通じて学んだ内容を次に活用するという意味の言葉です。特に、ビジネスで重視されており、仕事の業務で実施した内容を学習して、次に活かすプロセスとして重要と考えられています。
座学も必要ですが、ビジネスでは実際の取り組みから学ぶケースが多いため、仕事での成長の多くは経験学習ともいえるでしょう。
経験学習に取り組むメリット

経験学習のメリットは、効率よく学べる点です。座学では理論を学びますが、経験では予想外の出来事が起こる場合があります。良いことやトラブルなどを含めて、総合的な学習が身につくのが特徴です。
また、新入社員・リーダー・管理職など、どの職位やどんな企業に在籍していても、経験学習で学んだ内容を活かせます。個人の成長が組織の発展につながるでしょう。
反対に、経験学習を実践していない場合は成長を感じにくいケースがあります。自分では経験を次に活かせると思っていても、正しいステップで経験学習サイクルを回せないとロスが生まれるためです。
次に、経験学習サイクルの正しい回し方について詳しく解説します。
タッチポイントを設定して活用する手順

経験学習サイクル(モデル)はデービッド・コルブが提唱したものです。日本では、「職場が生きる 人が育つ「経験学習」入門」という本を執筆した、青山学院大学経営学部経営学科教授の松尾睦氏が有名です。
経験学習サイクルには以下の4つのステップがあります。
1.具体的な経験をする(具体的経験)
2.振り返って内省する(内省的反省)
3.情報をまとめて教訓にする(概念化・抽象化)
4.行動の修正や実践を繰り返し行う(能動的実験)
上記の4つのステップのサイクルを繰り返して、経験学習が強化されていきます。続けて、それぞれのステップについて詳しく解説します。
ステップ1.具体的な経験をする
目標を設定して経験する、というのが最初のステップです。その目標は個人に合わせて、適切なレベルを設定しましょう。
企業や組織で経験学習サイクルを実施しており、過去の事例を参考にできる場合は設定しやすくなります。ない場合は、一番近くで見ている上司と面談して決めるのがおすすめです。
目標設定が一番の要で、適度な難しさにするのがポイントです。低すぎたり高すぎたりすると、経験学習の効果が十分に得られません。既にできている目標より少し上の内容にしましょう。
ステップ2.振り返って内省する
内省的反省が次のステップです。経験した内容を振り返って内省します。経験学習サイクルでは、リフレクションと呼ばれます。
経験を通して何を学んだか、振り返るのが大事です。内省のポイントは、積極的なアウトプットにあります。学んだ内容を一度すべて書き出して考えると、自分で整理しやすくなるでしょう。
ステップ3.情報をまとめて教訓にする
概念化・抽象化のステップでは、内省でアウトプットした情報をまとめて教訓にします。
まず、「うまくいったもの」と「うまくいかなかったもの」に、分類するところからはじめましょう。うまくいったものは継続する、うまくいかなかったものは、どうやったらうまくいくかという観点で仮説を立てるところまでを実施します。
次に似たようなシーンに直面したときに、同じような失敗をしないために抽象化しておきましょう。
ステップ4.行動の修正や実践を繰り返し行う
ステップ3で抽象化した教訓を活かして、次に実践するというのが最終ステップです。自分自身が成長した状態で、ステップ1に戻るようなイメージです。
内省して教訓にまとめているため、似たような問題に直面しても乗り越えられるでしょう。そして、また同じように目標を立てて経験していきます。これらがサイクルになって経験学習で強化されていきます。
経験学習を取り入れるコツ

経験学習を取り入れるコツは以下のとおりです。
●積極的に経験する
●コミュニケーションを活性化させる
●内省については周囲の人々でサポートする
●経験が活かせているかチェックする仕組みを作る
「積極的に経験する」のがコツである理由は、行動が多くなるほど、サイクルをたくさん回せるからです。同じ時間でも回数が多くなるほど、経験学習として早く強化されて成長も早いでしょう。
企業においては、人事ローテーションや配置転換でさまざまな経験をさせる、というのも当てはまります。
また、職場や学校などでコミュニケーションが活発だと、内省時の分析の視点が多くなったり、抽象化・概念化の効率が良くなったりします。
同様に内省的反省や抽象化・概念化がうまくいかないときにサポートするというのもポイントです。経験学習サイクルをうまく回すにはコツがいるため、上司や有識者でサポートしましょう。その際に、あらかじめサイクルの各ステップでフィードバックする仕組みを作っておくとよい、と考えられています。OJTや1on1など、目的に合わせて取り入れましょう。
部下・後輩の経験学習サイクルを円滑に回すには

部下・後輩の経験学習サイクルを円滑に回すポイントはいくつかあります。
●客観的な視点でフィードバックをする
●面談で主体的なアウトプットを引き出す
●抽象化したものを持論にしてもらうような気づきを与える
内省的反省時や概念化・抽象化のステップで、部下や後輩にフィードバックを行います。1人では視野が狭くなっている可能性が高いため、別の目線・切り口で話すとよいでしょう。
また、フィードバックは面談がおすすめです。事前にデータで提出してもらってもよいですが、実際に話すことによってアウトプットを引き出しやすくなります。
ポイントは、面談相手として意見を押し付けないことです。部下や後輩から主体的なアウトプットを引き出しましょう。
抽象化・概念化するステップでは、まとめた法則のようなものを「その方の持論」にするように質問をしてあげるとよいでしょう。まずは多くの話を聞き、「過去にも似たような内容ではないか?」「実は別に見えていたものの共通項はあるのではないか?」と本人が気づくように質問してみましょう。
経験学習サイクルを回すうえでの注意点

経験学習サイクルを回すうえでの注意点は3つあります。
●振り返りの時間を設ける
●頭だけで考えずにアウトプットとして文字に起こす
●1人だけで振り返ろうとしない
振り返りの時間を確保するのが最も大事です。やりっぱなしでは経験学習とはいえません。あらかじめ、振り返る時間を予定に組み込みましょう。
また、文字でアウトプットするのも重要です。頭だけで考えていると、内容を忘れたり、もやもやしたりする可能性が高いです。客観的に見つめるためにも、書き出しましょう。
最後に、1人だけで実施しないというのも注意点です。他人の視点があったほうが圧倒的に効率が良く、自分では気付けない学びも得られます。経験に基づいたアウトプットを持って、上司や有識者と話しましょう。
経験学習サイクルを意識しよう

経験学習サイクルは「具体的経験」「内省的反省」「概念化・抽象化」「能動的実験」の4つに分かれます。
学びの多くは、経験から得られるでしょう。そのため、うまくいったこと・うまくいっていないこと、改善するための仮説などを文字に起こして言語化・可視化していくのが重要です。
大切なことや要点のメモ以外にも、文字に起こすと良質な振り返りができます。成長をサポートするツールとして、手帳の活用がおすすめです。
経験学習以外にもさまざまな用途で利用できる手帳をラインナップしております。ぜひNOLTYプランナーズにお問い合わせください。