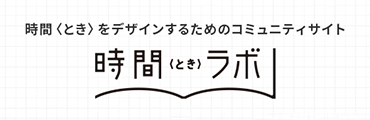鎌倉市としての学校教育に対する方針ついて教えて下さい。
現在、私たちは令和7年度の4月に向けた教育大綱を、市長や教育委員、先生方、そして子ども達とともに議論しています。その中で、「炭火」というキーワードが生まれました。この「炭火」という言葉は、子どもたちが内在するワクワク感を自分の中で育て上げ、生涯にわたって持続的に学び続ける姿を象徴しています。炭火がじわりと燃え続けるように、子どもたちの学びも生涯にわたって続いてほしいという思いが込められています。
炭に火をつけるためには、環境の巧妙さや高度な専門性が教育関係者に必要です。鎌倉市は「共生社会」というビジョンを掲げています。鎌倉で共に生き、共に学ぶ環境を整えていくことで、個人も社会もウェルビーイングな生き方を実現することが、私たちの究極的な目標です。
鎌倉市の教育現場において、どのような特徴や課題があるのでしょうか。特に重点を置いている方向性についてお聞かせください。
鎌倉市の子どもたちは、全国的な教育データと比較して、自己肯定感が高く、基本的な学習習慣や生活習慣が定着しており、発表や表現が得意な子どもたちが多いです。また、自然、文化、伝統といった地域資本の充実した環境も見逃せません。これらの要素を踏まえ、子どもたちを中心に据え、彼らの良いところをさらに伸ばしていけるような環境作りを目指しています。子どもたちには、「学びのハンドルを握る」つまり、自ら学びを掴み取り、主体的に取り組む姿勢を持ってほしいと考えています。
一方で、課題も存在します。全国的な傾向と同様に、鎌倉市でも不登校児童生徒の数が増加しています。また、教員の働き方に関しても、一律に勤務時間を短縮するだけの働きやすさ改革のみでは不十分で、多くの先生方が真に価値ある仕事に取り組むことができるようにするのが重要です。働きがいを向上させなければ、教員の確保もますます困難になっていくと思われます。さらに、教職員・児童生徒にはLTEでどこでもつながるiPadを用意しており、ネットワーク環境は整備されているものの、教員や教育委員会、学校間のデジタル連携に課題があると感じています。
こうした鎌倉市の教育現場の現状を踏まえ、「学習者中心の学び」、「ワクワクしながら未来を創る学び」、「地域の宝物を活かした豊かな学び」、「共生社会における自分らしい学び」という4つの重点的な方向性を導き出し、具体的な施策を考え進めております。
来年度から「学びの多様化学校」が新設されると伺いました。開校の経緯や意図についてお聞かせください。
令和7年度から「学びの多様化学校」として「鎌倉市立由比ガ浜中学校(仮称)」を新設する予定です。この学校の開校は4つの方向性、ビジョンの実現にすべて通じるものです。地域の宝を活かし、共生社会を実現し、学校に馴染めなかった子どもたちを包摂することを目指しています。 プログラムはワクワクを重視して組み立てられており、教科書から始まるのではなく、海や森などの自然から学ぶといったアプローチです。従来的な子どもたちが学校に合わせるという発想ではなく、「学校が子どもたちに合わせる」というコンセプトのもとで、子どもたちが主体的に学びを掴み取る環境を提供します。この学校は、地域とも共同しながら運営していく予定です。
先日行われた学校説明会では、保護者と子どもたち約250名が参加しました。運営スタッフは地域のフリースクールの方々や、このプログラムを共に作り上げた協力者の方々です。説明会の後、保護者と子どもたちに分かれて「どんな学校になると良いか」というテーマで意見交換を行いました。ファシリテーションも地域の方にお願いし、さまざまなぶっちゃけトークが繰り広げられる会となりました。教育委員会だけで作る学校ではなく、地域全体で作り上げていく学校にしたいと思っています。
また「学びの多様化学校」は、同様の課題を抱える子どもたちやその親同士、テーマに基づくコミュニティの形成を目指しています。親御さんのぶっちゃけトークでは、悩みや課題が共有され、共感や対話が生まれていました。心理的安全性のあるコミュニティの存在は非常に重要です。私たちは、生徒だけでなく、親のコミュニティ形成にも力を入れていきたいと考えています。
既存の学校では、ビジョンの実現のためにどのような取り組みを行っていく予定でしょうか。
もちろん、学習者中心の学びは「学びの多様化学校」だけで実現されるものではありません。学習者中心の学びにおいて最も重要なのは、子ども観を変えていくことです。「子どもたちは分かりやすく指示しないと動かない」といった考えを持っている大人がいます。しかし、元々子どもたちにはワクワク感を持っていて、学ぶ意欲が備わっています。子どもは一人ひとり違い、学び方にも得意・不得意があります。そうした個々の差異に寄り添い、子どもたちのポテンシャルを伸ばしてあげる発想が重要であると考えています。学びは本来、学び手のものであり、教えるものではなく、自ら掴み取っていくものです。先生方には、その環境をデザインする役割を担ってもらいたいと考えています。具体的には、子どもたちが学びのハンドルを握り、課題を設定し、それを深めて発表し、フィードバックを受けるというサイクルにおいて先生方が場のデザインやファシリテーションの役割を果たすような授業に転換していくことを目指しています。
先日拝見した中学校の理科の授業では、班ごとに分かれて計算問題を解いている班もあれば、実験をして仮説検証を行っている班や、植物の仕組みを深める活動をしている班がありました。授業の進行も子どもたちが中心となり、自ら深めたい単元を選び、それを深め、最後に対話をしてリフレクションする授業でした。先生は質問を受けてもさらに問いで返すなど、助言をしたり、取り残されている生徒がいないかを見たりしており、各生徒が頭をフル回転させて取り組んでいました。このような授業が唯一の正解ではありませんが、学習者中心を体現しているような教育活動だなと思われました。
新しい授業方法を積極的に取り入れる先生と、変化についていくのが難しい先生との間に生じる格差についてどのようにお考えですか
新しい学びをリードする「エバンジェリスト」のような先生がいます。彼らは理想郷とされる学びの転換島に既に到達し、率先して取り組んでいる先生方です。しかし、必ずしも全ての先生方がそこに到達すべきと考えているわけでもありません。飛び込んで泳ぎ始めた先生もいれば、船やいかだを作ってから向かおうとする先生、あるいはしばらく様子見の先生もいます。さまざまな立場の先生方が存在しますが、率先して変わろうとしている先生たちを止めることはしません。教育の世界では多様性が非常に重要です。見守っている先生や懐疑的に思っている先生も含め、すべての先生方の立ち位置に価値があると考えています。
「これが学びの転換だ」という唯一の正解はなく、一律に指示するリーダーシップも取っていません。むしろ、先生方と対話を重ね、各々の多様性を包摂しながら、共に目指すべき方向に目線を合わせ、ゆっくりと向かっていく伴走型のリーダーシップを鎌倉市教育委員会では目指しています。
先ほど、先生の働き方ではなく働きがいの改革が必要だとおっしゃっていました。具体的には、どのような取り組みをされていますか。
先生方の「腹落ち」がなければ、本当の働き方改革にはならないと考えています。先生方は価値ある仕事をしたいと思っています。鎌倉でも、部活動を指導したいと考える先生方が多くいらっしゃいます。しかし、部活動の地域移行が上からの指示で実行されると、先生たちのモチベーションが下がってしまうこともあります。価値ある仕事を増やし、意味がない仕事ややらされている仕事は極力減らしていく、先生方のアイデアを尊重し、彼らが納得しながら取り組める環境を作ることが重要だと考えています。教育委員会の役割としては、先生方と共に歩む「伴走」が大切だと思っています。
また、学びの転換こそが働きがいの改革に繋がると考えています。現在の教員不足やブラックな働き方を改善するためには、教育の質の向上と先生方へのリスペクトを守ることが欠かせません。そのためにも、学習者中心の学びを推進していくのだと思っています。これにより、先生たちの働きがいを高め、教育現場全体の質を向上させることを目指しています。
従来のトップダウンの管理型教育システムから、伴走型へと変革する必要があるとお考えですね。具体的にはどのような取り組みをされていますか。
従来のトップダウンの教育システムでは、文科省があり、県の教育委員会が採用を担当し、市の教育委員会がマネジメントし、校長、教員、子どもという形で指示が降りてくるピラミッド構造になっています。しかし、私は子どもたちが自ら学んでいくことを、先生方が支え、励まし、助ける。教育委員会は先生方を支え、励まし、助ける、あるいは十分な環境やリソースを整備する。このように子どもと学校が主役の逆三角形のモデルであるべきだと思っています。 先日教育センターで先生方による発表会がありましたが、単なる発表だけではなく、私がファシリテーションを行いながらパネルディスカッションや参加者同士の対話を実施しました。このディスカッションでは、「なぜ探究が必要なのか」、「鎌倉っ子はどんな子どもたちなのか」について対話を行いました。この対話を通して、先生方はとても話したがっているということを感じました。先生方の学びも主体的・対話的な深い学びにしていかない限り、教室内にも同じような学びが根付かないと考えています。子どもたちの学びと大人の学びには相似形があります。鎌倉に生きる大人たちも、生涯にわたってワクワクしながら、主体的に学び続ける環境を実現していきたいと思います。大人たちが学びの場で活躍し、炭火のように熱を持ちながら学び続ける姿を見せることで、子どもたちにもその価値が伝わっていくと考えています。
子どもたちにとっては火が付く前の火種をみつけることがいちばん難しいことかもしれません。その点も含め最後に、今後の展望について教えてください。
私は、何もやりたいことや好きなことがない子どもなどいないと思います。何か少しでも好きなものがあれば、そこからいくらでも学びを拡げ、深めることができます。また学びの多様化学校においても、様々な子どもたちが集まります。学校説明会に来た子どもたちの中には、じっと座っていられない子や別室で説明を受けた子、攻撃的な言動をとってしまう子もいました。教育というものは差分であり、進歩の一歩一歩を見つめることが重要です。一言も話せなかった子が、ワークショップの終わるころには他の人の意見に耳を傾け、良いと思ったことに花丸を書けるようになることも、一つの大きな成長です。これは、標準化の時代から個性化の時代へと移行している現代において特に重要です。学校はどうしても標準化を求めがちですが、私は子ども一人一人に合った学びやワクワクを、様々な方法で深掘りできるような環境を作っていきたいと考えています。そのためには、柔軟な教育体制と多様な学びの場を提供し、子どもたちが自らの学びを掴み取れる場をつくることが必要です。