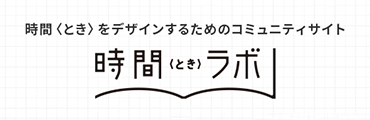葉山町としての学校教育に対する方針や取り組みについて教えて下さい。
まずはワクワクして楽しむという本来の学びを行いたいと思っています。葉山は海も山もあり、自然に溢れたところです。教員たちは小学生のころから子供たちを外に連れ出し、さまざまな経験させています。子供たちはそのような経験を通して、ワクワクして楽しむという学習の基礎や学びに対する好奇心が育成されるのだと思います。学習状況調査を見るとおもしろい結果が出ました。葉山の小学校の調査では、国語も算数もそんなに良い結果が出ているわけではありません。 ところが、中学校になると良くなります。アンケートを見ても、 小学生のときはあまり好きではなかった国語が中学校になると、好きになります。それはなぜか仮説を立ててみると、葉山の2つの中学校はインプットだけではなく、アウトプットの授業を多くしているからだと思いました。小学校の時に豊かな自然環境で学びに対するワクワク度を育て、中学校に行って、ロジックの部分もインプットしながら、アウトプットも同時に行うことで、学び自体が自然に好きになってくるのだと思います。好きになれば、自分で勉強するようになります。その結果がこの学習状況調査に出ているのだと思います。これからも、「もっともっとワクワクさせたい」というのが葉山の教育で目指しているところです。
来年度からは小中一貫校がスタートされますよね。どのような経緯で小中一貫校への転換を行っているのでしょうか。
まず子供たちの面から考えると、「中1ギャップ」という問題点があります。私服で毎日楽しくワイワイしていたのに、突然中学校に行くと制服を着ることになる。先輩後輩関係ができるなど、やはり型にはめられるというギャップを感じる生徒も多くいます。教員の面から考えると、 小学校の教員と中学校の教員との交流はほとんどありません。小学校の教員は中学校のことは知らないですし、その逆もしかり、中学校の教員は、生徒が小学校時代どのように過ごしていたか全く知りません。全ての学校を小中一貫校に全部する必要はないと思いますが、 同じ義務教育であるならば、小中が連携した教育を行うことに意義はあると思います。9年間の継続した学びをやっていくために仕組みを変えていこうと思ったことがきっかけです。
小中一貫校の実現に向けては、教員方の考え方や姿勢も変えていかないといけない部分も多くあるかと思います。
第一に、入学をした小学校の1年生の時から9年後はどういう子を育てたいのかということを 小学校の教員が理解していなければ継続性はないと思います。何ができるのか、何をするべきなのか、現場の教員に内在的に自分たちで考えてもらっています。フレームを作るのは教育委員会が担う部分もありますが、中身に関しては教員たち考えてほしいと思っています。
また小中の教員はあまり自由度が高くないように思います。 方向性が違うことをみんなでやりながら、全体としてのベクトルが変わってなければ本来何をやっても良いはずです。小学校や中学校の教員は、やはり学習指導要領に縛られていて、本当に自分たちがやりたい授業を展開できていなかったり、不自由な面もあったりするかと思います。小中一貫の葉山の教員たちには、本当に自分たちがやりたい授業をうまく 作っていってくれれば嬉しいです。子供たちが自由で本当にいい学びをしていくためには、教員たちが より良い楽しい学びを作っていける自由や余白がないといけないと思っています。
その自由度がもしかしたら働き方改革に繋がるのかもしれません。
その通りです。学校の一番忙しい時期は3月と4月初めです。校長には保護者に話してもらって3月と4月の一定の時期は給食後、生徒には下校してもらっています。3月は1年間をまとめ、翌年度のプランを立てる重要な時期です。ですが、今まではそこに十分な余裕を持った時間を取れていませんでした。 あっという間に始業式になって、入学式になって、すぐ授業をやらなければならない。教員たちにはしっかり準備をして、余裕を持って子供たち1人1人を見ていく時間がいつ取れているのだろという危機感がありました。余裕があるということは、1年間どうやっていくかもゆっくり考えられるし、 例えば新しいクラスになって、生徒の去年の様子をも含めて、自分でこの子をどう見るかなど考える時間もとることができます。まずは、そこをきちんと取ってあげることで、教員たちにとっては リラックスして、焦らずに準備に取り組めるようになると思います。
特に小学校の教員は朝から自分のクラスの全部の面倒を見なければいけません。そのような忙しい中では、研修の機会を持つことも難しくなります。教員にはそもそも研修が認められているので、一定の期間は研修させてあげるべきです。小中一貫校を作ってく中でも、 月に1回程度は小中同じ日に生徒を午後で下校させ、教員たちで どうやってより良い教育をしようかという小中一貫の打ち合わせをやっていきたいと思っています。
スクールミッション策定の経緯について教えてください。
※葉山のスクールミッション
https://www.town.hayama.lg.jp/material/files/group/22/school_mission1.pdf
葉山の教育はこうあるべきだというのを校長や教員たちと相談して、スクールミッションを作りました。ミッションが1つの軸になって、各校がスクールポリシーを作っています。各学校の校長、教員がこういう子たちを9年間で育てていきましょうという軸を作っています。今までは学校によってバラバラでしたが、教員は転勤をするので、 転勤してきた時に葉山の教育としての軸がないと、経験則で勝手なことをやる人もいます。葉山に転勤してきたら、葉山で葉山の教育し、小中一貫で貫く考え方をしっかり持ってもらいたいと思っています。
その他何か働き方改革に関することで取り組まれていることはありますか。
長柄小学校では教科担任制を低学年でも取り入れ始めました。小学校では担任のクラスとそれ以外のクラスとの連携の弱さが課題でした。例えば隣のクラスで学級崩壊が起きても、隣の教員がかかわることをあまりしていませんでした。教科担任制であれば、クラス横断をするので 隣のクラスの面倒も見ることになります。また教科の専門性も授業力も上がりますし、複数科目準備する必要もなくなるので働き方にも余裕が生まれるはずです。
わたしは義務教育の教員たちはもっと自由にすればいいと思っています。本当の意味で教員としてやるべきことをやるために選択と集中をどうするのかということを考えていきたいと思っています。
教育現場では生成AIの登場を含め、大きな変化が起きています。何か取り組まれていることや今後の教育の在り方について考えていることはありますか。
どう使っていくかっていうのはやはりすごく重要なことで、触らないのはダメだと思っています。実際、読書感想文などは、生成AIを使って質問を投げかけると、30秒でそれなりのレベルのものを作ってしまいます。生成AIが作った作文をそのまま校長や教員たちにもよく見せていますが、「それではここからどうしますか」というのを教員が考えられるかどうかが重要です。生成AIに、何を求めて何をさせるかというオーダーをかけるのは人間です。また、アウトプットされたものにエッセンスを加えながら、様々なことをするのは人間のやることです。 ですので、教員があらかじめその点を理解し、授業の中でどのようなことができるのかということを考えていくべき時代だというのは、よく話していることです。
かつては、今後生きていくために 人間に必要なのは、共通言語としての英語とプログラミング言語の2つだと言われていた時期もありました。ところがプログラミングも英語も生成AIがあれば一定の水準まではできてしまいます。となると、やはりそれをどう活用させるか、一歩先に進むには人間の判断力や工夫が必要です。これから先はその一歩先をどう進めるかを考えていく必要があると思います。これまでは主要5教科がすごく重要視されてきましたが、STEAM教育のArtの部分だけでなく実技科目がより重要になってきます。子供たちに学んでほしい中心核を、本当の意味でのクリエイティブなものに軸を移していきたいと考えています。