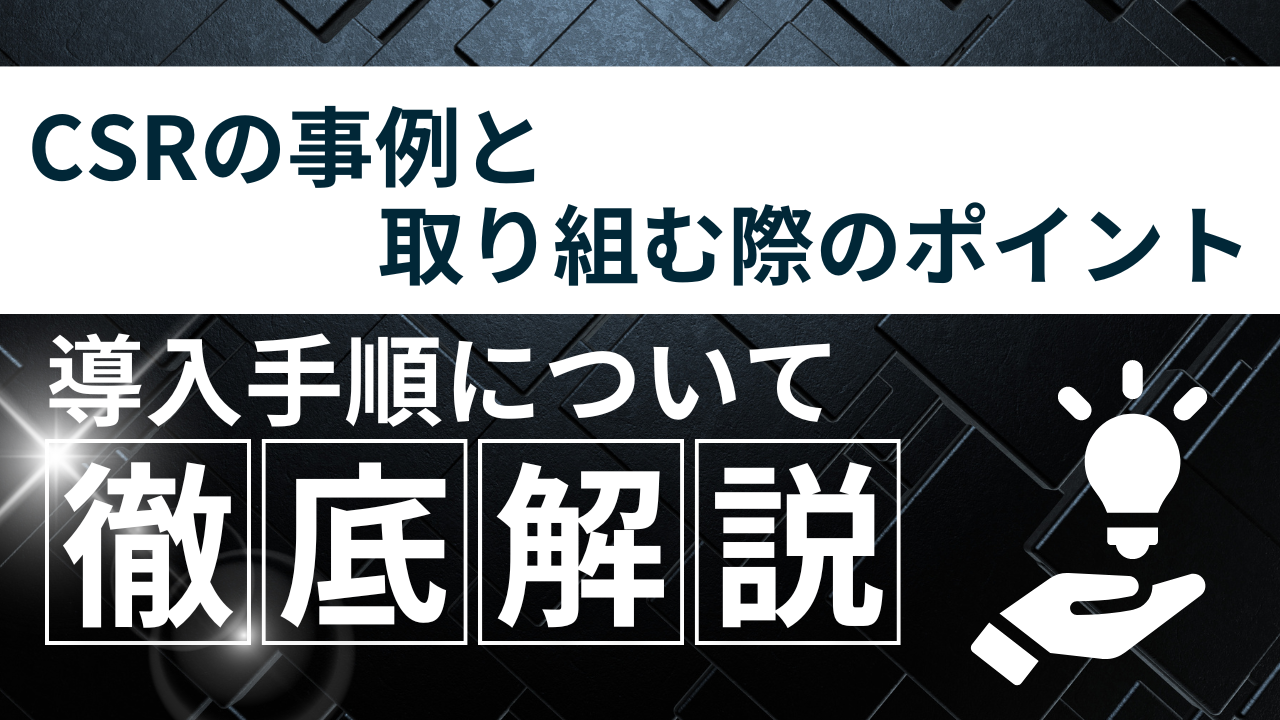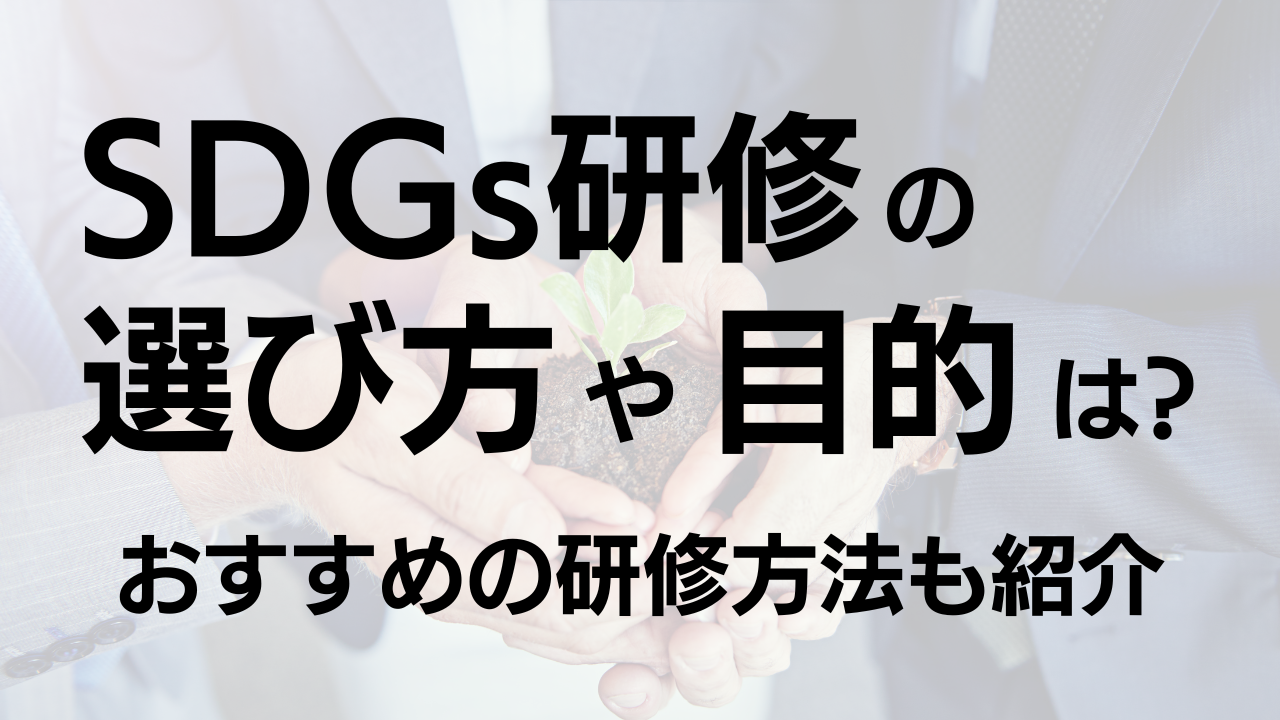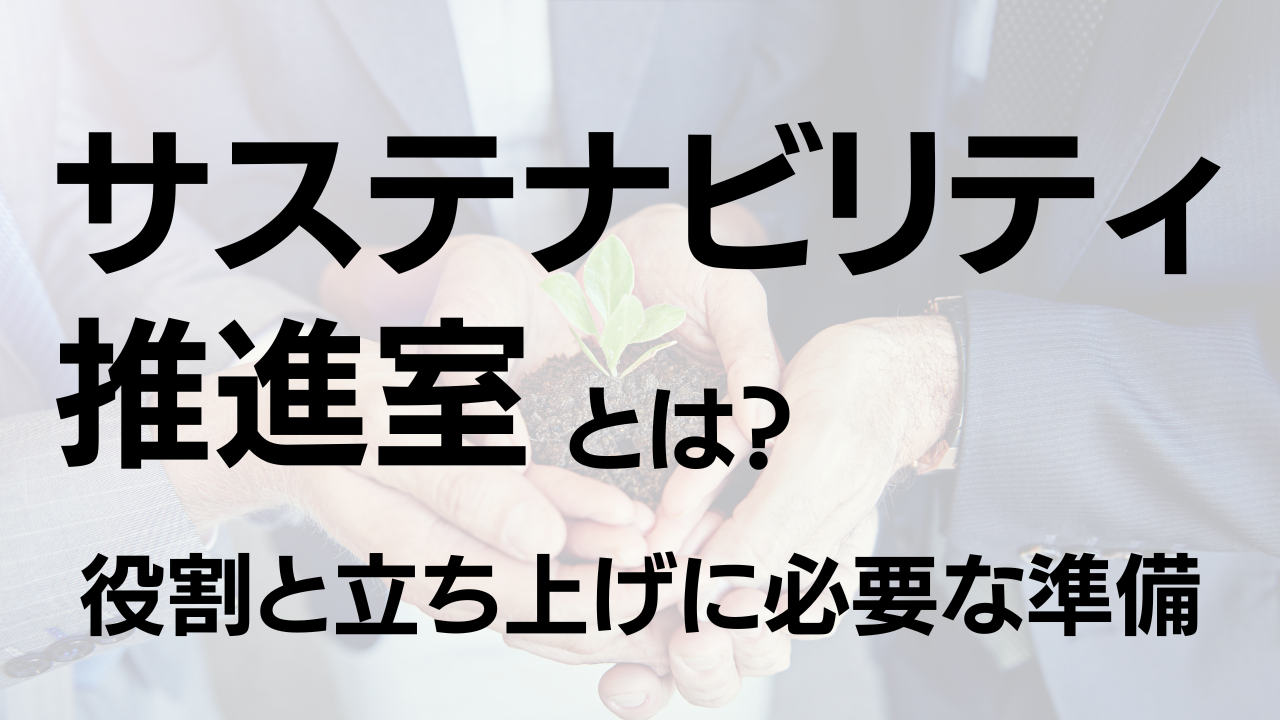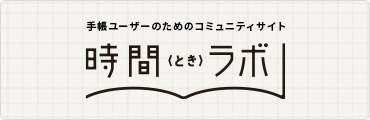「ソーシャルイノベーション」という言葉を耳にしたものの、その意味や具体的な例がよくわからない方は意外と多いです。
この記事では、ソーシャルイノベーションの意味や具体例・課題について詳しく解説します。ソーシャルイノベーションに取り組もうと検討している方に必見の内容です。ぜひ参考にしてください。
目次
ソーシャルイノベーションとは

ソーシャルイノベーション(Social Innovation)とは、目的・手段ともに社会的で革新的な事業を指します。これは、既存のやり方や常識などの価値観を変革する事業です。ソーシャルイノベーションで起業した方は、社会起業家と呼ばれます。
ソーシャルイノベーションは、一時的な革新で終わるのではなく、持続可能であることが求められます。地方や業界の一部から変革を起こして、周囲に広まっていく場合が多いのが特徴です。また、多くのステークホルダー(関係者)と手を組んで効果を発揮しているシーンが見られます。
ソーシャルイノベーションが求められている理由・背景

ソーシャルイノベーションが求められている背景は、大きく3つあります。
●社会問題の複雑化と既存の制度の限界
●SDGsや環境問題への関心の高まり
●テクノロジーの進歩と普及
現在、世界や日本では、貧困や格差、教育や医療、人種差別など、あらゆる分野の問題を抱えています。立場がさまざまで、既存の社会構造では対応しきれなくなっており、簡単に解決できるものはほとんどない、という現状があります。
法律や条例などの制度も、問題が起き始めて数年経ってから対応するケースが多く、最悪の場合は、是正もされません。
また、SDGsや環境問題に対して、人々の関心が高まっているのも背景の一つです。例えば、自動車・火力発電などの便利なツールを利用する際に、環境を犠牲にしている側面があり、それを解決する方法が求められています。
さらに、テクノロジーの進歩や普及も、大きな影響をもたらしました。オープンソースで無料で使えるソフトの登場や、デジタルプラットフォームが整備されたことで、ソーシャルイノベーションを起こしたあとに広まりやすくなりました。
特にX(旧Twitter)やInstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)の影響が強いといえます。ITツールが増え、それらを活用して社会課題を解決することが求められています。
ソーシャルイノベーションの具体例

ここでは、ソーシャルイノベーションの実例を3つ紹介します。
●Wikipedia(ウィキペディア)
●KUMON学習療法センター
●ウシャヒディ
ソーシャルイノベーションとはどのようなものか、具体的にイメージしやすく解説します。
Wikipedia(ウィキペディア)
Wikipediaは、一部の専門家によるプロジェクトとして2001年に始まりました。今では、Web上で辞書代わりに使えるサイトとして広く認知されています。
寄付やボランティアで運営されており、ユーザー兼編集者の方々の議論が行われるため、一定の品質が保たれている点が特徴です。
今ではGoogle検索でさまざまな情報にアクセスできます。しかし、Wikipediaは、インターネット黎明期に辞書を引く代わりにサイトで検索するという行動を一変させました。
人々の行動を改革をしたソーシャルイノベーションとしてふさわしい一例です。
KUMON学習療法センター
KUMON学習療法センターでは、認知症の改善や予防を目的とした学習療法に取り組んでいます。子どもの塾として有名な「公文式」をベースとして、認知症を予防する方法です。
デイサービスや有料老人ホーム、介護現場などと協業して実施しており、現在では、日本全国で多くの設備はもちろん、アメリカでも導入されています。
簡単な計算・音読などの学習で、脳全体を活性化させる効果があると東北大学の川島教授が提唱しています。子ども向けの教育プログラムをデイサービス・有料老人ホームで活用する点がイノベーションといえるでしょう。
ウシャヒディ
ウシャヒディは、スワヒリ語で「証言」を意味する、2008年にケニアで作られたクラウドソーシングツールです。誰でも無料で利用でき、当初は暴動の情報をGoogleマップ上に表示して市民に周知するために開発されました。
日本では、東日本大震災が起きた際に、ウシャヒディを活用した「sinsai.info」というサイトが一部で有名になりました。被害や復興関連情報を集めるサイトで、震災後4時間で立ち上げられました。※現在はアクセスできません
クラウドソーシングは、Web上で不特定多数の方に業務を依頼する仕組みで、それ自体がソーシャルイノベーションの一つといえます。
ウシャヒディは、社会的・政治的な課題に取り組む個人や組織を支援するツールとして広く認知されています。
ソーシャルイノベーションで直面する3つの課題

ソーシャルイノベーションは便利ですが、課題もあります。大きくは以下の3つです。
1.資金や人材確保が難しい
2.基準が定めにくく効果測定が困難
3.既存のルールや利害関係の調整が厳しい
ソーシャルイノベーションを深く知るために、それぞれの課題についても詳しく確認しましょう。
1.資金や人材確保が難しい
ソーシャルイノベーションの一番の課題は、資金調達が難しい点です。
まだ誰もやったことがない取り組みで、投資家や企業の理解を得にくいため、資金を集めにくいという壁があります。
さらに、人材の確保も問題になりやすいでしょう。資金調達が難しい点から、支払える報酬が低くなるケースが多く、人材を引きつけにくいといえます。また、ボランティアで成り立っている場合もありますが、ボランティアでは限界があり、人材の定着や引き継ぎが大変になる可能性がある点は認識しておきましょう。
2.基準が定めにくく効果測定が困難
ソーシャルイノベーションには、効果測定が難しく成果を数値で表すのが困難という課題もあります。
前例がないため、数値目標を設定するのが難しく、どのくらい普及するのか、役に立つのかなどを可視化するのが困難です。そのため、資金調達で投資家に支援してもらいにくい傾向にあります。
また、数値で示せないと賛同を得られるまでに時間がかかる場合があります。ソーシャルイノベーションでは、納得感のある数値基準や目標設定が難しい点を理解しておきましょう。
3.既存のルールや利害関係の調整が厳しい
ソーシャルイノベーションは、ルールや関係者についても大きな壁があります。前例がない取り組みが多く、法律や条例で制限を受ける可能性があります。
また、革新的で社会を変える力がある取り組みが多いため、多くの利害関係者が出てきます。うまく手を組めればよいですが、行動を阻もうとする方も出てくるでしょう。
ソーシャルイノベーションは、ルールの変更や信頼関係の構築に時間がかかります。すぐに変革するのは厳しい可能性があるため、腰を据える覚悟を持って取り組みましょう。
ソーシャルイノベーションをビジネスに取り入れよう

ソーシャルイノベーションは、社会的な課題を革新的なアイディアで解決するのに役立ちます。
ビジネスでソーシャルイノベーションを取り入れる(推進していく)際には、社員が社会課題に興味・関心を持つ(育成や教育する)ことが大切です。
そのためには、社内で掲げているSDGsやサステナビリティの目標を改めて腹落ちさせていくこと、そこから自部門で目標達成に近づくために新たな考えや視点を得るための施策をご検討してみるとよいでしょう。