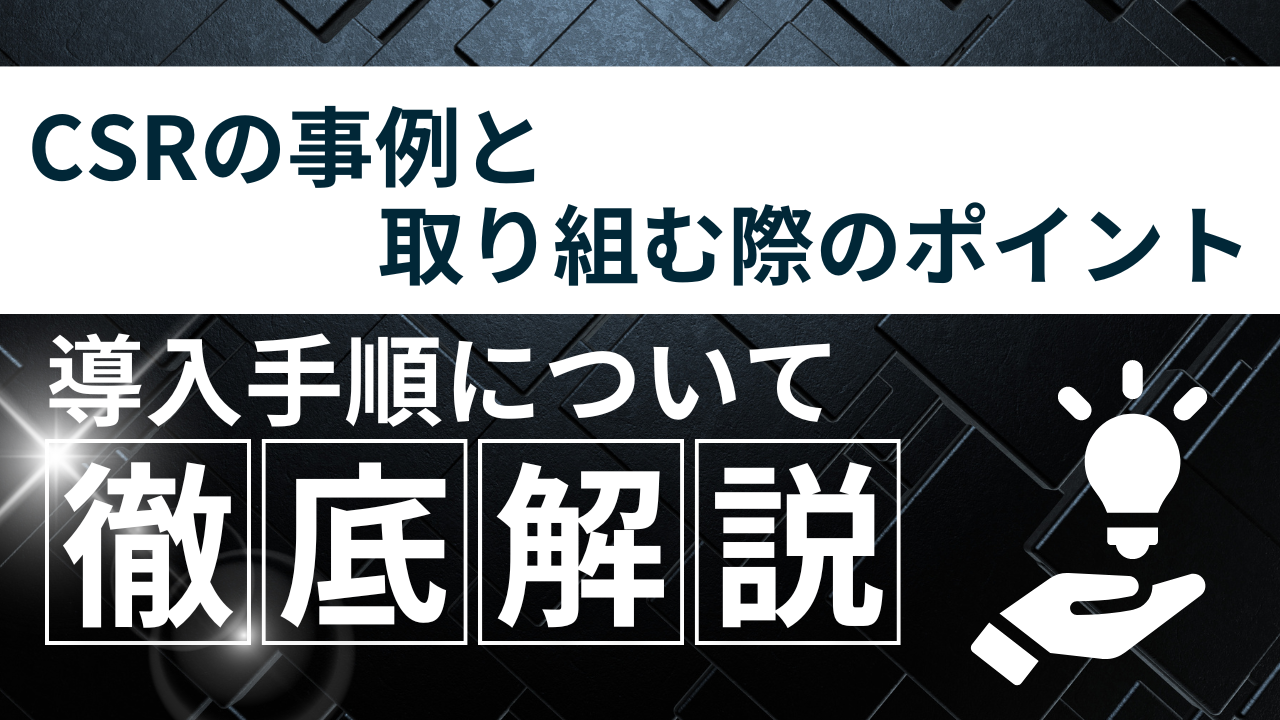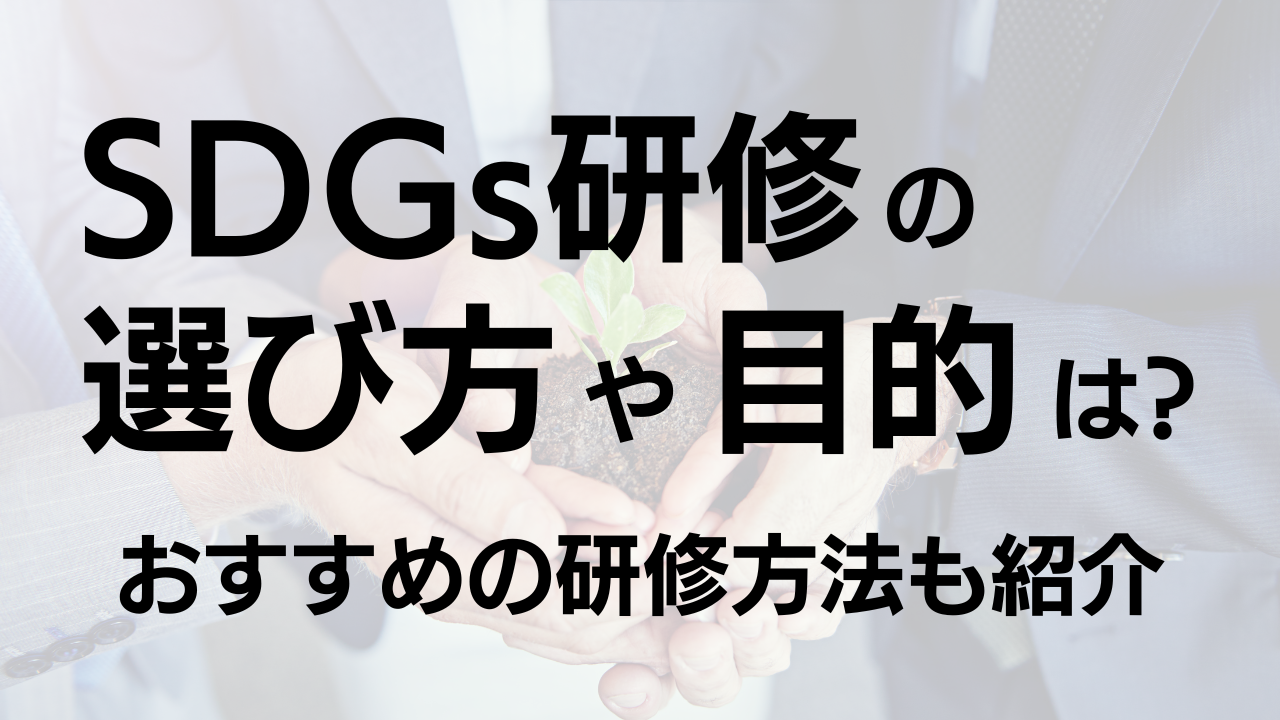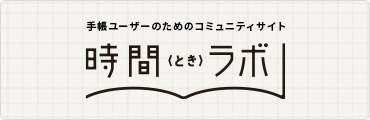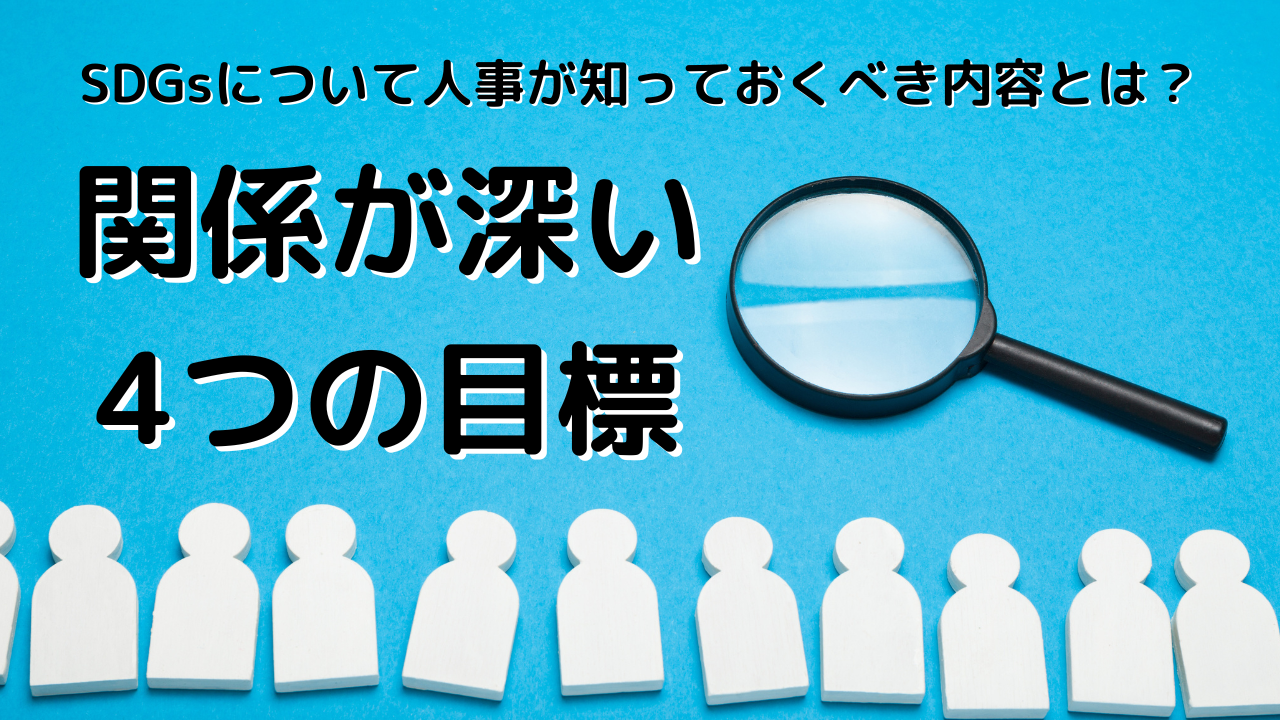
人事業務とSDGsは、一見あまり関係がないように思えます。
しかし、SDGsには人事に関係する目標も多くあり、人事の面からSDGsに注目することも重要なのです。
しかし、どのようなことに取り組めばいいのか、疑問に感じている方も多いでしょう。
そこで本記事では、SDGsと人事の関係や、具体的な取り組みの例をご紹介します。
人事がSDGsに取り組むメリットや、注意すべきポイントも解説していますのでぜひご覧ください。
目次
SDGsと人事の関係

SDGsとは持続可能な開発目標のことです。
従来のように、エネルギーや資源を豊富に使ってよりよい社会を目指すのではなく、持続可能な方法を取りながら、さまざまな面で環境を向上させていく取り組みです。
SDGsは、17の目標と169のターゲットで構成されています。
SDGsというと、環境問題やエネルギー資源などの問題を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は人や労働に関係する目標も多くあるのです。
企業としてSDGsに取り組むなら、ぜひ人事の面からもSDGsに注目してください。
人事と関係が深いSDGsの目標4つ

人事と関係が深いSDGsの目標は次の4つです。
・目標3:すべての人に健康と福祉を
・目標5:ジェンダー平等を実現しよう
・目標8:働きがいも経済成長も
・目標10:人や国の不平等をなくそう
各項目について、詳しく解説します。
目標3:すべての人に健康と福祉を
目標3「すべての人に健康と福祉を」は、世界中の方が適切な医療を利用でき、事故や病気が発生しにくい環境を目指すものです。
世界では、病気になっても適切な医療にアクセスできないため、子どもの死亡率が高い地域があります。
日本では、自殺率の高さや介護難民の発生、医師の偏在が問題とされています。
企業で目標3に取り組む際には、労働環境の整備や健康経営の実践が重要です。
具体的には、次のような取り組みが考えられます。
・定期的な健康診断の実施・推奨
・ストレスチェックの実施
目標5:ジェンダー平等を実現しよう
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、男女平等を実現し、特に女性に対する不利な扱いや搾取・暴力をなくすことを目指すものです。
世界では、現在でも児童婚問題が解消されていません。
また、学校にいけない女の子の数は男の子より多いのが現状です。
日本では、男女の所得格差や、家事育児負担の男女の偏りが課題とされています。
企業では、女性活躍の推進を行うとともに、男女ともに家事や育児など家庭での役割を果たせるような労働環境の整備が必要です。
具体的には、次のような取り組みが考えられます。
・在宅・時短勤務・看護休暇制度の拡充
・育休を含む長期休暇前後のフォロー体制の整備
ジェンダー平等を考える際には、男性・女性だけでなくLGBTQ+の方に向けた配慮も必要です。
目標8:働きがいも経済成長も
目標8「働きがいも経済成長も」は、すべての方が人間らしい働き方をしながら、同時に経済成長を目指すものです。
世界では、失業率の高さや、児童労働が問題となっています。日本では、長時間労働や雇用形態による賃金格差が課題です。
目標8への取り組みとして企業でできることには、次のような例があります。
・障害者雇用の推進
・長時間労働を避けられるような人員の確保
また、タレントマネジメントの実施も有効です。
タレントマネジメントとは、従業員が持つ才能や資質を採用や育成に活用することをいいます。
タレントマネジメントを行うと、従業員は自分の得意を活かして働けるようになり、生産性の向上も期待できます。
働きがいと経済成長を両立させるために、効果的な方法といえるでしょう。
目標10:人や国の不平等をなくそう
目標10「人や国の不平等をなくそう」は、人種や民族、宗教、性別、障害の有無、性的指向などに基づいた不利益や差別をなくすことを目指すものです。
世界では、所得格差やさまざまな理由による差別が問題となっています。
日本では、子どもや高齢者の相対的貧困や、ジェンダーの不平等が課題です。
目標10への取り組みとして企業でできることの例は次の通りです。
・差別的な慣行の洗い出しと撤廃
・同一労働同一賃金の実施
差別のない働き方を実現するためには、人事を中心に企業全体での取り組みが重要です。
人事がSDGsに取り組むメリット

人事がSDGsに取り組むメリットは次の3つです。
・企業イメージの向上
・従業員のモチベーションアップ
・従業員の定着率が高まる
それぞれ、詳しく解説します。
企業イメージの向上
SDGsへの取り組みは、企業イメージの向上につながります。
特に、Z世代と呼ばれる若者世代はSDGsに対する意識が高く、7割がSDGsに取り組む企業に対して好印象を抱いています。
また、SDGsに取り組んでいるか否かは、就職の志望度にも関連があるとの声も多いです。
参考:PR Times「Z世代のSDGsと消費に関する意識調査」
上記でも紹介した通り、SDGsへの取り組みは従業員の働きやすさやにもつながります。
「SDGsに積極的に取り組む企業=働きやすい企業」の認識が一般的になれば、SDGsに取り組んでいないと就職希望先の選択肢から除外され、採用活動が困難になる可能性もあります。
従業員のモチベーションアップ
SDGsに取り組み働きやすさがアップすると、従業員のモチベーションが高まります。
また、SDGsに積極的に取り組む企業での仕事は、社会貢献にもつながるためやりがいが生まれやすくなります。
従業員のモチベーションが高まれば、さらなる業務効率のアップも期待できるでしょう。
従業員の定着率が高まる
SDGsに取り組み働きやすい職場環境を用意すると、従業員の離職率を下げられる可能性が高いです。
離職率が下がると、採用活動に必要な費用や時間的コストを減らせます。
定着率が高まることで、新人の育成に必要な時間も減らせます。
その分、より高度なスキルを身につけてもらうための人材育成や、各従業員のパフォーマンス最適化などの取り組みにリソースを割けるようになるでしょう。
人事がSDGsに取り組む際の注意点

人事がSDGsに取り組む際には、次の4つのポイントに注意する必要があります。
・SDGsの方向性と経営方針を一致させる
・長期的な視点で取り組む
・従業員への負担が増えないよう注意する
・SDGsウォッシュを回避する
それぞれ注意すべき理由や、詳しい内容を解説します。
SDGsの方向性と経営方針を一致させる
SDGsへの取り組みを行う際には、取り組みの方向性と経営方針を一致させなければなりません。
経営方針と一致しない方向性の取り組みは、ムダが多く効率が悪くなります。
例えば「子どもを幸せにできる商品やサービスを提供する」という方針であれば、子どもがいる社員が働きやすいような環境を整える取り組みから始めるとよいでしょう。
長期的な視点で取り組む
SDGsは、2030年に向けた取り組みです。
そのため、目先の問題に惑わされるのではなく、長期的に取り組む必要があります。
例えば看護休暇制度の拡充を行う場合、すぐに制度を作ればよいとは限りません。
看護休暇制度を利用して休む従業員がいた場合でも、問題が起きないような環境を整えてから、休暇制度を取り入れる必要があります。
慌てずに、将来的によりよい職場環境を作れるような取り組みが必要です。
従業員への負担が増えないよう注意する
SDGsへの取り組みの中には、従業員への負担が増えてしまうようなものもあります。
例えば、女性管理職が少ないからと、女性向けの管理職育成プログラムなどを用意した場合を考えてみましょう。
労働時間内にプログラムを受けなければならない場合、仕事が減らなければその分残業をする必要があります。
プログラムを受ける女性の仕事を減らすために、従来持っていた仕事を別の人に振り分けようとしても、他の社員も自分の仕事を抱えているため、結局負担が増えることに変わりはありません。
SDGsへの取り組みのために負担が増えると、従業員のモチベーションが下がってしまいます。
まずは、負担を増やさずできることから少しずつ取り組みを実施してみましょう。
SDGsウォッシュを回避する
SDGsウォッシュとは、名目上はSDGsへの取り組みを謳いながら、実態が伴わない状態のことを指します。
例えば、従業員の長時間労働を減らす取り組みをアピールしながら、児童労働が行われているような現場から原材料を購入しているような場合には、SDGsウォッシュを指摘される可能性があるでしょう。
SDGsウォッシュと指摘されてしまうと、企業のイメージダウンは避けられません。
SNSでの炎上により、大きなダメージを受ける可能性もあります。
SDGsウォッシュを回避するためには、SDGsに取り組むことだけを目的とせず、本来世界はどうあるのが理想的かを考える必要があります。
また、SDGsへの取り組みを発表する前には、自社で取り組んだSDGsに矛盾するような取引などが行われていないかを、必ず確認しておきましょう。
人事でもSDGsに取り組もう

人事はSDGsにあまり関係がない職種と考えられることが多いですが、実はSDGsと関係が深い項目も多く存在するのです。
日本の職場環境にも、未だに改善すべきポイントは多くあります。
どのような点を改善すべきか、すぐに改善できることはないか、人事の視点から考えてみてください。
人事でSDGsに取り組む際には、本記事を参考にしていただければ幸いです。
▼NOLTYプランナーズでは、インナーコミュニケーションとサステナブル転換の両立を実現するSDGsサポートプログラムを提供しています。
詳しくは、下記のバナーからご覧ください!