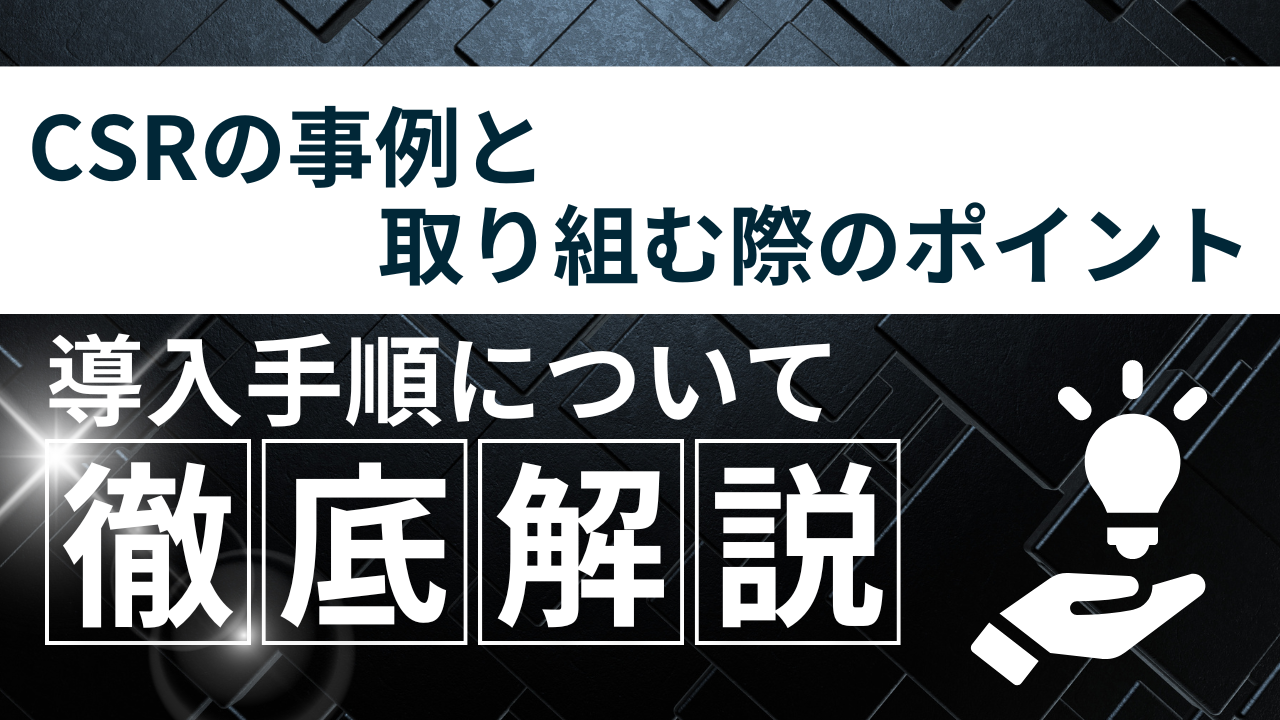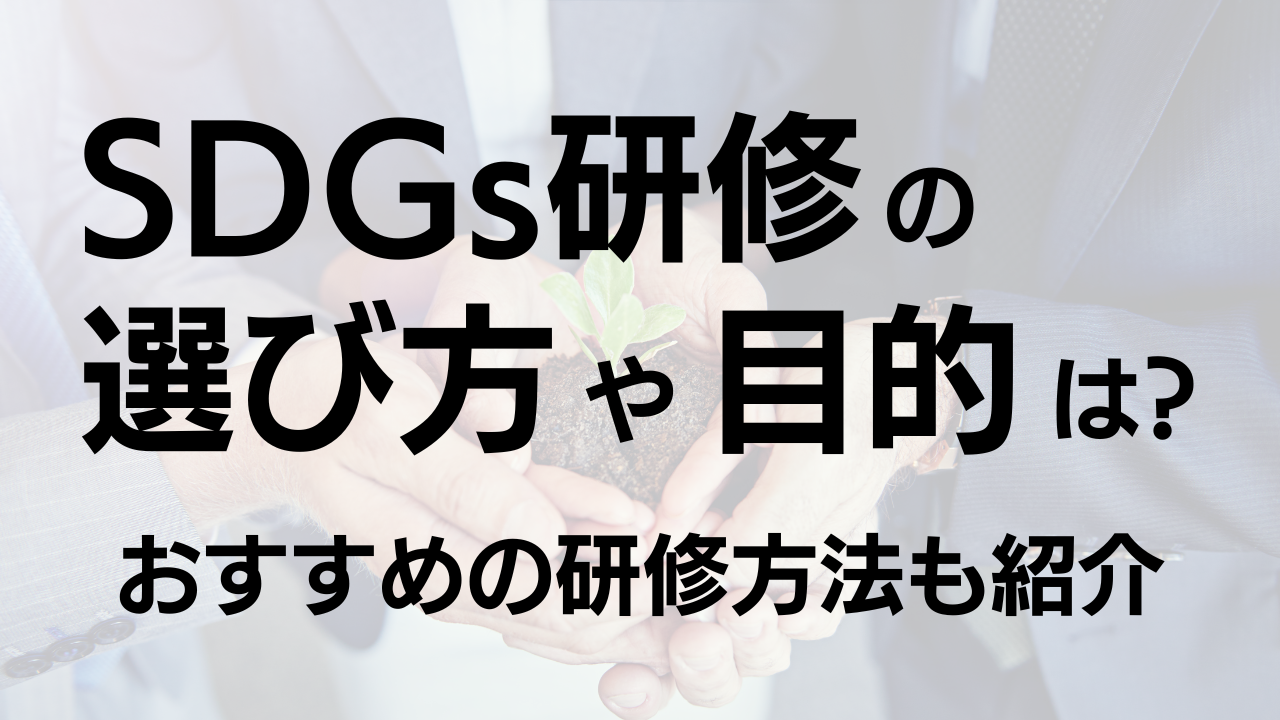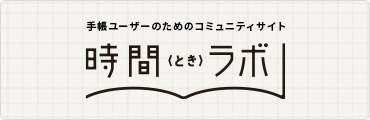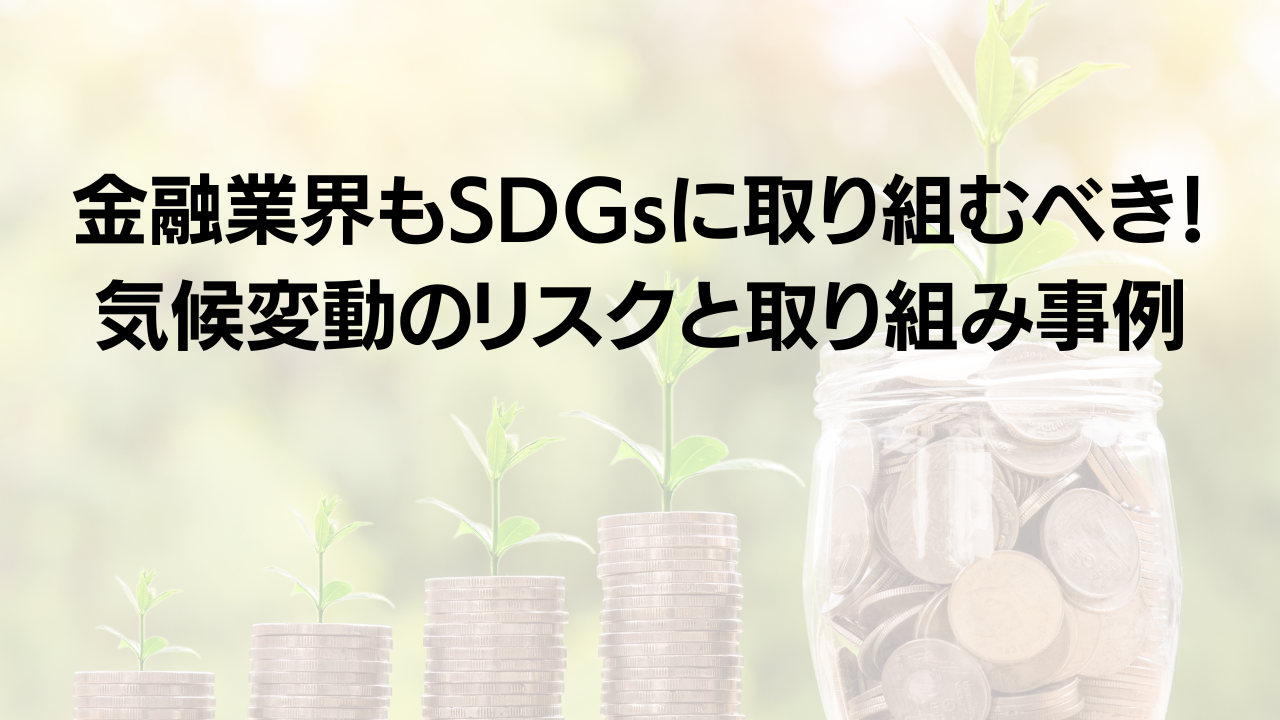
金融業界は、SDGsとの関係が薄い業界だと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、金融業界でも多くの企業がSDGsに対する取り組みを行っています。
実は、金融業界は気候変動による多くのリスクを抱える業界でもあることをご存じでしょうか。
この記事では、金融業界とSDGsとの関係や、気候変動によるリスク、さらに具体的な取り組み事例を紹介します。
金融業界とSDGsの関係があまりよくわからないという方は、ぜひご覧ください。
目次
金融業界とSDGsの関係

金融業界とSDGsの関係について、すぐにピンと来ない方も多いかもしれません。
実は、金融業界でも持続可能な経営のためにSDGsは重要だと考えられています。
金融業界がSDGsを重要視する理由のひとつが、社会インフラを担う責任を果たす立場であるためです。
SDGsは、国連に加盟するすべての国が取り組むべき共通目標とされており、当然その中で経済活動を行っている金融業界も無関係ではいられません。
社会全体が持続可能にならなければ、金融業界の業務も持続できないためです。
金融業界で特に積極的に取り入れられている活動が、ESG投資です。
ESG投資は、従来の投資指標に加えて、「環境」「社会」「企業統治」への配慮を重視して投資を行う手法のことを指します。
上記に配慮している企業への投資を行うことで、環境や社会、企業統治に配慮した経済活動を行っている企業を支援できます。
また、SDGsに取り組んでいる企業、ということで自社のイメージアップにもつながります。
このように、金融業界でも積極的なSDGsへの取り組みが行われているのです。
気候変動が金融業界に与えるリスク

SDGsの中には「気候変動に具体的な対策を」という目標があります。
気候変動は、金融業界にも次のようなリスクを与えることが懸念されています。
・物理的リスク
・賠償責任リスク
・移行リスク
それぞれのリスクの内容については以下の項目で詳しく解説しますが、こうしたリスクを抑えるためにも、金融業界も他の業界と同様に積極的にSDGsに取り組むことが必要です。
物理的リスク
物理的リスクとは、気候変動が直接的に担保資産などに与える影響のことです。
担保資産とは、万が一融資を返済できなくなった場合の返済を保証するものです。
融資を返済できなくなった場合には、担保資産を売却することで返済の代わりとします。
担保資産には土地や建物などの不動産が使われることが多いのですが、気候変動によってそうした担保資産が被害を受ける可能性があります。
担保資産が被害を受け、さらに融資が返済されない場合、融資を行った金融機関は、資金を回収できません。
また、自社が保有している物件が、気候変動によって被害を受ける可能性もあります。これが「物理的リスク」です。
賠償責任リスク
賠償責任リスクとは、気候変動によって何らかの損失を被った方が、自分自身以外の他者に責任があるとすることで、損失を回避しようとするリスクのことです。
例えばアメリカでは、送電線が樹木に接触するなどして山火事を引き起こし、電力会社が経営破綻した例があります。
しかし、外気温が異常な高温になっていることや、それによって樹木の水分量が少なくなっていたことなども、大規模な山火事が起きた背景だとされています。
気候変動によって、災害が起きやすくなっているのです。
このように、従来と環境が変わって災害が引き起こされやすくなることで、賠償責任を負うリスクが増大します。
金融業界の企業であれば、こうした災害で保険請求が増加する可能性も認識しておかなければなりません。
移行リスク
低炭素社会への移行に伴って、資産価値が再評価されることで発生するリスクもあります。
例えば、低炭素社会を目指すために政府が電気自動車の普及に力を入れた場合、ガソリン車の製造に使っていた施設は資産価値が大幅に減少してしまう可能性があります。
また、研究が進んで何らかの物質が環境に悪影響を与えるとわかった場合、それを扱っている企業は大きなダメージを受けるでしょう。
これらのようなリスクを、移行リスクと呼びます。
金融業界のSDGsへの取り組み事例

金融業界でも、SDGsに対するさまざまな取り組みを行っています。
取り組みの具体例としては、次のようなものが挙げられます。
・ESG投資信託
・寄付型私募債
・グリーンボンド
・サステナビリティ・リンク・ローン
・SDGs宣言支援サービス
それぞれ、詳しく解説します。
ESG投資信託
ESG投資信託とは、ESG投資となる金融商品を集めた投資信託のことです。
ESG投資とは、先にも紹介したとおり「環境」「社会」「企業統治」に力を入れている企業に投資する手法のことです。
日本ではまだまだESG投資の割合が小さいこともあり、これからの伸びが期待されています。
寄付型私募債
寄付型私募債とは、銀行が企業から受け取る手数料の一部を、自治体などに寄付する方法のことです。
たとえば、横浜銀行の「SDGs動物愛護私募債」では、顧客が私募債を発行したことの記念として、神奈川県内の主に動物愛護センターを設置する自治体に対して、横浜銀行が発行金額の0.1%を寄付します。
私募債とは、企業向けの資金調達手段のひとつで、少数の投資家が直接引き受ける社債のことです。
つまり、資金を調達したいときに寄付型私募債の方法を選べば、さまざまなSDGsに貢献しながら資金調達活動を行えます。
グリーンボンド
グリーンボンドとは、企業や地方自治体などが、環境改善活動などのための資金調達を目的として発行する債券のことです。
調達した資金の使途が限定されていることが特徴で、調達資金が確実に追跡管理されることに加え、事後のレポートで透明性が確保されます。
投資を行うのは機関投資家や運用機関、個人投資家などさまざまで、ESG投資における投資先のひとつとして注目されています。
サステナビリティ・リンク・ローン
サステナビリティ・リンク・ローンとは、借り手のESG戦略と整合した取り組み目標の達成度合いによって、インセンティブが発生するローンのことです。
SDGsに対する取り組みで結果を出すほど、金利が優遇されるといった有利な状況を獲得できるローンとも言えます。
借り手としては、SDGsへの取り組みをより一層強化しながら資金調達をできる点がメリットです。
一方、貸し手側としては、融資を通じて利益を得ながら社会に貢献できる点がメリットとなります。
SDGs宣言支援サービス
SDGsに取り組んでいることを社内外に発信する仕組みのひとつとして「SDGs宣言書」があります。
SDGs宣言書の発行によって、取り組みについて多くの方に知ってもらえるとともに、ブランドイメージのアップにもつながります。
しかし、初めてSDGs宣言書を作成する際には、どのように作成したら良いかわからないこともあるでしょう。
また、書き方によってアピールの効果に差が出る場合もあります。
金融業界には、SDGs宣言書の作成支援を行っている企業が多く存在し、SDGsへの取り組みを始めようとする企業をサポートしているのです。
金融業界のSDGsに対する取り組みはさまざま

金融業界では、SDGsに対するさまざまな取り組みを行っています。
金融業界がSDGsに取り組むのは、社会的な責任を果たすためでもあり、自分たちのリスクを減らすためでもあります。
この記事を参考に、まずは金融業界で行われているSDGsへの取り組みについて、知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
▼NOLTYプランナーズでは企業のSDGs事業のサポートプログラムを提供しています。
詳しくは、下記のバナーからご覧ください!