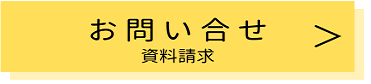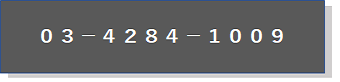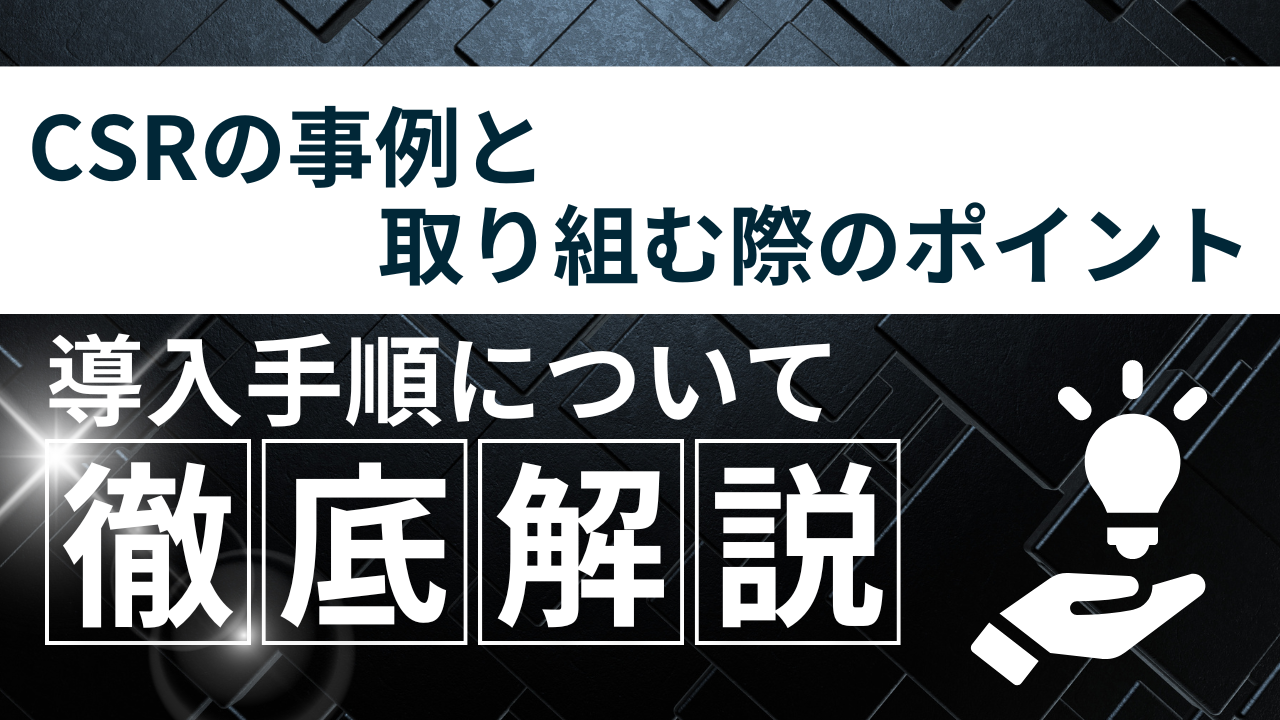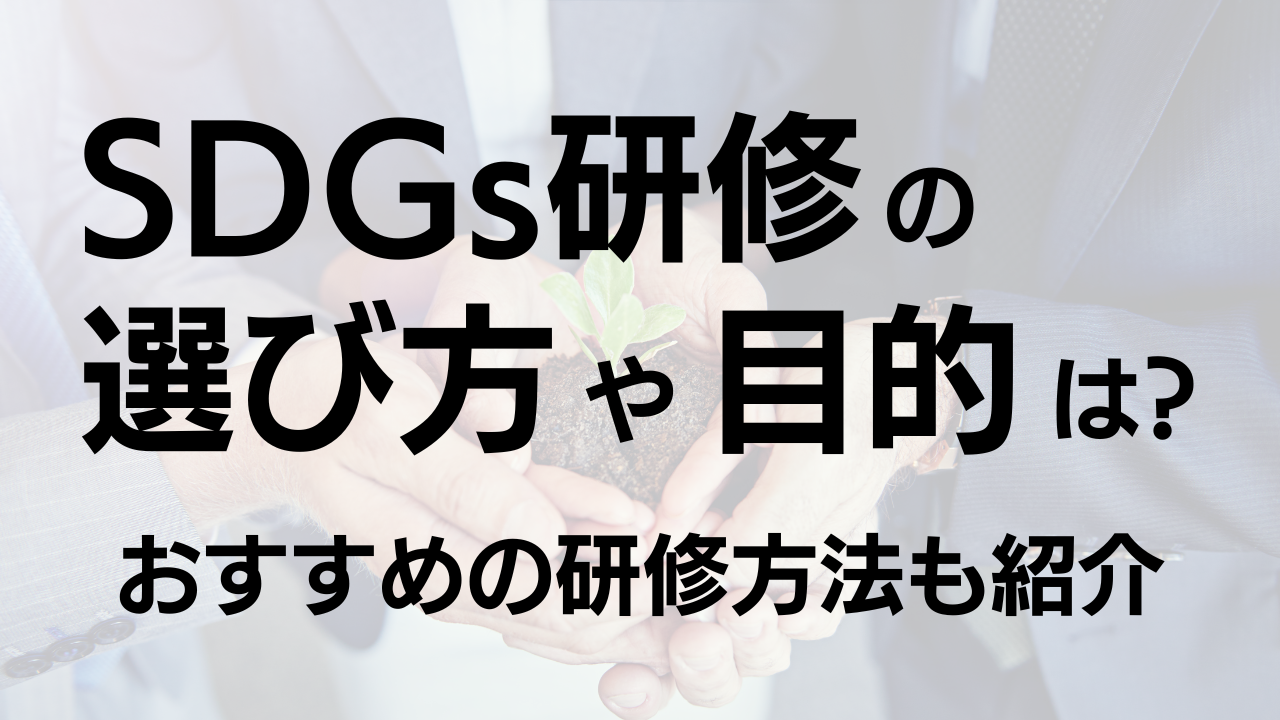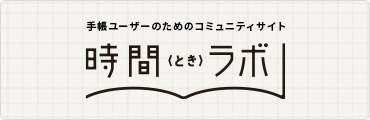「パーパス経営」という言葉は聞いたことがあっても、どのようなものかはよくわからないという方も多いでしょう。
そこで本記事では、パーパス経営の概要に加えて、メリットや注目される理由を解説します。パーパス経営について知っておきたい方はぜひご覧ください。
目次
パーパス経営とは

パーパス経営とは、社会における企業の存在意義を重視した経営手法のことです。パーパスとは、直訳すると「目的」や「意図」といった意味です。企業としての利益を追求するだけでなく、社会の中で果たすべき役割を踏まえて経営方針を決定するやり方のことを指します。
利益重視で運営している企業は、自然環境や従業員への悪影響など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。しかし、企業が利益だけを追求して社会問題を起こす状況は、社会にとって好ましいものではありません。
そこで、企業が社会に貢献していることを示すためにパーパス経営が注目されています。
パーパス経営と混同されがちなものとして「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」があります。
MVVとは、次の3つを経営の中心に据えてビジネスを進める考え方です。
M(ミッション):果たすべき使命
V(ビジョン):目指すべき未来像
V(バリュー):求める価値
MVVでは、必ずしも社会との関係を視野に入れて策定する必要はありません。一方パーパス経営では、社会の中でどのような役割を果たすかを中心にパーパスを決定します。
つまり、社会との関連の有無がパーパス経営とMVVのもっとも大きな違いといえます。
パーパス経営のメリット

パーパス経営を行うメリットは主に次の4つです。
・ブランディングに役立つ
・従業員のモチベーションが高まる
・企業のサステナビリティが向上する
・ステークホルダーからの支持を得られやすい
それぞれ、詳しく解説します。
ブランディングに役立つ
パーパス経営は、企業のブランディングに役立ちます。社会に貢献するような企業の働きは、顧客をはじめとしたステークホルダーに良い印象を与えます。
社会貢献を打ち出すだけでなく、実際にパーパスの達成に向けて行動していることをアピールできれば、評価はさらに高まるでしょう。
また、「あの企業といえば〇〇」のように、企業と社会貢献の内容を結びつけて覚えてもらえる可能性もあります。
行動を続けるうちにだんだんと応援してくれる人が増え、ブランディング向上に役立ちます。
従業員のモチベーションが高まる
パーパス経営によって、従業員のモチベーションが高まる可能性もあります。パーパスを設定すると、従業員はその企業で働くことが社会貢献に繋がることを実感できるようになります。
ただ仕事をしているだけでなく、それが社会的に意義のあるものとなれば、社員は仕事に誇りを持てるようになるでしょう。仕事を誇らしく思う気持ちが、社員のモチベーションを向上させ、より積極的・自発的な動きに繋がる可能性もあります。
企業のサステナビリティが向上する
パーパス経営を行うことで、企業のサステナビリティも向上します。いくら企業単体で利益を出していても、それが地域社会や従業員に負担となっているようでは、持続可能とはいえません。
社会的な立場をふまえたうえで経営方針を決定するパーパス経営であれば、身の回りの自然や従業員の労働環境にも注目しながら進むべき方法を決めるため、結果的に企業のサステナリティが向上します。
ステークホルダーからの支持を得られやすい
パーパス経営は、社会的な課題に対しての自社の取り組みを示すものと言い換えることもできます。そのため、ステークホルダーからの支持を得られやすいのも特徴です。
特に、ステークホルダーにとって身近な問題に取り組むと支持が得られやすい傾向があります。ただし、経営である以上、社会に貢献できるかだけでなく、利益が出るかどうかも考えなければなりません。
パーパス経営が注目される理由

近年、パーパス経営が注目されているのには次のような理由があります。
・SDGsに取り組む企業の増加
・社会貢献意識の高まり
それぞれ、詳しく解説します。
SDGsに取り組む企業の増加
人類がこのままの生活をしていては、将来環境破壊が進んでしまうという危機感が世界的に高まっており、SDGsに取り組む企業が増えています。パーパス経営は、社会問題に目を向けながら経営方針を決める手法です。そのためSDGsへの取り組みと相性が良いといえます。SDGsへの取り組みとパーパス経営を同時に取り入れることで、より社会的意義のある活動を行えるでしょう。
社会貢献意識の高まり
近年、企業だけでなく消費者の社会貢献意識が高まっています。特に、ミレニアル世代と呼ばれる1980年から1995年にかけて生まれた世代は、エシカル消費を重視する傾向があります。
エシカル消費とは、消費者それぞれが持っている問題意識に対して、積極的な取り組みを行っている企業の商品・サービスを選択する考え方です。社会貢献意識の高い企業の商品やサービスを選ぶことが、ユーザー自身の社会貢献になります。
そのため、どのような課題に取り組むかというパーパスをはっきり打ち出すことで、エシカル消費を意識するユーザーから選ばれる可能性が高まります。
パーパスを設定する際のポイント

パーパス経営を行う際に設定すべきパーパスとはどのようなものなのでしょうか。
パーパスを設定する際のポイントは次の5つです。
・社会課題を解決できるか
・事業と関連しているか
・利益を出せるものか
・無理なく実現できるか
・社員のモチベーションを高められるか
それぞれ、詳しく解説します。
社会課題を解決できるか
前述のとおり、パーパス経営とは社会の中での企業の意義を考えながら経営を行うものです。つまり、設定するパーパスは社会課題を解決できるものでなければなりません。
社会課題の例としては、例えば気候変動や少子高齢化、食料問題などが挙げられます。社会課題は数多くあるので、まずは自社の活動で貢献できそうなものを選んでみましょう。
事業と関連しているか
自社の事業と関連したパーパスを設定することも重要です。自社の事業に関連したパーパスであれば、事業活動の中で自然と社会に貢献できます。
逆に、事業と無関係な問題を選んだ場合、パーパスを達成するためだけに行動する人員や時間が必要となり、効率が良いとはいえません。
利益を出せるものか
パーパスを設定するのは経営のためです。そのため、社会的課題を解決するだけでなく利益を出せるものでなければなりません。
パーパスを設定する際には、事業として取り組み、利益が出せるかどうかも考慮する必要があります。
無理なく実現できるか
無理なく実現できるパーパスを設定することも重要です。経営資源をふんだんに投入し、やっとのことで達成できるハードルの高いパーパスでは、一時的には達成できてもその後継続するのは難しいでしょう。
無理なく実現できるパーパスを設定し、継続的に取り組みを続けていくことが重要です。
社員のモチベーションを高められるか
パーパスを設定する際には、社員のモチベーションを高められるかも考慮しましょう。社員のモチベーションを高められれば、自発的な取り組みが期待できます。
また、社員が会社に誇りを持てるようになれば、離職率が低下する可能性も高いです。そのため、パーパスは社員のモチベーションを高められるものを選ぶ必要があります。
パーパス経営について理解を深めよう
パーパス経営とは、社会の中で企業がどのような役割を果たすかに重点をおいて経営する手法のことです。企業のブランディングに役立つだけでなく、ステークホルダーからの支持を集めやすいといったメリットもあります。
パーパスを設定する際には、いくつかのポイントを押さえることが必要です。まずは、パーパス経営について理解を深めるところから始めてみてはいかがでしょうか。